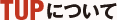英植民地では米国に四半世紀先駆けて奴隷制が廃止されていた。それはどうしてなのか。廃絶運動の担い手は誰で、どのように運動は広がったのか。
この記事はMother Jones.com他のサイトに独立した記事として掲載されているが、今秋英国で、そして来年一月に米国で出版される予定の英国奴隷解放史の、著者自身による要約でもある。
この本は、歴史研究者のみならず、21世紀の現代社会において政治運動に真摯に取り組む、あらゆる市民にとっても必読書になりそうな一冊。そのエッセンスがここに凝縮されている。
1年前TUPが始まって以来おそらく最大の分量です。プリントアウトなどなさって、どうぞごゆっくりお読みください。(和氣久明/TUP)
(★以下[ ]内は訳者注)
原題: "Against All Odds" by Adam Hochschild
原文URL: http://www.motherjones.com/news/feature/2004/01/12_403.html
FROM: Schu Sugawara
DATE: 2004年3月10日(水) 午前0時26分
英植民地では米国に四半世紀先駆けて奴隷制が廃止されていた。それはどうしてなのか。廃絶運動の担い手は誰で、どのように運動は広がったのか。
この記事はMother Jones.com他のサイトに独立した記事として掲載されているが、今秋英国で、そして来年一月に米国で出版される予定の英国奴隷解放史の、著者自身による要約でもある。
この本は、歴史研究者のみならず、21世紀の現代社会において政治運動に真摯に取り組む、あらゆる市民にとっても必読書になりそうな一冊。そのエッセンスがここに凝縮されている。
1年前TUPが始まって以来おそらく最大の分量です。プリントアウトなどなさって、どうぞごゆっくりお読みください。(和氣久明/TUP)
(★以下[ ]内は訳者注)
原題: "Against All Odds" by Adam Hochschild
原文URL:
http://www.motherjones.com/news/feature/2004/01/12_403.html
―――――――――――――――――――――――――――――――――
世界は変えられる――英国奴隷解放史
アダム・ホークシルド 『マザー・ジョーンズ』2004年1・2月号
―――――――――――――――――――――――――――――――――
■目次
- はじめに
- 「積荷」の海上投棄
- 「わたしの中で燃える義憤の炎」
- 「奴隷貿易の成功を祈って」
- 血で甘く味付けされた飲み物
- 政治書籍の史上初のプロモーションツアー
- 逸(そ)らされた運動
- 「わたしの子供たちは自由になるでしょう」
- 結論:世界を変える
はじめに
この街では有名な事件が起きたり名士が住んだりしたところには、必ず青と白の記念銘板[プラーク(末尾注1参照)]が設置されているものなのに、この場所にはなぜか何も標示がない。ロンドン地下鉄のバンク駅を出て1、2ブロック東に歩いてからさらに数歩進んで広場に入ったところに今日見られるものはただ、特徴のない低いオフィスビル2軒と古い居酒屋、そしてジョージヤード2番地というまさにその場所に建つ、ガラスと鋼鉄でできた高層ビルのみである。かつてここに建っていた書店兼印刷屋もなければ、1787年の夕方に、12人の人々が列をなして戸口をくぐり、着席し、史上最も遠大な目標を掲げた市民運動のひとつを始めたことを思い起こさせる徴(しる)しは何も残っていない。この12人のうち、一人はみすぼらしい身なりをした船員、一人は牧師の黒衣をまとい、残りのほとんどが幅広のつばのついた独特の黒い帽子[クェーカー教徒が愛用する]を被(かぶ)っていた。都市というものは王族や将軍たちの記念碑を作りはしても、本屋などに集った人々の記念碑を作ることはないのだ。けれども、この市民たちが行ったことは、実に世界中に影響を及ぼしたのである。たとえば、今日市民社会と呼ばれているものを取り上げた、最初にして最大の研究家から賞賛を得たほどだった。かれらが達成したことは、「歴史上まったく先例がなかった。あらゆる民族の歴史を紐解いてみてもこれほど並外れたものはまず見つからないだろう」と記したのは、かのアレクシス・ド=トックビル[(1805-59)フランスの政治家・歴史家、『アメリカの民主主義』(1835)で著名]だ。
ジョージヤード2番地で始まったこの出来事がいかに重要なものだったのかを理解するには、1787年に世界がどのような状況だったかを想像してみればよい。当時地球上の総人口の4分の3を優に超える人々が、どこか特定の土地に束縛されていた。南北アメリカ大陸には自由民の人口を上回る数の奴隷がいる地域が複数存在していた。イスラム世界の多くにもアフリカ系の奴隷が広く散在していた。そもそもアフリカ大陸では、大部分の地域で奴隷制度が通例であった。インドでもアジアの他の多くの地域でも、明らかに奴隷状態の人々がいたし、他にも北米南部の大農園所有者に奴隷が隷属していたのと同じくらい過酷な条件で、借金のために特定の領主に隷属する人々がいた。ロシアでは人口の大多数が農奴であった。しかし英帝国の海外領土ほど奴隷制度が固く根付いていた場所はほかになかったのだ。そこでは、約50万人の奴隷が西インド諸島原産のサトウキビ農業で労役を強制され、若くして命を落としていった。カリブ海諸島の奴隷農場の財産は、数多くの強大な家系の資金源となり、その中にはエリザベス・バレット・ブラウニング[英国の詩人。詩人ロバート・ブラウニングの妻]から、息子のピアノ教師にモーツァルトを雇う大富豪のロンドン市長ウィリアム・ベックフォードにいたる人々もいた。バルバドス[カリブ海東端の島国]の最も裕福なサトウキビ農園のひとつは英国国教会が所有していたほどであった。さらに、奴隷売買を支配していたのは英国の船舶であり、それらは捕獲された人々を鎖に繋(つな)いで、本国の植民地同様にフランス、オランダ、スペイン、ポルトガル諸国の植民地へと毎年何万人も送り込んでいたのだ。
1787年初頭のロンドンで、もしこのすべてを変えようと提案したとしたら、10人のうち9人に「正気かい」と一笑に付されていたことだろう。10人目にしてようやく「奴隷制度は不快だよね」と同意してくれる人がいたかもしれないが、その人でも「奴隷制を終わらせようとすれば、英帝国の経済を破綻させることになるのでは」と留保をつけたことだろう。それはまるで今日の社会から自動車を一掃するべきだと提案するようなものだからだ。10人に一人くらいは「みんなが徒歩や自転車、あるいは電車やトロリーバスで旅行をするようになったら、確かに世界はもっと良くなるだろうけど、自動車廃絶運動なんて現実味がないぜ」と言うのではなかろうか。しかし、振り返ってみれば、奴隷制の拡散よりもさらにずっと驚くべきなのは、それがいかにすばやく消滅したかということである。奴隷制度は19世紀の終幕までに、世界のほとんどあらゆる地域で違法とされたのだ。アメリカの小学生はみな米国史で「地下鉄道」[南北戦争以前に奴隷の脱出を助けた秘密組織]や奴隷解放宣言を教わるのだが、この国の自己中心的な教科書は当時の超大国[英国のこと]で、ほぼ四半世紀早く奴隷制度が廃止されていたという事実を端折(はしょ)ってしまうことが多い。けれども、南北戦争に先立つ20年以上もの間、米国北部でアフリカ系の自由民たちが熱狂的に祝っていたのは、(酔っ払った白人の暴徒たちによって襲われる危険性があった)7月4日[米国の独立記念日]ではなく、大英帝国における奴隷解放の日である8月1日だったのだ。
1. 「積荷」の海上投棄
1783年3月18日、『モーニングクロニクル&ロンドンアドバータイザー』紙の読者投稿欄に短い手紙が紹介された。ロンドンの裁判所で聴聞が進んでいたある事件についての手紙であった。これが元奴隷で英国に住んでいたオローダー・エクイアーノの目にとまる。恐怖にかられたかれは、ただちに知人の英国人グランビル・シャープのもとへと走った。かれは変わり者の言論家[原語は pamphleteer。自分の意見を広めるために、時に自らパンフレットを発行していたもの書きたちのこと]であったが、奴隷制度反対者としても知られていたからである。シャープは日記にこう記録している。エクイアーノが「わたしを訪ねて来た時、かれが携えていたのは130人もの黒人が生きたまま海に投げ込まれているという記事だった」
これより数か月前、ゾング号という帆船が、ルーク・コリンウッド船長の指揮下で、およそ440人の奴隷を乗せてアフリカからジャマイカへと向かっていた。そのうちの多くは、すでに何週間も船上にいた。逆風があるかと思えばしばしの凪(なぎ)が続いた上、さらに操船上の不手際が加わり(なんとコリンウッドは、ジャマイカを別の島と勘違いし、ついうっかり通り過ぎてしまっていたのだ)、この大西洋横断の旅は通常より二倍の時間がかかっていた。わずか107トンの小型船にびっしりと詰め込まれた奴隷たちは次第に病に冒され始めた。有能な船長なら積荷は適度な健康を保って運搬しなければならず、まして死んでしまったり、死にかけている奴隷は儲けにならないので、コリンウッドは頭を抱えた。だが、抜け道はあった。もしコリンウッドの手に負えない理由で奴隷が死亡した場合には、一人あたり30ポンドの保険が損失を埋め合わせてくれることになっていたのだ。
コリンウッドはリーダー格の船員たちに、最も病状の進んだ奴隷を海に投げ捨てるように命じた。かれは、もし質問された場合、風向きが悪くて船の飲み水がなくなりそうだと答えるように、とも指図した。もし備え付けの飲料水が尽きつつあったなら、この殺人行為も航海法の「投棄」原則のもとで容認されるはずだった。つまり、船長は他の積荷を救うために一部の積荷――むろんこの場合は奴隷のこと――を海に捨ててもよいことになっていたのだ。かくして、合計133人の奴隷が数回に分けて海上に「投棄」された。最後のグループは抵抗を示したので、うち26人が腕に手かせを付けられたまま海に放り込まれたのである。
後日ゾング号の船主たちが死んだ奴隷たちの対価請求を保険会社に提出したところ、それが今日の金額で言えば50万ドル[現在のレートで約5500万円]以上にも上ったので、保険会社は請求を棄却したというわけだった。エクイアーノにこの記事を示されるや、グランビル・シャープはただちに行動に移る。かれは複数の弁護士を雇い、裁判所へと出向き、この船の乗組員の少なくとも一人と乗客一人に個人的に接見した。けれど今日のわたしたちと同様、当時のエクイアーノやシャープにとってもショックだったのは、百人以上もの人間が船から投げ落とされて死亡したにもかかわらず、この件が殺人事件としてではなく、保険に関する民事裁判として扱われたことである。
シャープはゾング号の船主たちを殺人罪で告発しようとしたが、それは失敗に終わった。それでもかれは自分の考え付く限りのあらゆる人に向け、事件に関する熱心な手紙の一斉射撃を放った。その中の一通はどうやら有力な牧師の元へと届いたようだ。その牧師は翌年ケンブリッジ大学の副チャンセラー――米国の大学で言えばプレジデント、つまり学長にあたる――となった人物である。かれはこの件を知って非常に動揺し、自分が行使できる最も強力な道具をひとつ用いた。毎年恒例のケンブリッジ大学のラテン語論文コンテストの課題を、「奴隷制度の道徳性について」としたのだ。
当時英国の大学生活ではギリシア語ラテン語による論文の出来を競うことが学生の主要活動となっていた。大きなコンテストで優勝することは今日の米国でローズ奨学金[オックスフォード大学で学ぶ英連邦、米国、ドイツからの留学生を対象にした奨学金]やハイスマン杯[米国の大学フットボール年間最優秀選手賞]を受賞することに匹敵した。この栄誉は生涯にわたり当人の名前に付いて回ったのである。このラテン語論文コンテストの応募者の中にトマス・クラークソン[1760-1846]という25歳の神学生がいた。後にかれが書いているところによれば、これ以前にかれはまったく奴隷制度への関心を持っておらず、「ただ論文コンテスト優勝の名誉を手に入れたかっただけだった」。しかし、入手可能な文献をすべて読み、最近物故した奴隷商人の残した文書を調べ、南北アメリカで奴隷制度を間近に見てきた上級船員たちと面会するうちに、予期に反して、クラークソンは自分が圧倒されるのを感じた。かれはこう書いている。「日中落ち着かず、夜もほとんど眠れなくなった。悲嘆のために両目蓋を閉じられないことさえあった。心に考えが浮かんできた時すぐに寝床から起き上がってそれを書き留められるよう、いつも寝室にろうそくを点けておき、かくも重要なテーマに取り組む以上、議論のアイディアがひとつも失われることのないように努めた」
かれの論文は一等賞を受賞した。1785年6月の授賞式に際して、瀟洒(しょうしゃ)なケンブリッジ大学評議員会館で、クラークソンは聴衆に向かってこのラテン語論文を朗読した。その後学業を修了したかれは早々と[教会職の]執事の黒衣を身にまとい、前途有望な教会職に就こうとロンドンを目指した。ところが自分でも驚いたことに、かれは奴隷制度によって「自分の頭の中が完全に占められてしまっている」のに気づく。「ハートフォードシャー[大ロンドン圏周縁の北部に位置する]のウェイズミルが見えてきたあたりで、わたしは気が滅入って来てしまい、路傍の歩道に腰を下ろして馬を休ませた。この時こんな考えが心に浮かんできた。もしもあの論文の内容が真実だとしたら、誰かがこの悲惨を終わらせなくてはならないのではないか」
2. 「わたしの中で燃える義憤の炎」
「誰かがこの悲惨を終結させなくてはならない時が来ている」――英帝国において反奴隷制運動が不可避となった時点があるとすれば、それはトマス・クラークソンが馬を降り、道端に腰を下ろしたこの時にほかならない。かれは再び馬にまたがりロンドンへの道を進んだが、心に抱いていたのはまず何よりも件(くだん)の論文を英語で出版することであった。ロンドンのある著名な出版人の事務所を訪ねたところ、その人物は論文に関心を抱いてくれたものの、それは受賞があったからにすぎなかったことがわかり、失望を味わった。クラークソンは「この論文がそれにふさわしい道を見つけること、つまりわたしとともに考え、行動する人たちに読まれることを望んでいた」のだ。かれはこの出版人のオフィスを辞するとすぐに、そのまま同じ通りの、かれの家族の友人であった、あるクェーカー教徒の家に駆け込んだ。当時クェーカー教徒たちは奴隷制反対を唱道する唯一の宗派だったからである。するとその人物は、こう述べた。「クラークソンさん、あなたこそまさにわたしが探していた人だ。ご論文をぜひ出版しましょう」
ふたりはともに数ブロックを歩き、ロンドンの商業地区の、細く曲がりくねった通りが入り組む、ごみごみした一角にあるジョージヤードのジェイムズ・フィリップスの書店兼印刷所へ向かった。当時は、本の販売も出版も印刷も通常同じ屋根の下で行われていて(上の階に印刷者の家族が住むことも多く、裏庭には牛や豚の一匹や二匹飼われていたかもしれない)、フィリップスはこうして少数派である英国のクェーカー教徒たちのために仕事をしていた。フィリップスはすぐにクラークソンを気に入り、その場で件の論文の出版を約束する。この日こそまさにクラークソンが自分は孤独ではないと悟った日であった。
かれは激しい決意を固め、奴隷制度について調べられる限りのことをすべて調べ尽くすことに傾注した。テムズ川沿いの船着場からは多くの船がアフリカへ出航していたので、さっそく一隻に乗り込んで調査してみると「たちまち自分の中に怒りの炎が燃え上がるのを感じた」とかれは書いている。また、当事者情報を持っている人々、つまり、商人、船長、そして陸海軍の将官たちに体系立てて会うようにした。すぐれた報告者特有の本能的な判断から、「会話の後、その場で起こったことのすべてを書き留めて記録するようにした」
こうした仕事で力を合わせる主体となったのが、クェーカー教徒たちであったことはいうまでもない。かれらは固い信念を持ち、小規模ながら熱心な参加者からなるネットワークを国中に張り巡らせていた。むろんクェーカー教徒側にとっても、クラークソンその人が神からの賜物であることは明白だった。かれは若く、活力に溢れ、またなによりも重要なことに、英国のあらゆる場面で権力を持つ英国国教会の信徒であったからだ。クェーカー教徒たちの反奴隷制の運動がそれまでまったく実を結んでいなかったのは、ひとえにかれらがクェーカー教徒だったからである。人々はかれらのことを、「汝を」とか「汝は」などという奇妙な言葉遣いをし、説教やお祈りの時以外はあの目立つ黒い帽子を脱ごうとせず、曜日や月の名前が聖書からではなく、ローマ神話や異教の神々から取られたという理由でそれらを使おうとしない変わり者たちだと揶揄(やゆ)していた。世論を左右するために、クェーカー教徒たちはこの運動に全精力を注いでくれる有能な英国国教徒を必要としていた。クラークソンはかれらがついに見つけた待望の人物だったのだ。
クラークソンとクェーカー教徒の賛同者たちは共同で、慎重に国教とクェーカーの両方を広く組織する計画を立てた。「馬に乗って街へ行き、設立されたばかりの奴隷貿易協会の集まりに参加した」と、あるクェーカー教徒は日記に記している。1787年の5月22日の午後遅く、12人の男たちが初めて正式にジェイムズ・フィリップスの書店兼印刷屋に集合した。おそらく印刷工たちはすでに家路に着いており、やかましい音をたてる平台型のプレス機は片付けられていたことだろうが、まだ裁断されていない本の大判のページが頭上の天井に作りつけられた木製の棚からぶら下がり、印刷されたインクを乾かしているところだったであろう。
この協会がターゲットとしたのは奴隷制度そのものではなく、奴隷貿易であった。なぜなら、後者の方が前者よりも政治的に廃絶が達成しやすい射程にあり、また結果的に前者も終わらせることができそうに思われたからだ。西インド諸島の奴隷制度は、いかなる観点から見ても、他のほとんどの地域の奴隷制度にまして苛烈を極めていた。照りつける太陽の下で手作業でサトウキビを耕作するのは地上の最も過酷な仕事のひとつであったし、それは現在でも変わらない。熱帯特有の病疫は手に負えず、奴隷の食事は米国南部のそれよりはるかに劣っており、奴隷たちの子供の数もずっと少なかった。残虐を極めるカリブ海諸島の大農場[プランテーション]での死亡率は非常に高く、アフリカからの新規奴隷の着実な補給がなければ、現地の奴隷人口は年率3パーセントもの減少を示していただろう。奴隷解放主義者たちは、奴隷貿易を止めさえすれば、奴隷制度そのものがやがて成り立たなくなるだろうと信じていたのだが、これは少々甘かった。
圧倒的大多数が奴隷制度を当然視する国で、協会はその改革運動を開始せねばならなかった。大農場から出る利益が英国経済にとって大きな景気刺激剤となっている上に、およそ何万人とも思われる数の船乗り、商人、造船工の生活が奴隷貿易にかかっていた。そもそも、世論変革という途方もない大仕事をどのようにして始めるというのか。英国男性は10人のうち9人以上、英国女性は全員、選挙権すら持っていなかったのだ。これほど基本的な権利さえ認められていないのに、他者の権利、しかも異なる肌の色をした海の向こうにいる人々の権利を考える気にさせることなど不可能に近かった。
人類史上、このような政治運動の先例はない。
3. 「奴隷貿易の成功を祈って」
1787年6月、トマス・クラークソンはふたたび馬に乗り、当時奴隷運搬船の発着地となっていた、ブリストルとリバプールの大規模な港へと出かけた。最終的に国会の聴聞で証言をしてくれそうな奴隷貿易の経験者を探していたのだ。かれは[オルグのための]パンフレットを配布し、また地域の奴隷制度廃止協会を穏当に準備しようともくろんでいた。驚くべきことにその後数年間、この運動の継続的な常勤オルガナイザーはかれ一人だったのである。
ブリストルに近づくにつれて、ある不吉な予感がクラークソンを襲った。「その時、街のあちこちから教会の鐘が鳴り響いていた。その音を聞くと、わたしの胸は憂鬱な気持ちで満たされた。この時初めて、目の前の大都会を支える通商機構の一部をひっくり返そうという困難な仕事に着手したことを自覚し、体が震え出した。わたしは生きてこの街から出られるだろうかと自問した」。これが根拠の無い怖れではなかったことが、後(のち)にわかる。
後年クラークソンが著したこの運動の自伝的な歴史によると、手にした文書の紙そのものにかれの怒りの炎が燃え移りそうな気がしたという。つまり、現在ナイジェリアになっている地域の海岸で英国の奴隷商人たちがおよそ300人のアフリカ人を虐殺したという情報を記した文書を調べていくうちに、「それはわたしの体の中で血を熱く煮えたぎらせたほどだった」と、かれは書いている。
クラークソンは6フィート[182センチ強]の長身で、濃い赤毛をしており、射抜くような碧眼で、相手の顔をまっすぐ見て話すタイプの男だった。そのかれがブリストルの通りを強い目的意識に駆られて歩き回りながら、自分の使命にはっきりと目覚めていく。「この時わたしは昼の時間が足りないと感じ始めていた。夕暮れが近づいてきて、仕事を中断しなくてはならないのを悔しいと思うことがよくあった」と、かれは書いている。
奴隷貿易の残酷さは、奴隷たちそのもの扱いだけに限らないことにクラークソンは気づいた。航海から帰ったばかりの奴隷船で、実に32人もの乗組員が航海中に死亡していた例があったのだ。船員総数がこれより少ない船も珍しくない。ジョン・ディーンという名の解放された黒人船乗りが受けた仕打ちは、「あらゆる想像を超えていた。船長はかれを甲板に腹ばいにさせ、動けないように縛りつけておいて、熱く焼けたピッチ[タールなどを蒸留した後に残る黒色の物質]をその背中に注ぎ、その上から焼け火箸で切り裂いて、切り口をつけたのである」と、クラークソンは記す。ディーンは失踪していたが、クラークソンは「ディーンの、傷付き変形した背中をしばしば見ていた」目撃者に出会った。
ひとつ発見するごとに、またひとつ別な発見へとつながっていった。たとえば奴隷船がかくも悪名高いほどに残虐だとしたら、なぜ船乗りたちは乗船契約を繰り返すのだろうか。数週間の間、クラークソンはブリストルの港町の居酒屋[パブ]を足繁く訪れて上級船員たちがどのようにして乗組員を雇うのかを観察した。「この港へ初めて来た若い船乗りで、奴隷貿易の正体がよく分かっていない者はまず必ず引っかかった」。最初に給料はいいし、女はたんまりいると告げられる。「それから酒をしこたま飲まされる。船乗りたちは居酒屋の上階にある宿に仮住まいしているのだが、奴隷船の出航直前に限って、払える以上の金を使うように仕向けられた」。居酒屋の主人はそこでおもむろに支払いを要求し、こう迫る。「払えないなら残る選択は二つにひとつ。奴隷船に乗るか、監獄に行きかだ」、と。
船長やその取り巻きたちは、クラークソンと口をきこうとしなかった。ところが、ある日路上で耳にはさんだ会話の一部に興味を覚えたクラークソンは、ある身なりのよい男の後を尾(つ)けてみた。後になってわかったことだが、その男は医者で、ジェイムズ・アーノルドという名前であった。かれは過去2回、奴隷船航海に同行し、それについて胸が悪くなるくらい詳細にクラークソンに説明してくれ、さらに3回目の航海に出ようとしているところだった。(健康な奴隷は高く売れたので、奴隷船には医者が同乗することが多かったのである。)アーノルドは、「わたし[クラークソン]のような人物と出会ったことに多少不審感を抱いていた」が、それでも大胆に話をしてくれて、自分が「金に困っているから航海に出るのであって、今回生きて帰ることができればもう二度と奴隷船には乗らない」と語った。かれはアーノルドに、「航海中の事実を日記に書き留め、帰って来た時にもし求めがあれば、それを証拠として提出してくれる気があるか」持ちかけてみたところ、答えはイエスであった。
クラークソンは数度にわたり、奴隷船の船長たちが殺人罪で告訴されるよう骨を折った。この試みはいずれも実を結ばなかったが、この風評がロンドンに伝わり、奴隷制度廃止協会に属する謹厳なクェーカー教徒の事業家たちは、クラークソンが静かに調査すればいいのに、少々闘争的になりすぎているのではないかと懸念した。一人はクラークソン宛ての手紙にこう書いた。「汝がこの大義に没頭し熱意と精力を傾けても、慎みと手加減をお忘れにならぬよう」
しかしクラークソンは、当時世界最大の奴隷貿易港でその年には81隻の奴隷船をアフリカに送り出していたリバプールへ馬で赴いた際も、手加減など見せはしなかった。とある船舶向け雑貨商の店の前を歩いて通り過ぎようとした時、かれはショウウィンドウ越しに見えた手かせ、足かせ、そして親指締め[拷問用具]に戦慄を覚えた。かれはさらに螺子(ねじ)回しのついた外科手術用の器具にも目を留めた。これは[破傷風の初期症状などの]開口障害の際に用いられるものだったが、店員の説明によれば、船に乗せられた奴隷が食事を取るのを拒否して自殺するのをやめさせるために口をこじ開ける道具であるという。クラークソンはこれらの器具をひとつずつ買い求め、その後立ち寄る町ごとに、地元の新聞の編集者の前で広げてみせた。かれは単独で運動を組織するだけでは足りず、メディアを動員した運動が必要なのだとわかってきていた。
かれがリバプールで泊まっていた「キングズアームズ」という名の宿で、ある時食堂でかれを指差す男たちがいて、「航海の成功を祈願する乾杯の声が上がった。かれらは不穏な笑い声を放つとわたしがジョッキに手をかけてビールを実際に飲むかどうかじっと見守っていた」。やがて、かれは匿名の脅迫文を受け取るようになる。ある日強風の中、埠頭の端で振り返ると、「8、9人の者たちがわたしに向かって歩いてきた。かれらはわたしに近づき、さらに間を詰めてきた」。この集団の中には、かれが殺人罪で告訴しようとしていた奴隷船の上級船員たちが一人いた。もしもこの時かれが上背のある強靭な体躯をしておらず、当時の英国人の多くがそうであったように泳げなかったとしたら、おそらくひどい怪我を負わされるか、最悪の場合死を覚悟せねばならなかっただろう。「すぐに、この連中はわたしを埠頭から海に投げ込む気でいるのだとわかった。これは一刻の猶予もない。わたしは一心不乱に駆け出した。一人、わたしがぶつかった相手が転倒した。なんとか逃げおおせたが、まったくパンチを食らわなかったわけではないし、さんざん罵倒と悪態を浴びもしたのであった」
4. 血で甘く味付けされた飲み物
ロンドンではすでに協会が熱心に支持者を募り、書物やパンフレットを配布していたので、クラークソンが戻ってから2、3か月のうちに、世論には劇的な変化の兆候が現れていた。当時はギャラップ世論調査[統計学者G.H.ギャラップ (1901-84) が創設した機関が行っている標本抽出調査法]などなかったが、大衆の嗜好を巧みに探ることで生計を立てている事業者の一団があった。つまりロンドンの複数のディベートクラブ運営者たちである。(たとえばよくセックスが取り上げられて、「夫婦が流行の不倫に手を染めるのは、夫の側の堕落に帰するべきなのか、それとも妻の側の心変わりに帰するべきなのか」という風に、常に格好のディベートトピックとなっていた。)これらのディベートクラブでは、奴隷制度がまず滅多に取り上げられることのない時期が何年も続いていたのに、突如1788年2月のロンドンの日刊紙によると、一般市民参加のディベート大会で、全14のうち半数が、奴隷貿易廃止をディベート課題に掲げた。
ある新聞広告は「アフリカ出身者で何年間も西インド諸島で奴隷であった人」が演説をすると約束していた。その匿名のアフリカ人とはおそらくオローダー・エクイアーノ[1750?-97]のことだっただろう。また別の新聞記事にはこうあった。「いまだかつてディベートクラブで見られたことのない状況が目撃された。ある女性が課題について、参加者全員を驚かせたほどの威厳と精力、そして知識をもって演説したのだ。その婦人の立場は奴隷貿易反対であった」。学者たちによると、宗教的な集会を除けば、黒人ないし女性が英国でパブリック・スピーチをしたのは、これらが史上初の機会であっただろうということである。
民衆感情の最も重要な表明はごわごわした大判羊皮紙の巻物に現れた。この年の国会の会期が始まるまでに、奴隷制度の廃止ないし奴隷貿易の改革を求める請願書が、実に6万人以上もの署名を集めていたのである。選挙権保有者でも貴族院に影響力を持たず、また成人男性の10人に1人以下のみしか下院選挙の投票権を持たない国では、請願書は古い歴史を持ち、尊重される政治的圧力の手段であった。反奴隷貿易の請願書の数は、それ以前にはまったく見られなかったのに、突如として、他のあらゆる議題に関する請願書を合わせた数よりも多くなっていたのだ。
みごとに組織化された奴隷制度廃止協会は、それ以降現在に至るまで用いられている新しい手法もいくつか開拓した。たとえば、「わが国の親愛なる友へ活動の現況を知らせるための手紙」なるものを定期的に発行していた。これは印刷物と電子情報とを問わず、今日の活動家たちの諸グループが発行する夥(おびただ)しいニューズレターの元祖といえる。協会はまた、大ロンドン圏でかつて寄付をしてくれたことのある篤志家たちにもう一度、せめて前回と同じ額の寄付をしてくれるように依頼する文書を送ることでも同意をみた。これが史上初のダイレクト・メールによる運動資金集めの手紙だったかもしれない。
著名な陶芸事業家であった片足のジョサイア・ウェッジウッド[(1730-95)]がこの会に参加した際、かれは部下の職人の一人に命じて鎖に繋(つな)がれ膝まずいている奴隷の像のまわりを「わたしは人間でも同胞でもないのか」という銘が囲む浅浮彫[バス・レリーフ]のメダルを拵(こしら)えさせた。[(末尾注2参照)]米国人で奴隷解放運動の理解者だったベンジャミン・フランクリン[米国の政治家・著述家・発明家(1706-90)]は、この奴隷像を見て感動し、このメダルは「最良の意見論文にも匹敵する」影響力を持つと言明した。クラークソンは組織作りの道すがら、このレリーフメダルを500枚配って歩いた。「女性の中にはこれをブレスレットとして身につける人もいれば、髪かざりとしてピン止めする方々もいた」。現代のわたしたちが選挙運動で襟の折り返しにつけるバッジと同様のもので、おそらくロゴが政治運動で用いられた史上最初の例であった。つまり18世紀の「ニューメディア」だったわけである。
数年のうちに別の戦略が草の根から生じてきた。ブリテン諸島のいたるところで、英国の奴隷たちが収穫した主要産品、つまり砂糖を口にするのをやめる人々が出てきたのだ。クラークソンは「人々が自ら対症法を手に入れようとしている」と、喜んだ。「わたしが道中に書き留めていたメモから推察するに、富める者も貧しき者も、国教徒も非国教徒も問わず、実に30万もの人々が砂糖の使用をやめたのだ」。また、今日で言えば「フェアトレード」のラベルがついた食品さながら、広告がたちまち新聞を埋め始めた。「砂糖精製業者ベンジャミン・トラバース社より各位に告知。わが社の板砂糖、角砂糖、粉砂糖、シロップを各種取り揃えて売り出し中。いずれも『自由民』の労働によるものです」。現在も同様だが、当時経済のグローバル化はほとんど目に見えなかった。このボイコットが人々の想像力を捕らえることができたのは、隠されていたつながりを白日の下にさらしたからである。ロバート・サウジー[英国の詩人(1774-1843)]は紅茶を「血で甘く味付けされた飲み物」と呼んだ。
奴隷制度推進派たちは、慄然とした。ある者は反論を出し、「砂糖は贅沢品ではなく、生活必需品だ。砂糖をまったく使わないことで、大勢の人々が体に甚大な損害を与えているのだ」と主張した。
一方、奴隷制廃止論者たちは、さらにもうひとつ主要な運動の手段を編み出した。奴隷制度を取り上げたテレビ番組や絵本にはかならず出てくるので、読者にもおなじみだろう。[缶入り]鰯(いわし)のように船倉にぎゅう詰めにされた奴隷たちを、上から見た詳細な見取り図のことだ。これはリバプールのブルックス号という実在した船の絵だった。クラークソンと仲間たちがこの図を手際よく8700部も印刷し、それらがまたたくまに国中の家や居酒屋の壁に掲げられたのである。この企画のすばらしさは、反撃の余地がないことであった。奴隷制度推進派が対抗しようとして、船上でさも幸せそうな奴隷たちの姿を描いても説得力などあるはずがない。控えめながら正確で、また赤裸々なまでに雄弁でもあるこの図は、広く複製された最初の政治ポスターとなった。
5. 政治書籍の史上最初のプロモーションツアー
歴史上被抑圧者が蜂起したことはあるが、英国における反奴隷制の動きは、誰か他の人のための権利のために大規模な政治運動が持続的に取り組まれた世界最初の事例であった。英国人というのは、時として自己の利益に反することについてでも自らを組織化することができたようである。1789年に、鋏(はさみ)、鋤(すき)、ナイフ、髭剃りなどの製造で有名なシェフィールド[イングランド北部サウス・ヨークシャーの州都・工業都市]から、769人の金属工たちが国会に請願書を提出した。かれらの手になる刃物は奴隷買い入れの際の代価用として船長たちに売られていたから、奴隷売買を許容すると期待されていたのが不本意で、かえって奴隷売買に激しく反対したという。いわく、「われわれ請願書の提出者たちは、アフリカの人々の問題を自分自身のこととして受けとめている」
アフリカの人々の問題を「自分自身のこととして」受けとめるとは、何を意味していたのだろうか。ジャマイカの農園経営者たちの代理人であり、奴隷制推進派の主要人物であったスティーブン・フラーは困惑してこう書いている。国会に押し寄せる請願書には、「請願者各自に影響を及ぼすようなことは、苦情にせよ土地などの損失にせよ、一切述べられていなかった」、と。確かにかれが戸惑うのも無理はない。これは人類史上、まったく新しい出来事だったのだ。
同じ頃、この国で巻き起こりつつあった反奴隷制の熱狂の炎に油を注ぐものが、もうひとつ現れた。奴隷時と自由民になってからの生活を鮮やかに描いた、オローダー・エクイアーノの自伝である。一部7シリングで売られたこの本は、一躍ベストセラーとなった。エクイアーノは、5年という稀なほどの長い時間をかけて、この本を英帝国中に広めて歩いたが、とりわけ自分たちもどこか同様に英国人から抑圧されていると感じていたアイルランドでは大歓迎を受けた。エクイアーノの旅は史上最初の政治関連本のプロモーションツアーであり、実にこれ以上ないくらい時宜を得たものであった。
奴隷制度推進派は痛手を被ったのは言うまでもない。最大の奴隷港湾都市では『リバプール・ジェネラルアドバータイザー』紙の編集人が、「わが国はのぼせ上がっており、まっさかさまに破滅へと向かっている」と嘆いた。かくして奴隷制推進勢力の反撃が始まる。かれらは「特にケンブリッジで」配布するために(大学町は当時も左寄りであった)奴隷制度を奨励する本を8000部買い占め、さらに「こざっぱりとした小さな家と、庭に大量の豚と鶏のいる」いかにも幸せそうな奴隷の家族の様子が載ったパンフレットをやはり8000部印刷した。ロンドンのミュージカル『慈愛に満ちた農園主』のスポンサーにもなった。このミュージカルは、アフリカで生き別れとなったふたりの黒人の恋人たちが西インド諸島に行き着き、それぞれ隣り合った農場で生活していたが、親切な農園主たちのはからいで、ふたたび一緒に暮らせるようになるという筋書きのもの。それでも奴隷経済に依存していた英国人たちはやはり事態を憂慮していた。リバプールではこのような戯れ詩が流行る。「もしも奴隷貿易がなくなっちまったら、俺らの暮らしもお終いよ/物乞いにならなきゃならんだろ、子供も妻も一緒にな/港の船も出なけりゃ、誇り高き帆もひらめきゃせぬ/町の道には草が生え、それを牛らが食うのやら」
奴隷制度推進派の戦略は、今日攻撃を受けた産業が自己弁護に用いるものと驚くほどよく似ていた。たとえば、国会で奴隷の取り扱いを規制しようという動きがあった際、農園主たちはこぞって字面だけはさも高邁な自前の行動規範を打ち出し、政府の干渉は一切不要と主張した。他のPR手段を考えたものたちもいて、ある奴隷制推進派の作家などは1789年にこう提唱している。「低俗な輩(やから)は名前や肩書に影響を受けるものだから、いっそ『奴隷』というのはやめにして、代わりに黒人たちを『農園主助手』と呼んではどうだろう。そうすれば奴隷売買に対してこれほど酷(ひど)い糾弾は聞かなくなるのではないか」、と。
6. 逸(そ)らされた運動
国会の奴隷制度推進派で最も目立った代表演説者[スポークスマン]クラレンス公は、英国王ジョージ三世の数多い放蕩息子たちの一人であった。この人物は、10代の頃英国王立海軍に所属して西インド諸島へ赴き、そこで農園主たちから盛んに酒肴の馳走に預かっていた。かれは結婚の申し込みと性病とを農園主の娘たちに撒き散らすと同時に、農園主特有の偏向した態度に自分も染まりきった。紅の地に白テン[アーミン]毛皮つきのローブをまとう同僚の貴族院議員たちの前で行った処女演説では、かれは自らを「黒人奴隷たちが置かれた状況の注意深い観察者」と称して、奴隷たちはよく面倒を見てもらっているし、「かなり幸福な状態」にあると述べた。また別の機会には、英国が奴隷貿易を廃止してしまえば、奴隷たちは他の国の者たちによって輸送されることになり「[英国の奴隷商人たちが示す]これほどの優しさと配慮をもって扱われなくなるだろう」とまで述べている。
言うまでもなく、国会こそ奴隷貿易に関する最終的な論戦が闘われた場所であった。クラークソンが、下院での代表演説者として押し出したのは、ヨークシャー選出の裕福な議員で、体格は小柄ながら誠実さと雄弁さによって広く尊敬を勝ち得ていた人物、ウィリアム・ウィルバーフォースだった。ところが実は、ウィルバーフォースとクラークソンとは、反奴隷制度論者という一点を除けば、政治上の立場がまったく正反対であった。クラークソンがこの時代の急進的な流れに進んで身を委ねたのに対して、ウィルバーフォースは民主的な意思、労働組合、賃金アップ、女性の政治参加といったものに畏怖の気持ちを抱いていた。それにもかかわらずこの二人の男たちはよき友人同士としてほぼ50年に渡り、親しく行動をともにしたのである。
とはいえ議会が動き出す前には、うんざりするほど長い聴聞を経なければならなかった。元船長であったジェームズ・ペリーのような目撃者の証言などを聞くと、ミドル・パッセージ[奴隷貿易で用いられた航路]上の奴隷たちがあたかも豪華客船ツアーの旅客のごとく思えてくるほどであった。いわく、「暑いのに湿度が高すぎて、発汗作用がまるで働かなくなってきますと、奴隷たちは甲板に上がって参ります。そこにはふたりばかり男が待機しておりまして、布でもってかれらの汗をぬぐい、すっかり乾かしてやります。さらにもう一人が少量のリキュールを与えてやります。それからパイプとタバコが与えられます。祖国の音楽を奏でる楽器で楽しみます。また、音楽や踊りに飽きれば、[さいころなどで]運だめしのゲームをします」
奴隷貿易に不利な証言を進んでしてくれる目撃者を集めるのは、今日軍関係や企業の内部告発者[ホイッスルブローワー]たちを見つけるのと同じくらい骨の折れることであった。船乗りや航海士が批判的な証言をしようものなら、二度と奴隷船での仕事は得られなかった。目撃者証言を求める渉猟の旅で馬上のクラークソンが走破した距離は、2か月間に1600マイル[約2600キロ]にも及ぶことがあった。クラークソンもさすがに愚痴をこぼすとおり、以下のようななりゆきも珍しくなかった。「話してくれた内容をペンとインクを取り出して書き留めようとすると、その人は当惑し、すっかりすくみ上がってしまう」。ところが、最も劇的な証言者が絶好のタイミングで奴隷貿易から戻ってきていた。クラークソンが日誌を付けるように説得しておいたブリストルの医師、ジェームズ・アーノルドであった。
奴隷制度推進派が聴聞を利用し巧妙に議事の進行を遅らせたため、今や聴聞は数年にも及び、法律戦略家としての経験と組織力を欠いたウィルバーフォースは第一線から脱落していた。奴隷制度推進派は、ウィルバーフォースが議会を動かして奴隷貿易廃止をめざす試みを数度に渡り阻んだ。しかし、ジョージヤード2番地での最初の画期的な集まりから約5年たつ1792年の春までには、奴隷貿易反対の民衆感情は押しとどめ難いほどの勢いをつけていた。クラークソンはこう書いている。「現在この国を席巻する熱狂について云々(うんぬん)できるのは、それを目の当たりにした者だけだろう。流れは非常に強くかつ速すぎて、その方向を操作することなどまず不可能だった」、と。すっかり消耗してはいたものの、クラークソンは馬で国中を回る組織づくりキャンペーンをちょうどひとつ終えたところであった。エクイアーノは、行く先々で友好的な聴衆に迎えられた。砂糖のボイコット運動はそのピークに達していた。ウィリアム・ワーズワース[英国の代表的ロマン派詩人(1770-1850)]は、その春の反奴隷制の熱狂的な盛り上がりたるや「国民全体がひとつの声で叫んでいる」のに等しかったと記す。
クラークソンと他の活動家たちは、国会議員たちに対して情け容赦ないほど激しいロビー活動を繰り広げた。奴隷制度反対の請願書が多数国会に押し寄せるさまはかつてないほどの事態を呈していた。エジンバラから送られてきた請願書を広げたところ[請願書は巻物の形をしていた]、その長さは下院の床の全長に達した。マンチェスターでは市の総人口の3分の1にあたる2万人の人々が署名した。小さな町から送られてきた請願書の中には、字の書ける住民のほとんどすべての署名が集められていたものもあった。合計519巻の請願書がイングランド、スコットランド、ウェールズ各地から届いた。
対して、奴隷貿易に賛成する請願書は4巻届いたのみ。
やがて聴聞が済むと、国会の討議が夜を徹して続けられた。下院の議事堂の様子を想像してみよう。シャンデリアと壁の燭台にろうそくの灯りがほの暗くともり、説教壇のような椅子には、上衣を着用し、鬘(かつら)を被った議長が腰掛けている。議員たちは議場を離れる時にかれに一礼し、議長壇の下には黒衣の書記官たちがいる。入り口付近にはかぎタバコ入れがあり、中央の卓には金銀の儀礼用の[英国下院議長用の]職杖が置かれ、それにろうそくの灯りがキラキラ照り映えている。乗馬用のブーツや拍車をつけた者の多い議員たちの座る議席が、薄暗がりの中に立ち並ぶ。議場の上の狭い傍聴席は傍聴者で溢れ、遅刻者は入場を断られていた。エクイアーノは定刻までに入場したが、クラークソンは入り口の番人にそっと気前よく10ギニーを手渡して、30人ほどの奴隷解放主義者たちを入れてもらった。
スコットランドの大票田を左右できる政治的影響力を持つ内務大臣ヘンリー・ダンダスが立ち上がって演説を始めた時、奴隷制の賛否についてかれの立場を知る者はだれもいなかった。まずダンダスは自分が奴隷制度の廃止に賛成だという立場を表明したので、上の傍聴人席にいた者たちの心はきっと躍ったに違いない。かれはさらに進んで、奴隷の解放に賛成だとも言明した。ただし、はるかな将来の話だが、とかれはすばやく付け加えた。それに大変な準備と教育も必要である、と。さらに奴隷制廃止推進論者たちが落胆したことには、ウィルバーフォースが提出していた奴隷貿易を廃止する動議に「徐々に」という語を挿入する修正案を導入した。こうした瞬間はどんな改革運動家も味わわされる。つまり相手方がその改革側のレトリックを盗用せざるを得なくなる瞬間だ。たとえば、工場方式での大規模農場が製品に「ナチュラル(自然の)」と書いたラベルを貼ったり、石油会社がみずから環境派を宣言したりするように、ダンダスは奴隷解放主義者[アボリショニスト]を自称しながら、実際の廃止は延期することを求めたのである。
当時まだ弱冠33歳であった長身痩躯(そうく)のウィリアム・ピット[小ピット(1759-1806)]は、午前4時になって最後に演説した。開口一番、「疲労のためにわたしが求めるほど深く議題に入り込めますかどうか」と断ったが、演説の記録を今日読むと、現代政治の文脈で用いられる「メディア受けしやすいレトリック」[この箇所原文にはsound-biteという語を含むが、直接訳出していない]が恥ずかしくなるほどすばらしいものである。ピットは原稿なしで一時間以上演説を続けた。かれはまず「漸進主義派」の者たちの「自分たちは奴隷解放に賛成である」という言葉を取り上げ、かれらの掲げるひとつひとつの論点が、むしろ即座に奴隷貿易をやめるためのよい論拠になる旨、逐一証明して見せた。それから、奴隷商人たちのおなじみの議論を打ち砕く。今日の武器輸出業者と同様、英国の船舶所有者たちはもし奴隷の運搬をやめたら、この事業は外国、とりわけ英国の最大のライバルであるフランスに持って行かれるぞと脅していた。しかし、フランスがその最大の植民地であるハイチで起こった大規模な奴隷蜂起――いわゆるハイチ革命――の火消しに躍起になっている最中、奴隷貿易を拡大すると考える者は誰もいなかった。さらに奴隷貿易そのものについて、ピットはこう尋ねた。「議長閣下に申し上げます。世界中の国々の同意が得られるのを、どの国もかくも忠実に待っていては、この巨悪を一掃することができますでしょうか」、と。
最後にピットはこの国の帝国としての傲慢をたくみに利用した、大上段の歴史的な比喩を披露する。英国そのものも、そして英国の法律も英国の成し遂げてきたことも、人類文明の極致である、とかれは言明した。しかし、だからといって、アフリカを野蛮で非文明的であると決めつけ、アフリカ大陸から人々を運び去っても奴隷商人たちはなんら害をなしていないと主張するのは、公正とは言い難い。なぜなら何世紀も遡(さかのぼ)れば、英国本国でも奴隷制度や人身御供が見られたからだ。「当時ローマ帝国の元老院議員が、英国の野蛮人たちを指差して、[今のわれわれと]同様の傲慢さで、『やつらは将来に渡って文明段階になど決して達しない連中だ』と言い放ったかもしれないのですぞ」、と。伝えられるところによれば、かれがこう述べ終わったまさにその時に、議長の椅子の背後にあった大きな窓から、明け方の曙光が議場に差し込んで来たという。
しかし、ピットの雄弁さだけでは足りなかった。漸進主義者による提案が可決され、さらに議論が重ねられた末に、この後4年たってようやく下院が、1796年を奴隷貿易終結の年と定めた。だが、はるかに重大な障害は英国貴族院であり、漸進的であろうとなかろうと、ここがあらゆる奴隷制廃止案を却下していた。奴隷解放主義者たちはひどく落胆した。それにもかかわらず、世界中のいかなる地域にも先駆けて、国家的規模の立法府が投票によって奴隷貿易を終結させる議決をしたということには大きな意味があった。
7. 「わたしの子供たちは自由になるでしょう」
翌年の国会会期にこの議題が再び浮上するより前、英国とフランスが交戦状態に入るや、戦争は二回の短い中断期間を除き、ついにワーテルロー[1815年6月18日にナポレオン一世が英国‐プロイセン連合軍に大敗した戦場]で終結を迎えるまで、実に22年にも渡って続いたのであった。戦(いくさ)は抑圧の波をもたらした。奴隷解放運動を含むあらゆる進歩的な動きが立ち往生を余儀なくされる。クラークソンの髪はすでに白くなっていたが、そのかれが全国を遊説して歩いて忠実な運動家たちを再結集させてようやく、1806年になって初めて奴隷解放主義者たちが部分的な奴隷貿易の禁止に愛国的な色合いを被(かぶ)せる方法を見出した。戦争中にもかかわらず、英国船籍の奴隷船が密かに、しかし巧妙に利益を上げつつ、奴隷をなんとフランスの植民地に供給していたということが判明したためである。国会はすぐさまこれを禁止したが、奴隷解放主義者たちはこの動きに乗じ、1807年に両院で奴隷貿易を禁止する決議をさせることができたのであった。
かれらは、このままいけば奴隷制度自体もまもなく終わらせられると確信していた。ところが、カリブ海諸島の農園主たちは、奴隷を死ぬまで働かせては、奴隷船が補給してくれる新たな奴隷を買って穴埋めできなくなったため、奴隷の労働条件を緩め、よい食べ物を食べさせるようになっていた。1820年代までに、奴隷の出生率は増加に転じた。英国では奴隷制反対運動が再燃し、こんどこそ奴隷の解放を目指した。クラークソンは60代に達していたが、それでも再び国中を回り、つごう1年以上の旅に出ると、数十年来の知己ばかりか、しばしばその子供たちを訪ねては、200以上もの地域で奴隷解放協会の創設に手を貸す。再度極めて保守的な国会を目標に定めたかれとかれの同志たちは、慎重を期して、ゆっくりと段階を踏んだ奴隷解放を唱えたのである。
ところが、今回は何かが違っていた。「女性の」奴隷制反対グループが、英国中で70以上も立ち上げられたのだ。この女性たちの中には、エリザベス・ヘイリックという名の情熱的なクェーカー教徒の言論家に影響されて、漸進的ではない方針、すなわち奴隷たちの即時解放を求める人が多かった。ある女性活動家はこう書いている。「殿方はこの最悪の犯罪を徐々に廃止することしか提案されませんが、それでは結局、最も残忍な桎梏(しっこく)の存在を曖昧にするだけです。けれどもわたしたち女は、このような重大犯罪に真っ向から立ち向かわずにはいられません」
1831年末、奴隷解放運動が再燃したとの知らせが大西洋を渡るや、それは英領西インド諸島最大の奴隷反乱の勃発を促した。ジャマイカ北西部一帯で2万人以上の奴隷が蜂起したのである。農園主たちは長い間好んで巨大なバルコニーのついた家を風の強い丘の上に建てていたが、今回炎を上げて燃えていると、それらの家々は灯台がわりになった。民兵たちが反乱側の手に落ちた農場に近づいていくと、一人の女性奴隷が砂糖工場に火を放ち、民兵に撃たれる前にこう叫んだという。「わたしはこれで死ぬでしょう。でもわたしの子供たちは自由になるのです」
軍隊がこの反乱を制圧するまでに、およそ200人の奴隷と14人の白人が亡くなっていた。絞首台や銃殺隊によって、さらに340人の奴隷が処刑された。しかしこの反乱のおかげで、英国の主流派[教会・王室・富豪たちの権力複合体]は奴隷制の存続にはあまりにもコストがかかりすぎるということを悟る。元ジャマイカの大農場経営者にして警察裁判所判事のウィリアム・テイラーは、国会のある委員会でこう証言した。奴隷の反乱は「また起こることでしょうし、もし今度起こればかれらを抑えることはできません。わたしはみなさんがなぜ奴隷たちに大人しくしていることなど望めるのかわかりません。かれらは英国の新聞を読んでいるのですよ」
史上最大規模の請願の嵐とデモが席捲(せっけん)した後で、ついに国会が折れた。1838年8月1日、大英帝国中のほぼ80万人の奴隷が自由の身となったのだ。その前夜、うだるような暑さの中で、ジャマイカのフォルマスにあるバプティスト教会では、壁に木の枝と花々、加えてクラークソンとウィルバーフォースの肖像を掲げた。ひとつの棺に「植民地の奴隷制度、1838年7月31日死去、享年276歳」という銘が刻まれ、鎖、鉄製の首枷(かせ)、そして鞭がびっしり詰め込まれた。戸外では墓穴が掘られ、大きく口を開けて棺を待っていた。午前零時を回ったところで、葬儀の歌を合唱しながら、教区民たちが、棺をその中へと下ろした。地上最大の帝国の奴隷制度がここに終わりを告げたのである。
51年前、ジョージヤード2番地のクェーカー教徒の書店兼印刷所に集った12人の男たちの中で、この時存命だったのはトマス・クラークソンだけであった。
結論: 世界を変える
刀剣、鬘(かつら)、馬車の時代に生まれたものでありながら、英国の奴隷解放運動はわたしたちに、ひとつの並外れた遺産を残してくれた。今日の市民活動家たちが日々用いている運動のためのさまざまな方策は、このとき編み出されたのだ。消費者による不買運動[ボイコット]、ニューズレター[活動通信]、政治ポスターにバッジ、地域集会と全国規模の運動の両立および連携、等々。しかしもっと大切なのは、運動のビジョンの大胆さである。今日の世界が直面する問題を見てみよう。地球規模の温暖化、富んだ国々と貧しい国々との巨大な格差、核兵器の情け容赦ない拡散、地球の土壌・大気・水の汚染、そして習慣化された戦争。現実家であれば、これらのどの問題を取り上げても、解決までにはきっと数世紀かかると言うだろうし、そう考えるのが分別というものに違いない。だが、最初に奴隷制度をやめようと提案した者たちにまったく同様なことを述べたのも、やはり大勢の頭の固い現実家たちだった。奴隷制度はそもそも、世界の大半の経済に何らかの形で織り込まれているものなのではないか。それは貨幣や文字より古い歴史を持つものなのでは、等々と――。そんな奴隷制度全体を終わらせようとする者はみな、確かに夢想家だった。しかし、最終的に現実主義者たちは誤っていた。マーガレット・ミード[(1901-78)米国の人類学者]は次のように述べている。「疑ってはいけない。思慮深い、献身的な市民たちのグループが、世界を変えられることを。実際、かつて世界を変えたものはそれしかなかったのだから」
(注1)ロンドンのプラークの一例。マルクスゆかりの地。
http://www.blueplaque.com/show_image.php?photo_id=44
(注2)ジョサイア・ウェッジウッドの工房に由来するバス・レリーフ。
http://www.pbs.org/wgbh/aia/part2/2h67b.html
■アダム・ホークシルドは、[この記事の原文が掲載された]『マザー・ジョーンズ』誌の創立編集者でもある著述家。かれによる過去五作中の最近著『レオポルド王の亡霊――アフリカ植民地における強欲、恐怖、そして英雄的行為』(King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror andHeroism in Colonial Africa)は全米書評家連盟賞で最終選考まで残った。今回の記事は、英国の奴隷解放運動に関するかれの近刊書[Bury the Chain]に基づいている。新著はホートン・ミフリン社より今秋刊行予定。
[原文] Against All Odds by Adam Hochschild, Mother Jones, 2004
Copyright C2004 Adam Hochschild [TUP翻訳配信許諾済み]
翻訳:和氣久明 協力:井上利男、川井孝子、藤澤みどり、星川淳/TUP