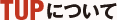今年4月に20年忌を迎えたルワンダ大虐殺が一つの契機となって、「保護する責任」という理念が打ち出されました。一国の政府に集団虐殺などの重大な人道危機を食い止める力や意思がないときは、国際社会が責任をもって(すなわち武力を行使して)阻止するという、「人道的武力介入」の理念です。しかしこの理念には、外国の介入に口実を与える危険性などが指摘されてきました。特に、前世紀に植民地支配のくびきから解放された南側諸国(先進国が多く集まる北半球に対して、グローバルサウスと呼ばれます)で深刻に懸念されています。以下は、「保護する責任」が初めて適用されたリビア爆撃に際して、グローバルサウスを代表する知識人の一人ウォルデン・ベローが、コソボ、アフガニスタン、イラクでの介入を振り返ってこの理念の問題を指摘し、人道介入がどのように行われるべきかを論じた記事です。3年近く前に発表された記事ですが、「人道的武力介入」を考えていく上で重要な点がまとめられています。(荒井雅子/TUP)
人道介入がはらむ危機
ウォルデン・ベロー
2011年8月9日
リビアとシリアでの出来事によって、武力による人道介入、すなわち「保護する責任」の問題が再び注目を集めている。
国民にとって疫病神である腐敗した独裁政権の打倒をめざす、武器を持たないデモ参加者に思いを馳せない者はないだろう。チュニジアとエジプトでは、市民が立ち上がって自分たちの手で独裁者を追放した。タハリール広場では、武装したムバラク政権支持者が人びとを攻撃し、銃撃さえしたが、軍が独裁者側につかないことを決め、大規模な弾圧は回避された。
その後は、それほど簡単にはいかなかった。リビアの暴君ムアンマル・アル=カッザーフィー(カダフィ)は、デモに参加した市民を厳しく弾圧し、その結果、米国と北大西洋条約機構(NATO)に、空爆と反政府勢力への武器提供による軍事介入の機会を提供することになった。また現在シリアで、反政府勢力が蜂起した諸都市に対してアサド独裁政権が大規模な弾圧を行っているため、介入を求める声が欧米諸国で高まっている。
市民を自国政府から守ることを目的とした軍事介入を国家主権という原則より優先することは、はたして正当なのだろうか。そして正当だとすれば、どのような状況ならそうした展開が正当化されるのか、介入はどのように実行されるべきなのか。
国家主権の制限
1648年にウェストファリア条約によってヨーロッパで最大最後の宗教戦争と言われる三十年戦争が終結して以来、国民国家主権の不可侵性という原則は、国際関係の基礎をなす原則となってきた。いわゆるウェストファリア体制の下では、国民国家は、自ら主権を有すると同時に、民主制であれ君主制であれ他国の主権を尊重することを期待される、国際関係の基本単位として登場した。しかし、国家主権という原則の優位性は、国家間の紛争の現実にぶつかった。こうして、国家主権原則の行使を保護すると同時に制限することを目的として、国際連合のような集団安全保障体制が登場した。
近年、国家主権という原則は、また別の角度、すなわち人権主義の拡大という点から制限されるようになっている。1990年代前半にルワンダや旧ユーゴスラビアで起きた悲劇的な出来事以来、ある国の中で集団虐殺のような出来事や大規模な人権侵害が起きたときに、外国の介入を正当化するため、国家主権の原則をさらに制限しようとする動きが出てきている。こうした取り組みから、「保護する責任」、「人道介入」という理念が生まれてきた。
この新しい理念は北側先進諸国では賛同を得ている一方、グローバルサウスでは論議を呼んでいる。グローバルサウスの国々は、国家主権という旗印のもと、比較的最近になって植民地占領からの独立を獲得した。さらにパレスチナのように、依然として外国による占領のくびきを振り払う途上にある国々もある。
コソボやアフガニスタン、イラク、リビアで見られたような近年の介入は、グローバルサウスの多くの人間から見ると、一連の行動が、たとえ介入を唱える側の善意から出たかもしれないにせよ、国家主権、国家領土保全、そして地域および世界の平和と安全保障の維持に有害な結果に終わりかねない危険性を示しているように見える。
先進国での一般的な見方とは異なり、一国の国家主権の尊重が絶対的なものだと主張する人間はグローバルサウスにはほとんどいないだろう。しかし筆者をはじめ多くの人間から見ると、介入が例外として許されるのは、集団虐殺の十分な証拠があり、また大国の論理が当初の人道的意図に取って代わらないようにする手立てが保証されている場合に限るべきだと思われる。
コソボと大国の論理
コソボのアルバニア系住民の保護を目的に行われた、1999年のNATOによるセルビア爆撃は、人道介入の典型的ケースとされてきた。しかし世界は、コソボでの軍事介入を手本とするわけにはいかない。
何よりも、この介入は国連の信頼性を著しく損った。安全保障理事会から介入の承認を取り付ける見込みがないことを知っていた米国は、戦争の法的体裁を整えるために北大西洋条約機構(NATO)を利用した。現実には95%が米軍によって行われた戦争で、NATOはその実態を取り繕う口実でしかなかったわけだ。
介入積極派の一部に人道的理由を目的としていた人びとがいたことは疑いないが、作戦は主として米政府の地政学的構想を推進するものだった。コソボ空爆後に長く続くことになったのは、バルカン諸国の安定した安全保障ネットワークの構築ではなく、NATOの拡大だった。結局のところ空爆はそのためのものだったのだから、これは驚くにはあたらない。というのも、ボスニア危機の初期およびコソボにおけるスロボダン・ミロシェビッチの動きは、アンドリュー・バセビッチによれば、「NATOの存在意義、ひいては米国がヨーロッパで主導権を主張することに疑問を投げかけるものだった」。
スロボダン・ミロシェビッチへの対応に失敗していれば、米国は、自身が主導するNATO拡大の勢いを維持できなかっただろう。クリントン政権にとって、NATO拡大は、東欧の安全保障の空白を埋め、ソ連崩壊後のヨーロッパにおける米国の主導権を制度化するものだった。米政府の考え方について、以下のような分析がある。
–NATO拡大は、中東欧で進行している国内体制の移行を確実にするための制度的枠組みを提供する。こうした諸国にとっては、NATO加盟の見通し自体が、国内改革を行う「インセンティブ(動機づけ)」となる。NATOへの将来的な編入は、これらの国の制度改革を確定的にするだろうと言われた。加盟すれば、こうした諸国の機関は広範囲にわたってNATO体制に順応することになる。たとえば、軍事的手続きの標準化、NATO軍との作戦相互協力体制への段階的移行、合同の計画および訓練などだ。新加盟国を、より広範囲の同盟組織に取り込み、その作戦に参加させることによって、NATOは、こうした諸国の政府が旧体制に逆戻りする可能性を減らし、自由化を強化する。あるNATO官僚はこう述べている。「われわれはこうした国々を、政治的にも軍事的にもNATOのカルチャーに取り込んでいる。したがって、こうした国々はわれわれと同じように考えるようになり、時が経つにつれて、われわれと同じように行動するようになる」
NATO拡大政策の主要な一側面は、西欧の米国への軍事的依存の継続を確実にすることにあった。こうして米政府は、ヨーロッパ諸国政府がバルカン半島でヨーロッパ独自のイニシアティブをとることに失敗したことをすかさず利用し、NATOによるセルビア空爆という手段によって、ヨーロッパの安全保障が米国の保証なしには不可能であることを証明できた。
その上、空爆は、終わらせると標榜していた事態をすぐさま誘発することになった。すなわち、人権侵害と国際条約違反を深刻化させたのだ。爆撃は、コソボのセルビア人によるアルバニア系コソボ人の殺害と強制移送に拍車をかける誘因となり、送電網や橋、上下水道施設を標的にすることによってセルビアの人びとに「間接的に大きな被害」を与えた――これは1949年のジュネーブ条約への1977年の第二追加議定書第14条に違反する行為である。同条文は、「文民たる住民の生存に不可欠な物」に対する攻撃を禁じている。
そして最後に、コソボは、以後、国家主権の原則が侵害される強力な前例となった。自由主義のクリントン政権は、人道的懸念を持ち出して「優先」を主張することによって、国家主権を脇に追いやることを正当化したが、その行き当たりばったりのやり方は、別の党、すなわち共和党の人間がアフガニスタンとイラクに関して倫理的・法的武装を固める際に、その一部として使われることになった。右派思想家フィリップ・ボビットが指摘したように、クリントン政権のコソボでの行動は、非民主的政権の主権を制限する「前例」となったのであり、その主権には、「自らの選択にしたがって、どのような武器も求めることができるという、一国の政権に本質的な権利も含まれる」
アフガニスタン:状況を悪化させる
2001年にアフガニスタン侵攻が行われたとき、先進諸国は、タリバン政府を追放する米国の行動にほとんど抵抗を示さなかった。米政府は、9/11で生まれた米国に対する同情とアル=カーイダをかくまったタリバン政府のもつイメージにつけ込んで、タリバンとの交渉を選択肢から排除した。米国は、自衛目的に限って報復攻撃を例外的に認める国連憲章第51条を援用し、ヨーロッパ諸国からほとんど抗議を受けることなく、アフガニスタンに侵攻した。しかしブッシュ政権が自らの立場を固めるために利用したのは、米国に対するアル=カーイダの脅威を取り除くという理由付けだけではなかった。ブッシュ政権は、米国のアフガニスタン侵攻を、抑圧的なタリバン政府を転覆するために必要な人道介入の行為としても描き出した。コソボという前例によって正当化された行為だ。人道的な理由付けが持ち出されたため、カナダ、ドイツ、オランダなどのNATO加盟国も、その後、武装部隊を派遣した。
コソボ空爆と同様、アフガニスタン戦争もすぐに、人道介入の陥る落とし穴を露呈した。コソボと同様、大国の論理に乗っ取られたのだ。ビン・ラーディンの捜索は、アジア南西部に米軍の駐留を確立・強化するという至上命令に取って代わられた。こうした米軍の駐留は、石油の豊富な中東とエネルギー資源の豊富な中央アジアの戦略的支配の両方を可能にする。また、当時の米国防長官ドナルド・ラムズフェルドは、ある分析によれば、「少数の地上部隊に航空戦力を組み合わせることで、戦局を左右する戦闘に勝利することができるという自らの理論を証明する実験室」として、アフガニスタンに飛びついた。アフガニスタン侵攻の主な機能は、介入には部隊の大規模な投入が必要だとするパウエル・ドクトリンの見解が時代遅れであることを証明することだったわけだ。ブッシュ政権は後に、イラク侵攻の戦略的目的を支持するよう懐疑派を説得するために、これを利用した。
アフガニスタンでの作戦はまた、食い止めるはずだったことをすぐに自ら行うことになった。民間人を恐怖に陥れたのだ。米軍による爆撃は多くの場合、軍事標的と民間標的を区別することができなかった。タリバンは、アフガニスタンの多くの地域で民衆からかなりの支持を集めていたことを思い出せば、これは驚くにはあたらない。その結果、大量の民間人死傷者を出した。マーク・ヘロルドによる推計では、2001年10月7日から2002年7月31日の間の民間人死者として、3125人から3620人という数字を出している。国連アフガニスタン派遣団によると、2006年から2010年の間に紛争で9579人の民間人が殺害された。
作戦はまた、政治的、人道的状況を、多くの点から見て、タリバン政権下より悪化させることになった。政府の基本的な機能の一つは、最低限の治安と安全を提供することにある。タリバンは、時代に逆行する数々の悪習を行った一方で、アフガニスタンに30年以上存在しなかった、安定した政治体制をもたらした。これとは対照的に、あとを継いだ外国占領政権は、この試練にものの見事に失敗した。戦略国際研究センターの報告書によれば、「2001年12月の復興開始以来、特に2003年の夏から秋にかけて、治安は実際には悪化した」。一般人にとって基本的な身の安全が保証されないため、国の三分の一で国連スタッフの立ち入りが禁止され、NGOのほとんどは、国のほとんどの地域からスタッフを引き揚げた。米政府の据えたハーミド・カルザイー政権は、カーブルをはじめとする二、三都市以外では権威が乏しく、当時の国連事務総長コフィ・アナンは、「国全体で、住民の基本的ニーズに応えられるよう、機能する国家組織がなければ、新政府の権威と正統性は短命に終わるだろう」と述べることになった。
さらに悪いことに、アフガニスタンは麻薬国家となった。タリバンは、けしの栽培を大幅に減らすことができていた。2001年にタリバンが追放されて以来、けし栽培は40倍に増え、新たにけし栽培に充てられるようになった土地は20倍に及んだ。アフガニスタンの最上級官僚・議員の多くがヘロイン取引にかかわっている。もっとも有名なのは、カルザイ大統領の弟で、カンダハール県議会議長だったが、一カ月前に暗殺されたアフメド・ワリー・カルザイーだ。
現在の生活は、タリバン支配と比べて改善していないと言うアフガニスタン人は大勢いるだろう。少なくともタリバンは一つのもの、すなわち基本的な物理的安全を提供していたからだ。こういう議論は、先進国で治安のよい郊外や「ゲーテッド・コミュニティ」[防犯のため人や車の流入を厳しく制限している住宅地]に住む中上流階層にはぴんとこないかもしれない。しかし、どこでも貧しい人びとと話してみれば、自分たちの住むスラム地域社会から犯罪者や麻薬密売人や悪徳警官が一掃されることを大いに評価するだろう。
イラク:歪められた人道介入
米国によるイラク侵攻の主な理由付けは、フセインが大量破壊兵器を保有しているとされたことだったが、それを補強する重要なものの一つとして、人道的理由による政権転覆があった。大量破壊兵器が存在しないことがわかったとき、ブッシュ政権は、米国による侵攻はもともと人道的根拠によるものだったのだと後付けで正当化した。抑圧的な独裁政権を打倒して民主制を打ち立てるためだったというわけだ。
あとはご存じのとおりだ。イラクは今日では、石油の豊富な中東への米国の地政学的支配の拠点と化している。イラクは米国の軍事力によって支えられる国家となり、その石油資源と富は、何よりも欧米の利益に供されている。国家は著しく弱体化し、民族的・宗派的対立という遠心力に脅かされている。世俗的価値観と女性の地位は、原理主義によって損なわれている。犯罪とテロが横行し、物理的な危険が大きく増している。経済状況を見れば、一人あたりの生産量と生活水準は、侵攻前の水準をはるかに下回り、住民は慢性的な不安定状態の中で暮らしている。イラク人の55パーセントが安全な水を得られず、100万人が食糧安全保障を欠き、640万人が公的制度による食糧配給に頼っており、労働力の18パーセントが失業している。
人道介入は、かつて中東で最も進んだ国の一つをこうした悲惨な状態に陥れた。
先制的人道介入
リビアのケースはおそらく、人道介入という理念の乱用の最たるものの一つとして歴史に残っていくだろう。リビアの事態は当初は、腐敗した独裁政権を打倒するために人びとの蜂起が起きているように見え、エジプトにかなり似た形で展開していた。しかしリビアの独裁者と指揮下の軍、カダフィ支持層が抵抗し、軍事力を使って反撃して民間人の死傷者を出した。この過程で人権侵害を行ったことは疑いない。この時点で、事態は内戦へと悪化した。国外では、カダフィ政権からの離反者が、リビアのほとんどの上空に飛行禁止区域を設ける決議を国連安全保障理事会で通させることに成功した。ドイツ、中国、ロシアをはじめ安保理の決議を棄権した国々の憂慮をよそに、米国、イギリス、フランスはこの決議の採択に飛びついた。
リビアへの介入は、実際に起こった集団虐殺に基づくものではなく、それどころか集団虐殺が起こる恐れにさえ基づくものではなく、メディアであっという間に広がった、報復をちらつかせる言葉に基づいていた。3月11日の演説で、カダフィは支持者に対して、ベンガジで「家々をしらみつぶしに」調べ、「一切容赦しない」よう求めた。オバマ米大統領はこれに飛びつき、集団虐殺が起きようとしていると警告した。実際は、多くの解説者が指摘したように、カダフィの言葉は民間人ではなく反乱側の戦士に向けられたもので、同じ演説の中で、「武器を捨てる」者は赦すと約束していた。
実際、NATOが戦争を開始したあと、アムネスティ・インターナショナルとヒューマンライツ・ウォッチの人権活動家が行った調査によれば、集団虐殺や民間人を意図的に標的にした攻撃、デモ参加者や群集に対する軍用機の投入、集団レイプの証拠は見つからなかった。カダフィの部隊によって蛮行が行われなかったと言おうとしているのではない。しかし、介入の理由となる集団虐殺や人権の大規模かつ組織的な侵害の証拠はなかった。
リビアへの介入の間に、飛行禁止区域の設定という理由付けはすぐに政権転覆という目的に取って代わられた。NATO機は政府側の戦車や歩兵に対して攻撃的作戦を実行し、トリポリでカダフィが隠れていると疑われた場所を狙って爆撃し、カダフィの息子の一人をはじめ人びとを殺害した。NATOの支援する反乱側対カダフィの戦闘は消耗戦となり、民間人死傷者数、インフラの破壊、経済的苦境という点で、介入前より民間人にとっての状況を悪化させている。
嘆かわしい前歴
現在の人道介入には、三つの大きな欠陥がある。介入の人道的理由付けが、すぐに大国の論理に圧倒されること。こうした介入は悪い状況をさらに悪化させる場合が多いこと。そしてこうした介入は、以後、国家主権という原則の侵害に利用されうる、きわめて危険な前例となること。コソボ紛争へのNATOの介入は、アフガニスタン侵攻の正当化に一役買い、この二つの介入の正当化が、今度は、イラク侵攻とNATOによるリビア戦争の正当化に利用された。
ある国の政権が自国民を弾圧していれば、もちろん各国政府は、弾圧をやめるよう圧力をかけるべきだ。政権による自国民の弾圧を可能にしている軍事輸出を停止する行動は完全に正当であり、抑圧的政権を非難し孤立させる外交努力や経済制裁も正当だ。しかしこうした行動は、主権国家を侵略したり主権国家の政府や軍、政権支持者を爆撃したりして政権転覆を達成することとは、まったく一線を画す。
集団虐殺が政府によって行われているという例外的なケースでは、細心の注意を払って武力介入が行われなければならない。グローバルサウスの多くの政策担当者、分析者から見ると、以下のことが守られなくてはならない。
第一に、集団虐殺の確たる証拠がある。第二に、介入は、外交や軍事禁輸、経済制裁など集団虐殺を食い止める手立てを尽くしても奏功しなかった場合の最後の手段でなければならない。第三に、介入に法的正当性を与えるのは、欧米が支配的な安全保障理事会ではなく、国連総会でなければならない。第四に、覇権大国――特に米国とNATO――に属する軍部隊は、介入への参加を認められてはならない。第五に、派遣された軍は、集団虐殺を止めることだけを目的とすべきであり、状況が安定すれば撤退すべきであり、後継政府への資金提供や支援、「国家建設」への参加は控えなければならない。
こうした指針に照らした場合、過去40年間の人道介入の中で、正当に実行され、有効性があったと評価されるものはほとんどないだろう。おそらく2つだけではないだろうか。1978年、血に飢えたクメールルージュを権力の座から追うことを目的とした、ベトナムによる侵攻(ただし国連の承認を得ていない)と、1999年、インドネシアの支援を受けた民兵によるチモール人大虐殺と強制移送を終わらせた、国連主導の多国籍軍INTERFET。
人道介入という理念が辿ってきた悲劇的な道筋を簡潔に表すには、この古い言い回しがもっともふさわしいのではなかろうか。地獄への道には善意が敷き詰められている、と。
原文
The Crisis of Humanitarian Intervention
By Walden Bello, August 9, 2011 .