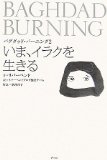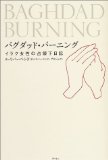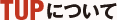TUP BULLETIN
投稿日 2011年11月28日
1967年に始まったヨルダンとガザ地区に対するイスラエルの占領は、44年目を迎えようとしています。
占領とは何か? 死傷者の多寡で紛争を測る従来の定義に従えば、占領下のパレスチナで起きていることはジェノサイド(大量殺戮)ではありません。しかし、パレスチナ人社会学者サリ・ハナフィは、こうした従来型の定義では、占領下パレスチナで進行中の事態の本質を表すことはできないとして、これを「スペシオサイド(Spaciocide; 空間的扼殺)」と名づけました。パレスチナ人が生きている空間それ自体を破壊することで、彼らが自らの土地で生きていくことを不可能にする、という意味です。パレスチナでは、人間が物理的暴力で大量に殺される代わりに、人間が人間らしく生きる可能性それ自体が、構造的暴力によって組織的かつ集団的に奪われているのです。
この「パレスチナの女性の声」シリーズは、そのような占領の現実を生きている19人の女性の肉声をまとめた報告書(2009年刊行)の翻訳です。作成したのはWCLAC(女性のための法律相談センター)という団体です。普遍的な人権擁護の一分野として、パレスチナにおける女性の権利擁護のために活動する上で、「女性の眼を通して語られる物語を聞くことなしには、パレスチナ社会が被る長期的被害が及ぶ範囲を評価することはできない」(事務局長 マハー・アブー・ダイィエ)という問題意識から聴き取り調査が行われ、文書にまとめた内容について証言者本人の確認を得た上で英訳され発表されました。
(英文報告書:http://www.wclac.org/english/publications/book.pdf )
パレスチナの現状について様々な立場からの報告を入手することができますが、そこで暮らしている女性の生の声を通して、特に女性であるために被っている被害を立証するものは大変貴重なものと言えます。また、「女性の物語は占領の残酷さ、差別および暴力の証拠であるばかりか、パレスチナ人女性の強さとしたたかさを証拠だてるもの」(同報告書序文より)でもあります。
報告書は大きく分けて「暴力」「移動の自由」「住居と家族の離散」「家屋の取り壊し」という構成になっています。
この報告書がパレスチナに生きる権利の回復のため、また世界のすべての地で人が人として生きる権利を確保するために活用されますように。
前書き:岡真理、向井真澄/TUP
翻訳:岡真理、キム・クンミ、寺尾光身、樋口淳子、藤澤みどり、向井真澄/TUP
凡例 [ ] :訳注 〔 〕:訳者による補い
投稿日 2011年10月28日
2001年9月11日の出来事を受け、10年前の10月8日、米軍とNATO軍はアフガニスタン空爆を開始します。以後、今日まで続く「対テロ戦争」の始まりでした。こうして、ソ連の撤退以後、世界の忘却の中に打ち棄てられてきたアフガニスタンは9・11という出来事によって世界の耳目の中心となりました。けれども、2003年にイラク戦争が起こると、世界の関心はイラクに移り、アフガニスタンは再び忘れ去られていきました。 2014年末までに外国軍が完全撤退することが発表されてはいるものの、10年たっても外国軍の駐留は続き、アフガニスタン国内は「平和・安定」とはほど遠い状況です。「対テロ戦争」の開始から10年、アフガニスタンは今、どうなっているのでしょうか。
アフガニスタン空爆さなかの2001年11月、ローラ・ブッシュ大統領夫人(当時)は、全米向けラジオ演説で、空爆はターリバーンに抑圧されるアフガン女性解放のためと語り、アフガニスタンの女性の人権を理由に攻撃を正当化しました。しかし、10年後の現在、アフガ ニスタンでは女性の焼身自殺があとを絶ちません。多くの女性たちにとって、自ら命を絶つことが、絶望的な現実から救われる唯一の道だからです。
今月、アフガニスタンの女性人権活動家、元国会議員のマラライ・ジョヤさんが「RAWAと連帯する会」の招聘で来日し、広島・沖縄・大阪・京都・東京・名古屋でアフガニスタンの現状について講演会をおこないます。 (詳細はこちらをご覧ください。http://rawajp.org/?p=244)
ジョヤさんは、2005年の議会選挙で、最年少で国会議員に選出されました。しかし、国会の内外で、内戦で国を破壊し、国民を虐殺した軍閥政治家を戦争犯罪者として糾弾し、その処罰を求め続けたために議員資格を停止されてしまいました。現在、国内で、暗殺の危険にさらされながら、ターリバーン、軍閥、外国軍の占領という三重の敵と闘いつつ、女性のための人権活動に挺身しています。
日本もまたアフガニスタンの惨状と決して無縁ではありません。アフガニスタンに自衛隊が上陸こそしていないものの、インド洋に自衛隊を派遣し、米軍に燃料補給し、アメリカの「対テロ戦争」を支えてきました。また民主党政権は2009年、ジョヤさんがその腐敗を告発してやまないカルザイ政権に対して「2010年から5年間にわたり50億ドルの民生支援」をすることを発表しました。
マラライ・ジョヤさんが来日されるこの貴重な機会に、TUPは、これまでのジョヤさんの主張ならびにアフガニスタンに関する記事を速報として発信し、忘却にふされていたアフガニスタンの<今>をお伝えするとともに、私たちの責任について考えたいと思います。
投稿日 2011年2月28日
◎メガリークの衝撃:ロンドンで聞くエジプトの声 米国の生々しい機密外交電文を逐次公開しているウィキリークスの資料ほどに、情報の価値と威力を見せつけた情報が近来あったでしょうか。ツイッターや SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)によって大量の生の情報が瞬時に広がるインターネットのこの新時代には、真に価値ある 情報は誰も予測できないような大きな力で世界に変動をもたらすものだということを、我々は今、リアルタイムで目撃しています。
独裁者や帝国主義国の正体の一端が顕れるやチュニジアの独裁者が逃亡し、エジプトをはじめ中東各地にも影響が波及していて予断を許しません。けれどもこの ように世界が躍動している時に、日本ではその状況がほんのわずかしか伝えられていません。大手メディアは申し合わせたかのように不気味な静けさを保ち、 ウィキリークス情報を黙殺同然にしているかのようです。
ロンドン在住のTUPメンバー藤澤みどりは家事の傍らBBCや、デイリーテレグラフ紙、アルジャジーラなどのもたらすニュースなどから豊富な情報を得て、世界の大変動の始まりに立ち会う実感をブログ http://newsfromsw19.seesaa.net/ に綴っています。
この文章がお目にとまるころには情勢はさらに大きく進展しているかも知れませんが、ロンドン生活から切り取った、ある時間帯のナマの声を紹介します。
(本文:藤澤みどり、前書:藤谷英男/TUP)
投稿日 2008年12月28日
2008年12月にはじまったイスラエルのガザへの空爆。そのガザから届くアブデルワーヘド教授のメールを速報として配信しました。このリストは、のちに『ガザ通信』として一冊の本になったその一連の速報と共に、ガザの状況を伝えた速報を加えています。

投稿日 2008年7月27日
2008 年3月13日、イラクとアフガニスタンでつづく戦争から帰還した米兵たちが、「冬の兵士」公聴会を開きました。会場では16日までの4日間、兵士たちがそれぞれの体験を証言として語りました。TUPでは、マスメディアでは報道されない戦場の真実をお届けできるよう、いくつかの証言を速報にしました。また、米国で出版された証言集の翻訳にメンバーがとりくみ、2009年8月に岩波書店より出版いたしました。

『冬の兵士』書評
[書評] 「マスメディアの寺院」を抜け出るために 竹山徹朗
[書評] 兵士達の絶望と希望を私達の胸に どすのメッキー
[書評] 『読書人』11月27日号掲載 本橋哲也
[書評]「日米同盟」堅持は無条件なのか―「冬の兵士」が突きつけるもの― 半澤健市
[記事] 「冬の兵士」証言集会へ 藤澤みどり
投稿日 2005年5月28日
オーストラリア人女性ドナ・マルハーンは、2003年の春にはイラクで「人間の盾」に参加した。04年春にはイラクで米軍包囲下のファッルージャに入り、その帰路地元レジスタンスによる拘束を経験し、つぶさにその報告をしてくれた。04年冬から05年春にかけてはイラク・パレスチナ「巡礼の旅」を伝えてきた。05年8月には、シンディ・シーハンのキャンプ・ケーシーに駆けつけ、アメリカからの報告は、ほとんど実況中継だった。05年12月にはオーストラリアがイラク戦争に最も貢献してきたパイン・ギャップ秘密基地に侵入し、「市民査察」を強行して逮捕されたが、08年2月に無罪判決を勝ち取った。09年末から10年初頭には、イスラエルによる包囲封鎖に苦しむパレスチナ・ガザ地区に入って援助を届け、現地から報告してきた。10年2月に、『普通の勇気――わが旅、人間の盾としてバグダードへ』を出版した。
投稿日 2004年4月28日
戦火の中のバグダッド、停電の合間をぬって書きつがれる24才の女性の日記「リバーベンド・ブログ」。イラクのふつうの人の暮らし、女性としての思い・・・といっても、家宅捜索、爆撃、爆発、誘拐、検問が日常、女性は外を出ることもできず、職はなくガソリンの行列と水汲みにあけくれる毎日。「イラクのアンネ」として世界中で読まれています。すぐ傍らに、リバーベンドの笑い、怒り、涙、ため息が感じられるようなこの日記、ぜひ読んでください。
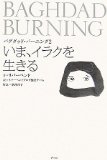
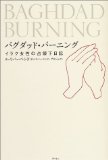
投稿日 2003年3月28日
コロラド州ボルダ―に住むパンタ笛吹さんの、「帝国」現地レポートです。