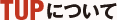FROM: hagitani ryo
DATE: 2003年6月16日(月) 午後11時19分
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
『ペンタゴン提供、戦争エンターテインメント』
――トム・エンゲルハート
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
前回の『1968-2003――ベトナム世代からイラク世代への伝言』とペ
アになった2回シリーズ。今回は、編集者トム・エンゲルハート自身の筆で、
大衆エンターテインメントに見るアメリカ国民の戦争イメージの通史を振り返
る。
騎兵隊の進軍ラッパから第2次世界大戦記まで、映画などの大衆娯楽は戦意高
揚プロパガンダの道具であるが、ベトナム戦争敗北によるアイデンティティー
喪失の悪夢を経て、現代では、戦争ニュースそのものがテレビゲーム型のエン
ターテインメントに仕立てあげられているかのようだ。
エンゲルハートは言う――「アメリカの勝利文化の再来はつかの間の夢に終わ
るはずだ」 そして、「そうあってこそ、たぶん、私たちは幸運の星に感謝すべ
きなのだ」 この言葉の中に、未来への希望を見るべきであろう。
(TUP 井上 利男)
[目次]—————————————————————
序文
ペンタゴン提供、戦争エンターテインメント
『サヨナラ、ジョン・ウエィン』 西部劇の時代は過去に…
『リビング・ルーム戦争』 ベトナムの傷を抱えて…
『戦争の略取』 今ふたたび、栄光の勝利を求め…
======================================================================
[序文]
さて、ここに『過去から未来への伝言』2回シリーズの第2回(すなわち最終
回)をお届けする。2日前の第1回では、クリス・アピーが昔と今の戦死者につ
いて考察した。続けてお届けするのは、以前に私が本に書いた主題、アメリカ
の勝利至上主義、そして戦争にまつわって私たちに吹き込まれる伝説について
の私の現在の思索である。(第一次湾岸戦争を素材にした)私の見解の詳細をお
望みなら、『勝利文化の終焉(The End of Victory Culture)』を一読なさるよ
うにお勧めする。(署名)トム
———————————————————————-
『ペンタゴン提供、戦争エンターテインメント』
――トム・エンゲルハート トム・ディスパッチ編集者
2003年5月25日
———————————————————————-
まるでサダム・フセイン、ムラー・オマール(タリバン指導者)、オサマ・ビン・ラ
ディンがどこへとも知れず消えてしまったのと同じように、戦争がいつのまに
か消え失せてしまったように感じないだろうか? アメリカ軍の前にイラク人
が倒れ、戦車隊が北を目指し、ミサイルが家屋を撃破し、その多くが自宅リビ
ングのスクリーンの中でリアルタイムで進行しているうちに、いかにもあっけ
なく戦勝に終わった。ジェシカ・リンチの英雄的救出があった。サダム像の引
き倒しがあった。サダムの宮殿のひとつで、大理石のテーブルの奥で、我らが
将軍たちがニヤッと笑っていた。アメリカはなんて強いんだろう。戦勝に続い
たのが、略奪と発砲騒ぎ。無能な一代目の占領行政官。ガソリン・スタンドの
行列。シーア派イスラム教徒は怒っている。大量破壊兵器は見つからない。従
軍記者たちは出国し、どこへ行ったのかも分からない。カメラは向きを変えた。
リアド、カサブランカ、エルサレムで爆弾だ。足元、アメリカ国内では、夫た
ちが妻たちを殺し、妻たちが赤ちゃんを殺している。
これまでも30年近く、国民に楽しめる戦争を提供するために、ペンタゴンは
メディアの動員に励んできた。年年歳歳、封切りに次ぐ封切りで、『最高に偉
大な世代』は国民に『グッド・ウオー』なるものを上映してみせてきた。ジ
ョージやドン、それにポールや私などが、かつて遠い昔の幼いころ、暗がりに
座って、アメリカの小国民として、勝利と凱旋に彩られたアメリカのイメージ
にドキドキしながら見つめたアメリカ流の良い戦争。奇妙だ。あのころの映画
では落ち着いて戦勝を楽しめた。どこかへ消え失せるなんて思えなかった。
『サヨナラ、ジョン・ウエィン』
1990年代初頭のある時、そのころはたぶん7才だったと思うが、息子をつ
れて、カウボーイとインディアン(それに騎兵隊)が登場する、1953年製作
の立体映画『フェザー河の襲撃』を観に行った。私にとっては懐古趣味に浸る
機会だった。あの時代のハイテクSFXである3-D映像が得意技を見せて、
物がスクリーンを飛び出して、こちらへ突進してきても、今では粗雑としか言
えない技術の立体効果で、はたして私を怯ませることができるだろうかと思っ
ていた。
1953年の昔、初めて3-D映画『ティー砦』を観た時は、1本目の火矢、
それもこともあろうに私のと同じ名前が焼き鏝で刻まれたやつがスクリーンか
ら飛び出してくると、私は座席の前に転げ落ちてしまった。さて、40年後、
蛇の毒(つまり唾液)が私の方に飛んでくると、私はやはりたじろいでしまうこ
とが分かった。
だが映画そのものは、1953年当時の基準で判断しても、『襲撃』はレトロ
だった。インディアンが極悪だったし、野蛮人に捕われた白人女性たち、お馴
染みの救出という筋立ても、アメリカ文化殿堂の大衆路線コーナーに店晒しに
なった一番古いやつだった。メアリー・ローランソンが1682年に出版した
彼女自身の虜囚体験記は、アメリカ史上初のベストセラーになった。彼女が大
ヒットに恵まれたのだから、3世紀近くの後の世でも、救出劇は有効であって
もおかしくないのではなかろうか?
実際、三文小説、薬売りの客寄せショー、大衆演劇、大西部ショー、それにも
ちろん、後には映画に支えられて、3世紀もの間、栄光に包まれた戦争物語が
延々と発展してきた。映画館上映室の暗がりの中、地平線に光る銃の映像の背
後に潜むアメリカの軍事力至上主義のお話が、私が子どもだった時から、ゾク
ゾクする感覚で虜にしてしまった。
私と同世代の子どもたちの父たちは、自らの戦争体験について――戦争に行っ
た、勝った、程度しか言わず――ジョン・ウェインやゲイリー・クーパーといっ
た無口なスクリーンの巨星たちと同じように寡黙だが、その重い口から戦争に
ついて学んだのも、この勝利至上主義の視点からである。そして、私たち以前
の幾世代ものアメリカの子どもたちと同じく、棒切れ、時には軍用品ショップ
の陸海軍放出品、自分たち自身の特殊効果を用意して、裏庭や町の公園に繰り
出し、戦争で敵を掃討するシーンを自分たちで演じたものである。これは学校
の教科書の知識ではなく、私たち自身が学んだリアルな歴史であり、全ての点
で私たちに意味があるものだった。生命力のある神話と同じく、満足しうる信
念の体系だった。 今になっては、認めるには時代遅れであるように思えても、
私の幼年期のころ、子どもたちの多くにとって、映画で観た、公園で遊んだ、
あるいは床の上で人形の兵隊を動かした戦争は、成長期のもっとも楽しいでき
ごとだったと認めることが大事なのだ。
それはさておき、10年昔のあの時に話を戻せば、映画館の暗がりに座ってい
て、私は、隣りの席で静かに座っている、私の息子のことをいささか忘れてし
まっていた。やがて彼は私の袖を引っ張り、声を抑えて話し掛けてきたが、そ
れでも劇場全体に響いてしまった。「お父さん。わかんなくなったよ。ぼく、
インディアンはいい人たちだと思ってた」
あの映画館観客席に座っていた時、第一次湾岸戦争直後であり、スターウオー
ズ、ランボー、プラトーンよりもずっと後、ダンス・ウィズ・ウルブズ、トラン
スフォーマーズ、ヒーマン(学術用人体解剖構造データベース)からも後、それ
にダンジョンドラゴンの初期バージョンと最初のビデオゲーム以降の時代にな
って、私の幼年期の頃の、もっとも不可欠であり、もっともアメリカ的だった
物語が過去のものになってしまったと悟った。それは、アメリカ兵たちの隊列
が前進する時、騎兵隊ラッパが鳴り渡り、あるいは海兵隊讃美歌が湧きあがり、
背中がゾクゾクする物語が進み、負けそうにもない敵が負け、我が方は勝ち、
敵が失点し、我が方は得点する――その理由を解明してくれる物語だった。
私の息子は床で忍者タートルズとスケレターズを動かして遊んでいたが、カウ
ボーイもいなければ、インディアンの酋長もいなかった。(南軍の)灰色軍服も、
(北軍の)紺色軍服もなかった。オキナワ上陸作戦の準備がととのった緑色プラ
スチックの第二次世界大戦セットもなければ、ノルマンディでナチスと戦うG
Iジョーもいなかった。ベトナム戦争後、アメリカ流物語の語り口はすっかり
廃れてしまった。私の息子にとって、『フェザー河の襲撃』を観ることは、私
が東京の夜のホテルの部屋でサムライ・メロドラマを観るのと同じだった。ア
クションの見せ場はたっぷりあるが、何が起こってるのか、ぜんぜん分からな
い。インディアンが悪者なのはどうしてなのと息子が訊ねることは、何あろう
――アメリカの勝利の伝統は地に落ちてしまったことを示している。サヨナラ、
ジョン・ウェイン。
さて、第2次イラク戦争後、私たちは新しいアメリカの勝利の瞬間の真っ只中
にいるが、これには奇妙な点があって、この度は、私は、映画館で不信感を示
した息子の気持ちと同じ気分である。我が国の大統領があの航空母艦に着艦し、
世界を観客に見立て、シャッター・チャンスとウイニング・ランを演出して以
来、あるいはジェシカ・リンチ映画…いや失礼、捕われの白人女性が野蛮人の
手から救出されるアメリカの昔話さながらのニュースがほぼリアルタイムで放
映されて以来、私は息子の10年前の言葉について考え込んでいる。戦時中の
何週間か、『従軍』テレビ・レポーターたちが、来る日も来る日も、夜毎の褪
せた色合いの緑の画面で、ほぼリアルタイムで送り続けてきた視点は、子ども
時代の私が観た映画の画面中央で、移住者たちが幌馬車で円陣を組み、ハイテ
ク兵器構えの姿勢で、狂信者たちの襲撃に備える、あの古典的なシーンと同じ
であると理解して以来、私は息子の言葉について考えている。
『リビング・ルーム戦争』
第二次世界大戦のころ、ニュース映画が戦場から映画館まで届くのに数週間か
かり、政府が管理し、検閲したハリウッド映画が公開されるまで1年あるいは
それ以上かかった。ベトナム戦争は(ニューヨーカー誌の記者マイケル・アーレ
ンのうまい表現に従えば)『リビング・ルーム戦争』と呼ばれたが、それでも
あの頃は、ニュース映像が撮影されてから放映されるまで少なくとも24時間
かかった。だが、その後、戦争とテレビの戦争シーンとの時間差は消えてしま
い、あるいは別の言い方をすれば、逆転してしまった。ペンタゴンの担当官た
ちはこの度のイラク戦争のための準備と人員・装備の配置に1年近くを費やし
たが、リビング・ルーム戦争をほぼリアルタイムで一斉に放映するための準備
と人員・装備の配置にも、同じような時間を費やされた。
政府の戦争宣伝と、政府肝いりの戦争映像製作には長い歴史があり、ペンタゴ
ンには――軍事顧問、部隊、高価な軍用装備を貸与する契約を映画スタジオと
結ぶなど――映画製作とメイキングに参画してきた長い歴史がある。だが、最
近の射撃企画と『射撃映像』企画の両者とも、何か別の意味があると私は信じ
ている。ペンタゴンは、アメリカ式の戦争とアメリカ流の戦争神話との融合を
試みていて、今や、戦争と『戦争』とを同時進行的に進めるのに余念がない。
ペンタゴンの役人たちは、世界支配と同様、永遠に残るイメージを創造しよう
としている。だが、我が国の新しい植民地戦争とそれを伝える物語は、賞味期
間が著しく短いようだ。戦争にしても、物語にしても、進行中は意気揚々と戦
勝気分にも浸れるが、その満足感たるや、さほど長くはもたない。また、昔の
戦争物語のような賞味期限も望めないだろう。戦争にも物語にも疑問が付きま
とう。まさしく、何というインスタントな勝利主義の時代に私たちは突入した
のだろうか?
もちろん、ペンタゴンは映画館の戦争を管理下に置くことを簡単には諦めない。
例えば、ディズニーの『パールハーバー』(2001年)のために、ペンタゴン
は装備と助言を提供し、台本を校閲し、しかも、映画のプレミア・ショーのた
めに、航空母艦にマンモス・スクリーンと観覧席を装備して動員した。だが、
ここには奇妙な点がある。彼自身が軍事オタクであるプロデューサーのジェ
リー・ブルックヘイマーでさえも、大して稼げなかった。期待された割には、
映画は国内的にも世界的にもヒットしなかった。
実際、一分も考えてみると、ベトナム以降の紛争を描いた戦争映画で成功した
のは、クリントン政権時代のソマリアでの無惨な軍事的冒険を描いた(同じく
ジェリー・ブルックヘイマー製作の)『ブラック・ホーク・ダウン』(2001年)
と、第一次湾岸戦争を辛辣に解釈した、デービッド・O・ラッセルの『スリー・
キングス』(1999年)の2本だけである。現代の戦争で観客をシネマコンプ
レクスに一貫して動員しているのはベトナムでの我が国の敗北であり、最近の
ベトナム物ヒット作は、おかしく聞こえることは分かっているが、スティーブ
ン・スピルバーグの『プライベート・ライアン』(1998年)であり、これは第
二次世界大戦に背景を借りたベトナム戦記である。(この映画では、ノルマン
ディー上陸直後に、単独の行方不明兵捜索のために、偵察小隊が独自行動任務
に就くが、このテーマは、第二次世界大戦ではありえなかったことであり、ベ
トナム以降のベトナム戦争映画には不可欠であることに、あなたはお気づきで
なかっただろうか?) これ以外の近頃の戦争映画は、程度の差はあれ、おしな
べて興行上の失敗作である。『ハートの戦争』(2002年)、『ウインド・
トーカーズ』(2002年)のような第二次世界大戦再録映画はがた落ち、メ
ル・ギブソンの英雄的なベトナム戦記、『ウイ・ワー・ソルジャーズ』(2002
年)は立ち消え、ブルース・ウィルスの特殊部隊物『太陽の涙』(2003年)は、
ストーリーの核心に白人女性救出という昔馴染みの売り物があるにもかかわら
ず、討死にであり、その他に何があるか、誰が知っているだろうか?
近頃は、結局、私たちが映画館の暗がりに潜り込むのは、勝利史観であれ何で
あれ、現実の歴史から逃れるためである。私たちは、何百万人の単位で、外部
宇宙、あるいは地下、ファンタジーの時代、コミックの神話的世界へ消え去る
のである。『戦闘』といえば、敵地ローハンで騎士たちと対決するサルマンの
ウルク・ハイであり、あるいはコミック世界のニューヨーク上空でグリーン・ゴ
ブリンに飛び掛かるスパイダーマンであり、あるいはマトリックスのどこかで
5層構造の時間の中、ジャッキー・チェン張りのカンフーで闘うネオであり、
あるいはコンピューター画像のコロシアムで切りあい、刻みあうグラディエー
ターたちの群なのだ。アクションは目が廻るほどたっぷりだが、どれ一つとし
て、私たちの現実世界と連結しているとは認められない。戦争は、輝かしいエ
ンターテインメントの素材としては、ベトナム戦争時代にアメリカ文化から一
掃され、何光年かなたのギャラクシーにおけるスターウォーズでようやく熱狂
のうちに復活したが、いまだに惑星地球にしっくりと定着したのではない。
エンターテインメントとしての戦争は、ベトナム戦争後の今では、神々の恵み
たるささやかな収穫を僅かな例外として、賞味期限が短くなったようだ。いみ
じくもブッシュ政権の登場により、戦争は、Xメン、テレビ番組企画サバイバ
ル・ゲームのサバイバーたち、スティーブン・キングとラシ・ピーターソン、昨
今のテロ攻撃、NBAファイナル戦、セインフェルド再放送がひしめき、競り
合う文化のフリー・マーケットに放り込まれた。綿密な事前計画があったにし
ても、行き当たりばったりで、ペンタゴンとメディアが大急ぎで継ぎ接ぎした
戦争は、文化的創造物としては奇妙にも調子はずれの作品である。なるほど、
戦争は数週間は私たちの目を惹きつけているが、程なく、お次の24時間オー
プンの出し物にお株を奪われてしまう有様である。はてさて…。でも考えてみ
ると、たった今でさえ、ごく最近の戦争について、もっとも輝かしい瞬間をど
れだけ憶えているだろうか? 明日、あなたをゾクゾクさせるのは何だろう
か?
『戦争の略取』
現在では、大衆の心を捉えて離さない戦争物語を案出するのは、生半可な芸当
ではなくなった。ペンタゴンは、これまでの30年間、計画を十分に練り、資
金もたっぷり注ぎ込んで、努力を傾けてきたが、それは先が見えないままの苦
しい道程のままである。
1982年と言えば、ベトナム戦争の傷がまだ癒えない時期であり、敗戦の要
因として、裏切りに等しい戦争報道も大きな理由の一つだったと確信していた
ペンタゴン当局者たちは、イギリス軍が隔絶した南大西洋でアルゼンチンを一
方的に打ち破り、同時に報道を抑え込んでいるのを注意深く見つめていた。
(アメリカのベトナム体験を注目していた)イギリス軍は、記者たちをおおむね
英海軍艦艇に閉じ込め、批判的なジャーナリストたちは置いてきぼりにして、
戦争ニュースの流れをほぼ完全に掌握していた。これにヒントを得て、我が国
の軍はより良い戦争を提供する準備を始めた。
レーガン政権が命令した、1983年のグレナダという小島への侵攻作戦以降
の我が国の数多くの戦争と軍事介入のひとつひとつが、軍産複合体の実地実験、
すなわち、より新型の、より強力な、より技術的に進歩した世代の兵器体系の
実戦試験であったと言われている。例を挙げれば、最近の我が国の戦争では、
実質的に核爆弾級の威力がある(『すべての爆弾の母』とやさしい名前で呼ば
れている)MOAB爆弾が、フロリダの実験場からペルシア湾岸地域へ急送さ
れたが、実戦使用には間に合わなかった。その初回実戦試験の機会は、お次の
アメリカ帝国拡大戦争まで待たなければならないだろう。しかし、戦争の度毎
に行われる、このような実地試験の実施は滅多にそうと気づかれることもない。
報道管制のためであり、より正確に言えば、報道とニュース映像としての戦争
が現場で製作されているからである。
イギリスを模範としたペンタゴンの最初の反応は、メディアに対して、すなわ
ち一般国民に対して、戦争を否認することだった。イギリスが報道陣をフォー
クランド諸島に寄せ付けなかったのと同様、グレナダ侵攻に際して、ペンタゴ
ンは先ず記者たちを沖合いに『留め置き』、数日間、事態の推移の取材、撮影、
報道を許さなかった。この処置は、ベトナムでの敗北の記憶をすべて消し去り、
アメリカ国民の心証の内にどこか心ときめく戦争のイメージを再構築する露骨
な企ての始まりに過ぎず、また、従軍するメディアに対する怒りと復讐心の要
素も含んでいた。戦争報道にある種の罰則を課したのである。パナマ侵攻に始
まり、アフガニスタンまで、戦争の度毎に洗練されてはきたが、この方針は、
内実として防御であり、聖書の戒律にも似て、否定詞を連ねた――例えば(ア
メリカ兵の戦死は一般国民の厭戦気分を招き、本国世論の支持率を下げかねな
いので)、『汝、テレビで遺体運搬袋を見せるなかれ』といった――禁止項目
の列挙で構成されている。遺体袋は別の品名で、気付かれもしないうちに、空
輸される。しばらくの間は、戦闘のどちらの陣営にも戦死者は存在しないこと
になった。
こうした報道管制手法は第一次湾岸戦争で極点に達し、ペンタゴン、メディア
共同製作としてスムーズに運んだ。報道陣は今度も一ヵ所に集められ、『作戦
行動』現場から遠ざけられ、本国の一般国民は、砂漠景観の荘厳な日没と青い
空に向かって発射されるロケットの現実離れした映像と、イラクの標的が破壊
される最高の見せ場を、ペンタゴンが編集し、選別し、提供した形でふんだん
に見せられることになった。おまけに、テレビでは――(「湾岸の対決」といっ
た)キャッチフレーズとテーマ・ミュージックが色を添え――前の戦争で活躍し
た退役将校がしゃしゃり出て、前に在籍していた部隊の作戦行動を解説し――
精巧にデザインされた動画地図が理解を助け――(実態としては、メディアに
とって見世物が何もなかったフォークランド戦争を起源とする流れの帰結なの
だが)スターウォーズ流儀の映像が流れ――このような演出がメディアの第二
の天性になってしまっている。さらに、ペンタゴンは、戦争をディズニー風の
光の芸術――バグダッド上空のテレビ向き花火スペクタクル映像――として、
リビング・ルームのプライムタイムに、放映することまでやっている。
だが、このような報道のど真ん中には矛盾があったと、あなたは言うかもしれ
ない――そして、これこそはいまだに疼くベトナム症候群の後遺症なのだ。そ
れで結局、『戦争』は、作戦行動は――何処にある? ペンタゴンとホワイト
ハウスの役人たち皆は、子どもの頃に照明の消えた映画館で観たワクワクする
英雄的な瞬間を、どのようにはっきりと憶えていられたのだろうか? 最高の
見せ場は別にしても、作品そのものは奇妙にも駄作だった。記者たちは相変わ
らず登場せず、アクション映像も不足していた。戦争はそこにあって、計画通
りに進行していたが、たいていは視野の外だった。
12年後、第二次イラク戦争が、第一次イラク戦争の続編としてではなく、改
良されたリメイクとして計画された。今回は、暴君がノックアウトされ、アメ
リカ国民は我が国の勝利で沸き立つことになっていて、その通りに筋が運んだ。
2回目ともなれば、ホワイトハウスとペンタゴンはギャンブラーたちの支配下
にあり、地球ゲーム盤の上でサイコロを振る用意も整って、メディアも控えて
いた。新規に採用された手法は、記者たちを軍隊に『抱え込む』ことであり、
開戦準備中の『前線基地』に固め、ブラッドリー歩兵戦闘車とエイブラムズ戦
車で編成された(奇妙にも、数え切れない映画で繰り返し見せられた、西を目
指す開拓者たちの幌馬車の長いキャラバンによく似た)戦闘車列の各部隊毎に、
記者たちを配置して送り出し、戦争を本国の私たちに中継したのである。これ
は、彼らがサダム・フセインのパンチのない軍隊に圧勝する自信を抱いていた
ことを、疑う余地なく示していた。自信たっぷりだったので、リアルタイムの
映像を絶え間なく放映する機会に賭けたのである。映画製作と戦争政策が絡み
合っていたのだろう。今回の作品のロケ地がイラクだったのだろう。映画監督
はペンタゴンだったのだろう。製作スタッフはカタールのドーハに設営したセ
ントコム米中央軍前線司令部に駐留したのだろうし、そこでは、25万ドルを
掛けて、報道ブリーフィング用の映画セットを築造していたし――私たち一般
国民は我が軍の威風堂々とした前進を眺めていられたのだろう。
それでも、ペンタゴンの思惑通りにいかなかったことも幾つかあった。イラク
国民が解放軍を歓迎しなかったし、短期間にしろ、南部で戦争が泥沼に嵌まり
こんだ。すべて現実だった。このようなインスタント映画製作のハイライトは、
たぶん、ジェシカ・リンチの救出劇であり、彼女の姿は病院に到着した米軍特
殊部隊が装備した暗視カメラに捉えられ、救出シーンの映像が撮影され、ドー
ハのセントム前線司令部にリアルタイムで転送され、そこで編集され、放映さ
れた。結果は、本国メディアの演出による、夢のような愛国主義の熱狂であり、
ジェシカTシャツ、その他関連商品、おまけに間違いなくすでに製作に入った
NBCの今週のテレビ映画までそろった波状キャンペーンである。 だがそれ
でも、ジェシカ・リンチのニュースは、バグダッドでの銅像引き倒しのニュー
ス同様、サダム・フセインの巨大な大量破壊兵器備蓄のニュース同様、夏には
ボロ切れ同然になってしまうだろう。すでに、BBCがジェシカ救出劇を検証
し、大きく異なった、疑いようもなく非英雄的な――銃創も切り傷もなく、虐
待もなく、救出を阻むイラク防衛隊もいない…云々の――バージョンを報告し
ている。
それはさておき、世代を超えて再版され(今でも購入できる)メアリー・ローラ
ンソン救出物語に引き比べて、ジェシカ・リンチのニュースが明日になれば色
褪せてしまうとすれば、カメラがいかにハイテクであっても、いかに劇的な舞
台を設定しても、急拵えの神話につきまとう問題の一例であるにすぎない。第
一次湾岸戦争で、ペンタゴンは新しい現象――すなわち、当時、CNNがネッ
トワークを駆使して活用し、視聴者を捉えた――24時間放映テレビに真っ向
から直面した。今や、24時間放映テレビは私たちの娯楽生活に完全に組み込
まれていて、『私たちの生活』そのものに等しくなりつつある。初めて対面す
る時には、ペンタゴンは勝利者のように見えるかもしれないが、見掛けはあて
にならないと私たちは見抜いている。
私が思うに、この政権を動かしているのは――驚くべきことかもしれないが―
―単にジョージ・H・W・ブッシュの一期限りだった政権の盛衰の記憶だけでは
ない。トッド・ギトリンの言う『集中豪雨型メディア』の真っ只中にある、私
たちの騒々しい文化宇宙では、幾多の戦争と幾多の政権を含め、遅かれ早かれ、
すべては諸行無常に流れ去る。バグダッド国立博物館と同様、私たちの世界で
は――トピック、映像、脚色が目玉を鷲づかみにし、日常に溢れるスクリーン
と音響システムで送り出されるニュース報道が、私たちの耳目を釘付けにし―
―生活が繰り返し略奪されている。私たちがイラクで目にしているように、略
奪の雰囲気の下では(ABCテレビのショー『百万長者になりたい人は?』を
観れば分かるが)――あるいは、再建の任務に当たる者たち自身が略奪者であ
る場合には――永続的なものは何も建設できない。現今の文化フリー・マーケ
ットは富裕な略奪者たちの天国であり、彼らには、戦争を題材にしても、神話
は創造できない。お次のイベントに素材を求めても、とうてい無理なのだ。
結局、メディアとはそんなものなのだ。『インディアン』は悪者ではなく、領
地全体を簡単に征服することも、自分好みに簡単に再編することもできないし、
地球上のいかなる土地でも支配することは、よくても暫定的であり、戦争はさ
らなる敵を作るし、私たちが野蛮人のラベルを貼る人たちが今にも立ち去るわ
けではないという認識が広がっていく世界では、勝利の感覚よりも、恐怖こそ
が、現代の支配的な情動なのだ。9月11日攻撃に遭遇して、恐怖が大統領と
その政府の一番目の反応であり、恐怖がアメリカ国民をイラク戦争支持に走ら
したのだ。安全が保証された映画館では、サメが飛び出し、恐竜が跳ねても、
異境の地であっても、恐怖は楽しみであるかもしれないが、伝統を築くことに
も、長く安定した精神状態をもたらすことにも役に立ちはしない。
タコの足のように自らを蝕むシステムとして、アメリカの勝利文化の再来はつ
かの間の夢に終わるはずだ。今から10年先までどころか、1年先に、アメリ
カのどこでもいいが、裏庭や街路で、子どもたちが、GIとイラク兵ごっこ、
あるいは対テロ特殊部隊とアフガン兵ごっこをして遊んでいるだろうか? Y
ESには、私は賭けない。そうあってこそ、たぶん、私たちは幸運の星に感謝
すべきなのだ。
———————————————————————-
【原文】Tomgram: Giving good war
Copyright C 2003 Tom Engelhardt エンゲルハートによりTUP配信許諾済み
http://www.nationinstitute.org/tomdispatch/index.mhtml?emx=x&pid=698
======================================================================
翻訳 井上 利男/TUPスタッフ