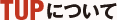![1961年2月11日、NYのベルギー領事館前で反ベルギー、ルムンバ支持のプラカードを掲げて抗議する人々 [AP Photo/Jacob Harris]](https://www.tup-bulletin.org/wp-content/uploads/2020/07/congo_women_202007_cedf1d8a4e784ddd984a85bbc40251e3_18-600x338.jpg) 1961年2月11日、NYのベルギー領事館前で抗議する人々 [AP Photo/Jacob Harris]
1961年2月11日、NYのベルギー領事館前で抗議する人々 [AP Photo/Jacob Harris]本稿は、アルジャジーラ紙オピニオン欄に掲載された“Remem
著者は、コンゴ独立から60年経った今、アフリカ解放のために闘った女たちのことはほとんど記憶されず、歴史の周縁に追いやられてしまっていると嘆く。そして、コンゴ独立に貢献したアンドレ・ブルアンの物語を通し、コンゴやアフリカの文脈を超え、今こそ、国家の暴力の被害者となった女たちの存在を認識し、公正を勝ちとる闘いの歴史で女たちが重要な役目を果たしてきたことに光を当てる必要があると説く。
コロナ禍が世界を覆うなか、“Black Lives Matter”の抗議運動もまた、国境を越えて共感をよんだ。国家の暴力に抗議するこの運動で掲げられた“Am I Next?” や “I Am A Man” といったメッセージは皮肉にも、人の尊厳へのより強いまなざしが向けられている今日だからこそ、より多くの人に実感をもって受け止められたのかもしれない。しかし実のところ、人種差別問題は政治と切り離すことができず、根深く、その歴史にいたっては非人道的極まりない。これはもちろん米国社会に限った問題ではなく、また人種だけの問題でもない。本稿でも、同じように警察の暴力の犠牲者でありながら、(現在の運動の発端となった事件の被害者である)黒人男性のジョージ・フロイドさんと黒人女性のブリオナ・テイラーさんの違いが指摘されているように、多くの社会において、弱い立場におかれた人びと、つまりは女や子どもは未だに虐げられ、その声は沈黙させられている。忘れられた物語に光を当てる本稿の試みを通し、歴史に埋もれてしまった声なき声に耳を傾ける必要があるという認識が広まり、人の尊厳につながるさまざまな問題がただされていくことを願っている。
(前書き・翻訳:和田直/TUP)
独立のために闘ったコンゴの女たちを忘れない
アフリカ解放のために生きて、死んだ女たちが、歴史の周縁に追いやられつづけることは、もはやあってはならない
コンゴ民主共和国の独立が宣言される数日前、コンゴの空港を搭乗機に向かって足早に、自信に満ちた足取りで歩く女性がいた。アンドレ・ブルアンは、植民地政策に反対する活動家として知られ、ベルギー政府によって国外追放を言いわたされていた。人びとの目は、ローマ行きの飛行機へと向かうブルアンに注がれていた。しかし、ほとんどの人が、その後ろに束ねあげられた艶やかな髪のなかに、コンゴ独立運動の指導者たちの署名の入った機密文書を隠していようなどとは知るよしもなかった。
ブルアンは、国外追放を利用して国際メディアへの記者会見を招集し、独立に対しベルギーの干渉があったという事実を暴露しようとしていた。ブルアンが搭乗しようとすると、植民地高官が行く手を遮って聞いた。「ブルアンさん、コンゴに戻って来るおつもりはありますか?」ブルアンも、負けじと皮肉を込めて言った。「あなたの方こそ、コンゴから出て行くおつもりはありますか?」
コンゴ独立へと導いた一連の動乱から60年が経ち、アンドレ・ブルアンを含め、アフリカ解放のために闘った女たちのことはほとんど忘れさられてしまっている。ブルアンは当時、コンゴのパトリス・ルムンバ、ガーナのクワメ・エンクルマ、ギニアのセク・トゥーレの助言者として3つの植民地列強と闘っていたというのに。
国家の暴力に抗議する運動が、アメリカ合州国、フランス、ブラジルなど各国で展開され、黒人女性活動家がその先頭に立っている今、自由をもとめて闘ったアフリカの女たちの物語は、公正を勝ちとる闘いの歴史で、女たちがいかに重要な役目を果たしてきたのかに光を当て、現代に教訓をしめしている。なかでもブルアンの活動は、女性解放が、脱植民地化の文脈から切り離せないのだということを教えてくれる。
ルムンバの影の女
アンドレ・ブルアンとは何者か? ロシア、あるいはアメリカのスパイという人もいれば、コンゴの首相となったルムンバの愛人という人もいる。1960年10月15日のボルチモア・アフロアメリカン紙には、「ルムンバの影の女」という見出しのついた記事で紹介された。確かなのは、自称パンアフリカ主義者として反帝国主義の行動に参加し、アフリカの民族を祖先とする人びとの解放のために重要な貢献を果たしたということだ。当時あるジャーナリストが、共産主義者なのかとブルアンに聞くと、「取るに足らない愚か者には好きなように呼ばせておけばいい。私はアフリカのナショナリストなのだから」と、こたえたそうだ。
1921年に中央アフリカ共和国に生まれたブルアンは、家族と引き離され、ブラザヴィルの「混血の」子どものための孤児院で大きくなった。ベルギーは、植民地下のこの非道な政策について謝罪をしているが、フランスは未だにしていない。
時が経ち、ブルアンには息子ルーンが生まれ、ルーンは2歳になってマラリアにかかった。しかし、マラリア治療薬はヨーロッパ人だけのためのものと決められており、フランス植民地総督府はブルアンが薬を手に入れることを認めなかった。ブルアンは、息子が死んでいくのを見ているほかなかったのだ。フランス領とベルギー領を行き来しながら過ごした人生のなかで、ブルアンは、それぞれの植民地大国の際だった残忍さをじかに体験し知ることになった。
こうして、フランス領での植民地支配の暴力を知り尽くし、そこから得られた知見で身をかためたブルアンは、ベルギー領で政治的な活動をおこなうようになった。独立運動へコンゴの女性たちを参加動員させるべく、草の根の取り組みを大規模に展開した。ブルアンはこう語っている。「アフリカ大陸の資源に関わる問題は、アフリカの女性の問題とは切り離すことができない」
ブルアンは、女には家事や針仕事といった訓練しか受けさせない植民地教育を批判し、新しい独立国家ではより総合的な教育が実施されるべきだと訴えた。1960年までには、ルムンバの側近3名のうちのひとりとなり、ルムンバがコンゴの首相に就任すると密接に協力した。このため、メディアには「チーム・ルムンバ=ブルアン」と呼ばれた。
国際的な最前線でも、ブルアンは、コンゴの脱植民地化を妨害しているとしてベルギーを非難した。ローマで記者会見を開き、この事実を明るみに出すと命を狙われ、ギニアに逃れることを余儀なくされた。ベルギーにコンゴの土地から部隊を撤退させるよう圧力をかける支援を、ルムンバがアメリカに要請したのも、ブルアンの提案だった。この目的は、実はアメリカはベルギー帝国と同盟関係にあることをアメリカ政府が明かさざるをえないようにすることだったと、ブルアンは自伝で語っている。アメリカが誠実な同盟国とは決して思っていなかったのだ。
ルムンバやその側近たちが暗殺され、ブルアンにも死刑が宣告された。そこで再び、ブルアンは今度はパリに逃れ、1986年に亡くなるまでの間、亡命者として暮らした。しかし、家族の女たちはブルアンほど運がよくはなかった。娘のイヴ・ブルアンは、母方の祖母とともに拘束された。彼女の母がマラリアを患い亡くなる息子をただ眺めていることしかできなかったように、兵士に殴られて死ぬ祖母を見ているしかなかったと、イヴ・ブルアンは語っている。
ブルアンの物語は、世界にひとつしかない。しかし、見方を変えればブルアンは、脱植民地化のために尽力したにも関わらず、見過ごされてきた多くの女たちのひとりにすぎない。ブルアンは、1960年4月8日の「アフリカ連帯のための女性運動」の結成にも携わった。最初の集会には6,000人のコンゴの女性が参加し、5月末には、登録者は4万5,000人にまでふくれあがった。政治的な影響力が増すにつれ、植民地総督府は「アフリカ連帯のための女性運動」に集会を禁じたが、コンゴの政治家たちは人気取りのためにこぞってこの運動を利用しようとした。組織は、女性への参政権付与に焦点を当て、女性の健康や識字、そして新生ポスト植民地国家の市民としての認知に向けた展望を描いた。また、各地に支部をつくり、地方の女性も運動でリーダーシップを発揮するよう促した。
後世への教訓
ブルアンはある意味、まさにルムンバの影の女だったといえる。コンゴ独立の「偉大な男たち」の遺産の影に、ブルアンが遺したものは隠れたままだからだ。
ブルアンがほとんど記憶されていないのは、ルムンバの指導部の影の操縦者だったからではなく、アフリカ解放のために生きて死んだ他の多くの女たちと同様に、歴史の周縁に追いやられているからだ。「アフリカ連帯のための女性運動」の活動もまた、コンゴ独立への長く痛ましい道のりの歴史を語る文脈では、比較的知られざるままなのだ。
60年が経過した今日、ジョージ・フロイドを殺害した犯人らが世界的な抗議によってすぐに捕まったのに対し、ブリオナ・テイラー*の犯人らは捕まっていない。コンゴ共和国の女たちの脱植民地化の闘いは、国家の暴力の被害者となった女たちの存在を認識し、自由のための彼女たちの貢献を記憶しなければならないということを思い出させてくれるのだ。
*(訳者注)ケンタッキー州ルイビルの救命士ブリオナ・テイラー(26歳)は、2020年3月、誤った薬物捜査のため自宅に強制侵入した警官によって射殺された。警官らはひとりも現在のところ何の処罰も受けていない。
原文: “Remembering the Congolese women who fought for independence” by Annette Joseph-Gabriel, Al-Jazeera, Opinion/Democratic Republic of the Congo, 30 June 2020
URI: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/remembering-congolese-women-fought-independence-200630091359924.html