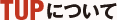◎緊縮財政の負の遺産、正の影響
英国はEU離脱(ブレグジット)に揺さぶられている。
『候補者ジェレミー・コービン ー「反貧困」から首相への道ー』
アレックス・ナンズ著
藤澤みどり、荒井雅子、坂野正明 共訳
岩波書店 2019年4月4日発行
チーム・コービンはイギリスを変える
メイの解散戦略とコービンの対抗策
その朝ラジオのスイッチを入れると、興奮したジャーナリストの声が飛び出した。2017年4月18日のことだ。午前11時15分に首相官邸前でテリーザ・メイが重大発表をするという。その約3週間前に、英国はEU離脱(ブレグジット)手続きを開始するためのリスボン条約第50条[EUの基本条約で加盟国の離脱を定めた条項]の発動をしており、まもなく始まるEUとの離脱交渉を前に与党の足腰を強くしようと、期日前解散総選挙に打って出るのではないかとジャーナリストは言った。
案の定、メイ首相は6月8日に総選挙に実施すると発表した。5月初旬に統一地方選があるため、二つの運動期間を合計すると選挙戦は7週間の長丁場となる。2011年に成立した議会任期固定法によると、期日前選挙実施には議会の3分の2の賛成が必要だが、メイ首相が唱導する強硬なブレグジットを緩和するためには与党の過半数を削がなければならず、野党が選挙を拒む理由はなかった。しかしこの頃、労働党の支持率は低迷しており、大敗してコービン党首が辞任を余儀なくされることを恐れた支持者の中には、労働党は解散総選挙を止めるべきだと主張する者もいた。
メイ首相は総選挙を求める理由として、野党が議会で邪魔だてばかりするのでブレグジット交渉の障害になるとし、各党をいちいち名指しして理由を述べた。EU国民投票を労働党は残留支持で運動したが、離脱の結果を尊重し、50条発動に賛成していたし、そもそも議会は政府の方向性を検証したり修正したりするための機関で、それがなければ独裁だ。さらに、この時までコービン党首は、効果的な「公式野党」運営ができていない、野党としての存在意義がないとメディアからひっきりなしに攻撃されていた。そんなわけで、メイ首相の言い分はまるで筋が通らなかったが、タブロイドの見出しには適切だったのだろう。
EU国民投票以降、テレビでもラジオでもソーシャルメディアでも議会でさえも、英国人の議論の質が著しく落ちた気がする。論理的な説得が通じない場面がしばしばあり、一方で、同じ言葉遣いで議論できない階級を蔑むような言動もよく見られる。普段は公平で公正な人々が、ブレグジットの話には別のルールを適用しているようだ。
総選挙への賛同声明でコービンは、キャメロン政権とメイ政権の7年間に及ぶ緊縮財政で、ぼろぼろになった国民保健サービス(NHS)ほか社会保障を建て直すために議席増を狙うと抱負を述べたが、奇妙なことに、この選挙のメインテーマであるブレグジットにはふれなかった。
ブレグジットに関して、労働党は難しい舵取りを強いられていたのだ。労働党支持者の3分の2は残留に投票しており、同時に、同党現職議員の約6割が離脱多数選挙区の議員だった。メイ首相がブレグジットを主軸に選挙戦を展開しようとする理由もそこにあり、労働党は、ブレグジットに賛同すれば6割の支持者を、反対すれば6割の議席を失う危険性があった。
コービン労働党は奇策に転じた。ブレグジットについてほとんど語らないことで議論を無力化したのだ。それを可能にしたのが、社会のあらゆる階層の人々に訴える社会主義者のマニフェストで、ブレグジットは約150ページある政策群の一項目に埋もれた。
コービン・プロジェクト—-運動の政治
この後に展開された選挙戦は、英国選挙史上まれなもので、労働党は選挙前世論調査での保守党との支持率差最大25%ポイントを、投票日には2%ポイントにまで縮め、結果、30議席増となる結果を獲得した。大幅議席増を狙ったメイ首相のギャンブルは、13議席減で過半数割れという予期せぬ結果に終わった。英国のエスタブリッシュメントにとっては、国民投票での離脱勝利という望まぬ結果の修正になるはずだった総選挙が、またしても予測を裏切る結果になった。
労働党は大学再無料化や最低生活賃金10ポンドなど若年層向けの公約を掲げて選挙登録を奨励したほか、高齢者や子育て世代にも配慮したポピュリスト型公約で、社会全体の「連帯」を呼びかけ、政治参加を活性化した。負担も利益も全体で分け合う社会ビジョンを示した労働党のマニフェストには党員、労働組合、シンクタンク等から吸い上げたアイディアが凝縮されており、解散総選挙で急ごしらえしたとは思えないほど良くできている。
7週間の選挙戦でコービン党首は60選挙区計90回の選挙集会を実施、時には1万人にも及ぶ大群衆を引き付け、集会のあった選挙区は周辺選挙区も含め全て得票率が上がった。
選挙後、あちこちで「コービンは英国政治のルールをどう変えたか」が問われた。二大政党制にしばしば見られる浮動票狙いの中道寄りを拒み、代わりに埋蔵票を発掘した点が注目されたが、これは2年前の党首選時の戦略の流用だ。
コービンと他のリーダーとの根本的な違いは、「コービンは一人ではない」ことだ。コービンの政治は関係する人の間でしばしば「コービン・プロジェクト」と称されるように、現場の声を集約することに徹した運動の政治で、関わる人数の多さが特徴だ。
その中心にあって、コービンは、あいかわらず控えめなおじさんであり、自分はたまたま頼まれてこの役割を果たしているだけだと述べる。質疑応答では当意即妙なのに、原稿のある演説が下手で、頑として上達しまいと決心しているかのようだ。そして、他のだれとも著しく違っているのは、良い社会を作りたいという願いはあっても、党首になろうという野心がなかったこと。その物語はこのように始まった。
社会主義者の党首誕生まで
2015年5月15日付けの『ガーディアン』紙に、つい1週間前の総選挙で議員になったばかりの労働党新人議員のグループが、「予算削減のアジェンダに異議を申し立てるとともに、大企業との対峙を厭わず、緊縮政策に代わるオルタナティブを提示する新たな党首」を求める書簡を公開した。過去5年の緊縮財政でここまで急激に悪化するかと驚くほど貧困が増え、格差が広がっていた。選挙戦敗北の責任を取ってエド・ミリバンドが党首を辞し、党首選の準備が始まっていたが、名乗りを上げていたのは閣僚経験のある、すなわち「緊縮やむなし」アジェンダから離れられない議員ばかりだった。「反緊縮候補を求む」とはっきり申し立てるこの新人議員たちそのものが、その時の労働党では異端的存在だった。トニー・ブレア一派がニューレイバー時代に築いた極端な中央集権統治体制で落下傘候補が増え、左派は立候補さえしにくい仕組みになっていたからだ。エド・ミリバンドはまぎれもなく労働党エリートの一人だったが、党首に就くと目されていたのは右寄りの兄デイヴィッドの方で、その兄を労組票で制す形で党首になったエドは党内基盤が弱く、新人議員候補に左翼が混じる余地が生じた結果だった。
この公開書簡に動かされた一人の党員が、参加していた労働党寄りのフェイスブックのページで「この議員たちに連帯して自分たちも書簡を公開したらどうか」と提案したところ、すぐに別の党員から反応があり、「労働党党首選挙に反緊縮の候補を求む」署名集めが、5月20日、オンライン署名NPOの『38度』で開始された。ちなみに、38度とは、軟弱な左翼を揶揄する表現「スノーフレーク(雪片)」が集まって雪崩になる角度のことだ。この署名が5000筆に達したころ、これに応える候補を供給すべき労働党最左派の社会主義者運動グループは、候補者をまだ見つけられずにいた。
およそリーダーのタイプではない万年ヒラ議員のコービンが立候補することになったのは、他に名乗り出る者がいなかったからで、なぜ義務を感じたかと言えば、党員が緊縮財政に異議を唱える候補を望んだからだ。候補者を選定するミーティングでコービンは「私が立とうか」と申し出た。彼自身、規定数の議員推薦を集めることなどできっこないと思っていたので、自分の役割は議員推薦締切までの12日間、討論集会やテレビ討論などに参加して反緊縮の議論に場所を作ることだと考えていた。この議会の会期中に下院議員の定数削減が予定されており、コービンの選挙区は周囲の選挙区と統合される見込みだったので、次の選挙では立候補しないつもりだったと後に述べている。
しかし反緊縮の候補者が存在することがわかると、コービンの思惑はどこへやら、今度は推薦議員を求めるオンライン運動がおき、議論の幅を広げるためとの口説き文句によって票を貸す議員が現れた。運動の甲斐もあって推薦議員が規定数集まり、コービンが公式候補者になると、膨大な数のボランティアが選挙運動に参加、政策作りさえもクラウドソーシング(公募で意見収集)する等、徹底的にボトムアップの運動を展開した。コービン・プロジェクトは、それまでばらばらに闘って来た、あらゆる左派の運動を引きつけた。コービンがしばしば言った「緊縮は必要からではなく政治的な選択である」は、緊縮による福祉削減を避け難い痛みとして諦めていた人々の目を開いた。
2015年9月12日、英国政界に激震が走った。二大政党の一翼を担う公式野党労働党の党首に、まぎれもない社会主義者が選ばれたのだ。4人が出馬した党首選の第1回投票で59.5%を獲得する圧勝ぶりだった。こうして、不承不承の党首が誕生した。
コービン現象は、治療を要する政治的病理(緊縮財政)の早期の発現だったのだが、労働党左派の枠を超えた政界のどこでも、メディアでも、あたかも一過性の不可思議現象としてしかとらえられなかった。コービンは新規加入者を引き寄せ、労働党は党員50万人の大政党になっていたのに、なぜコービンが党首に選ばれたかを正しく理解しようとせず、珍しいものを見るように観察し、揶揄するだけだった。そして、これが前震に過ぎなかったことが翌年明らかになった。
思いがけない離脱勝利
2016年6月24日、コービンを党首に押し上げた人々が共有していた英国社会の病理への懸念が、もっと広い範囲で、より深刻な症状となって現れた。EUへの帰属を問う国民投票で離脱票が過半数を超えたのだ。離脱が勝つとは離脱運動側ですら予想していなかった。
離脱が過半数を超える選挙区は都市部を除くイングランド全域に見られ、保守党地盤はほぼ全部が離脱多数だった。離脱投票者の大半は、そもそも保守党支持の帝国2.0を夢見る高齢者と、EUの規制を嫌うリバタリアンだ。この人たちは過去40年間、今か今かとこの時を待っていた。
しかしメディアが大きく取り上げたのはイングランド北部にいくつかある数値が突出した地域で、かつての労働党地盤だった。サッチャー以降、破壊され、二度と立ち直ることのなかった脱工業化コミュニティに、緊縮の影響で目に見える変化が現れていた。社会保障のおかげで低所得でも暮らしていけた人々に、手当削減という直接の影響だけでなく、医師の予約が取れない、学校の一学級の人数が増える、特別なケアの必要な子どもたちへの支援がなくなる、図書館や公民館、ユースセンターの閉鎖など間接の影響が表れていた。
そういった地域にEU懐疑政党のUK独立党や、極右政治団体の英国防衛同盟などが入り込み、タブロイド紙の助けも借りて、移民が、とりわけ移動の自由を利用してやって来たEU移民があなたがたの福祉を奪っていると吹き込んだ。
ところが、思いがけず離脱が勝ってしまったことで、昨日までの声なき弱者が何一つ条件も変わらないまま勝者になってしまった。この人々は、黄色い反射チョッキも着ておらず、石も投げず車に火もつけず、ただ生活を変えたい、エリートに一泡吹かせたい、私がここにいることを知らせたいと、粛々と投票し、一夜にして英国をひっくり返してしまった。こういった、都市部の繁栄から取り残された人々が英国中にいて、「私を見なさい」と言い続けている。ロンドンの一角から発せられたこうした声を、この翌年、英国の人々は聞くことになる。
グレンフェル・タワーの惨事
進行方向右側のドアの脇に立ち、車窓の風景を眺めていた。7月の空は灰色の雲に被われ、雨の気配がする。地下鉄ハマースミス・アンド・シティー線は始発駅から数駅分が高架になっているので、以前は遠くまで見渡すことができたが、郊外に転居して10年以上も乗らないあいだに建ったビルが景色を見慣れないものに変えていた。
変わっていたのは車窓の景色だけではなかった。名前が変わった駅が一つあり、以前はなかった駅が一つできていた。過去15年ほどの間にロンドンは激しく変貌しており、住民がすっかり入れ替わるほどジェントリフィケーション[都市の居住地域を再開発して高級化すること。しばしば低所得層は居住できなくなる現象=ソーシャルクレンジングを伴う]が深化した東ロンドンほどではないまでも、西ロンドンのこのあたりでも再開発が進んでいるのが見て取れた。車窓に目を凝らしていると、息子の手を引いて幾度となくその前を通った高層アパートが見えて来た。垂れ込める雲のあいだに開いた細長い鍵穴のようだ。無慈悲な黒さが目を射る。この日から1カ月ほど前の2017年6月14日未明、下層階からの出火が、壁伝いに燃え広がり、わずか15分ほどで最上階まで火に呑み込まれた。上階の住人を中心に犠牲者72人の大惨事となった高層アパート「グレンフェル・タワー」では、この日も現場検証が続いていた。
グレンフェル・タワーは、日本のメディアの第一報では、高級住宅地に建つ高層マンションと説明されていた。タワーが建つ北ケンジントン地区は、英国のみならず欧州全体でも指折りの富裕地区ケンジントン・アンド・チェルシー区にあるのだからそう思うのは無理もないが、北ケンジントンは、その英国一裕福な行政区にある国内有数の貧困地区だ。タワー住人の大半はつましく暮らす庶民であり、移民の家族が多かった。難民もいた。もともとは団地全体が公営住宅群であり、出火当時はそのうちのいくつかは民間に払い下げられていたが、建物の保守管理はケンジントン・アンド・チェルシー区および配下の管理団体の管轄にあった。この区は英国一平均余命が長い行政区であるが、裕福なチェルシーと火災のあった北ケンジントンでは、平均余命に12年の差がある。
グレンフェル・タワーは1974年に完成した24階建ての直方体で、英国のどこにでも見られる無愛想な高層集合住宅だ。この時代に建てられたブルータリズム建築のコンクリート集合住宅は「醜いコンクリートの固まり」として嫌う人も多いが、100年は使えるほど丈夫で、ともかく燃えないようにできている。中層でも高層でも、基本的にコンクリートの独立した箱の組み合わせであり、火事はそれぞれの箱の中に留まるように作られている。グレンフェル・タワーもそうであったはずなのだ。しかも、その前年に大掛かりな改装を終えたばかりだった。
改装そのものに問題があったことが、その夜が開ける前に明らかになった。建物内の不具合を区役所と管理団体に訴える居住者グループがあり、彼らが詳細を記録したブログを誰かが見つけてソーシャルメディアで共有したのだ。ブログを読んだ少なくない人々が、ケンジントン区のネグレクトが構造的なものであることと、その根源に貧困差別あるいはレイシズムを見出した。同グループの2016年11月20日付ブログにこうある。「深刻な火災による死者が出るまで外部の調査は行われず、KCTMO(同区のソーシャルハウジング管理会社)の杜撰な管理が注目されることはないと結論せざるをえない」
取材に入ったチャンネル・フォー・ニュースのアンカー、ジョン・スノウは激怒する群衆に囲まれ、「なぜ今まで取材に来なかったのだ」と罵られた。住人たちによる再三の不正の訴えをキャッチできなかったのは、今の英国メディアが多様性を欠き、普通の人々の生活への視線を失ってしまったせいではないかとスノウは後に述べている。
鎮火するかしないかの段階で、火の回りが早かったのは外壁材に不備があったからだとの証言が出て来た。大掛かりな補修工事は熱効率を上げるために行われたもので、窓を入れ替え、外壁を断熱材で被う工事が行われていたが、この断熱材の外側に貼られた可燃性のクラディング(被覆材)が死の罠になったと考えられている。また、クラディングと断熱材の間にできた隙間が火や煙を吸い上げる煙突の役目を果たし、さらには、新しい窓は密閉力が低く、毒性のある煙の室内侵入を防げなかったこともわかった。クラディングは住人のためではなく、自宅の窓からの景観を気にする人のために「醜いコンクリートの固まり」を隠し、地域の資産価値を高値に維持するために使用されていた。しかも、区の担当者がお金を出し渋ったことで不燃性のものから可燃性のものにグレードが落とされていた。ちょうどこの値切り交渉がおこなわれていたころ、区はその年の住民税が余ったとして、不動産所有者を対象に一律還付金を支給していた。区議会選挙が近かったからだと推測されている。英国で最も裕福な行政区で、不動産所有者に還付するお金はあったのに、タワーの壁にはわずかな価格の違いで可燃性のクラディングが貼られ、スプリンクラーも取り付けられなかった。区議会の役付担当議員は火事以降一度も公に姿を見せず、数週間後に辞任した。捜査が終了すれば、刑事責任に問われると見られている。
火災発生の翌日、メイ首相が現場を訪問したが、群衆を避けた囲いの中で、消防士のみに面会する様子を遠くから撮影された。同じ日、おそらくメイ首相の訪問を待っていたのだろう、コービン労働党党首が現場を訪問し、古い友人らに案内されてボランティアの様子などを、時間をかけて視察した。右派メディアは政治的スタントと断じたが、遠くから撮影されたコービンの顔には怒りや悲しみや共感が生々しく反映されていた。議会に戻ったコービンは緊急委員会に出席、緊急必須事項(葬儀費用の公費負担などが含まれる)を書簡にしてメイ首相に送ったが、そのうちのいくつか(例えば生存者全員への恒久住宅の供給)はまだ完遂されていない。
緊縮が破壊した社会の再生
英国は新自由主義最初期の実践場の一つであり、サッチャー以来かれこれ40年もこれをやっているが、2008年の金融危機以降に保守党政権が敷いた緊縮財政が、英国多文化社会の寛容さをへし折る最後の藁になるかもしれない。グレンフェル・タワーの大火災が明らかにしたように、剥き出しの資本主義は無意味なほど残酷だ。
政策とその結果にはタイムラグがあるのが普通だ。例えば、大学学費3倍増は、学生ローンの借入可能枠を広げたせいもあってすぐには影響が出なかったが、横ばいだった大学入学者数が下降したのは5年後で、その頃には「学費が上がっても学生の意欲は衰えない」と豪語していた制度の導入者たちは、キャメロン元首相もオズボーン元財相もクレッグ元副首相も、政界から去っていた。テリーザ・メイが内相時代に実施した警察予算の大幅削減で約2万1000人の警官が段階的に解雇され、これから少しタイミングをずらして、ロンドンをはじめとするイングランド各都市で、おもに青少年によるナイフ殺人が増加している。午後4時過ぎが事件発生のピークともいわれ、中学高校の下校時刻との関連が明らかだ。自治体の予算が削減され、図書館、プール、ジムその他、若者が放課後にすごせる場所がなくなったことも背景にある。
小学校の校長先生がラジオでこんなことを言っていた。放課後、家に帰りたくないと訴える子どもが何人もいる。家は暗く、寒く、食べるものもないのだと。家族はいるし、失業もしていない。節約のために電気もガスも使用を控えているのだ。25年教師をやって来て、こんなことは初めてだ。
緊縮の悪影響は、もはや一つ一つに対処するだけでは解決しないほど複雑にからみあっている。総合的なビジョンに基づく社会改革が必要であり、チーム・コービンが提供したマニフェストがその糸口になるだろう。英国はコービン政権をいますぐ必要としているが、既得権益層の抵抗の強さは、傍流扱いだった2017年の比ではない。コービンを平議員席から発掘したのは普通の人々であったことを思い起こすと、今度も同じことが起きないと、誰が言えようか。
(岩波書店『世界』2019年2月号より編集部の許可を得て転載)