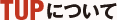FROM: Schu Sugawara
DATE: 2004年10月21日(木) 午後10時58分
琉球新報がスクープして掲載した外務省の機密文書、「地位協定の考え方」全文の「その4」をお送りします。
〔第十七条〕は、問題となっている犯罪者の裁判の問題です。果たして外務省は、この問題をどう解釈しているのか、じっくりとお読み下さい。また〔第十八条〕は騒音被害などの問題について外務省と米国側とのやりとりがどうなってるかが記述されている興味深い部分です。
TUP(平和をめざす翻訳者たち)配信係
- その1 (速報385号)
- その2 (速報388号)
- その3 (速報392号)
- その4 (速報394号)
機密文書「地位協定の考え方」その4
〔第十七条〕
第十七条は刑事裁判権の分配等につき定めている。
一 米軍当局の裁判権
1 第十七条の規定に従うことを条件として、米国の軍当局は、米国の「軍法に服するすべての者」に対して、米国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本において行使する権利を有する(1項(a))。米軍法に服する者の範囲については、米政府が合同委員会を通じて日本政府に通知することになっており(第十七条1項(a)及び2項(a)に関する合意議事録)、これによれば、米国統一軍法第二条及び第三条に掲げられるすべての者が含まれることとなっている(合同委員会合意「刑事裁判管轄権に関する事項」)ので、具体的には、陸海空軍の軍人、召集を受けた者、軍の学生、生徒、予備員等の外、米国外に駐とんする米軍隊に勤務し、或いはこれに雇用され、又はこれに随伴する軍属・家族等がすべて含まれるものと解せられている。米軍公用船の乗組員については、米政府又はその機関とタイム・チャーター(期間用船契約)を結んでいる船舶のすべての乗組員は、右の軍属に含まれるが、単なる航海用船契約又は一部用船契約の船舶の乗組員は、含まれないとされている(合同委員会の右の合意)。
2 第十七条の規定は、ナト協定第七条の規定と実質的に同文であるが、これら協定の締結後、累次の米連邦最高裁の判決により軍属・家族に対する平時における米軍法会議の管轄権が否定されるに至った結果(注86)、ナト諸国の間では、現在、軍属・家族は、右の「軍法に服するすべての者」には該当しないと解されている模様である。
(注86) 軍属を平時に軍法会議に付することが違憲であるとの判決は、一九六〇年の Guagliardo case において示された(これ以前の Covert caseでは、死刑についてのみ違憲ということであったが、この事件で初めて死刑以外についても違憲とされた。)。
平時における家族に対する管轄権については、一九六〇年の Singlton caseで、死刑であると否とを問わず、軍法会議の管轄権は違憲とされた。
以上は、平時(in time of peace)のことであって、戦時には必ずしも当てはまらない(事実ヴィエトナムにおいては、軍法会議は、右よりも広い管轄権を行使していた。)。
わが国においては、建前上は軍属・家族も軍法に服する者に含まれるとの考え方が現在でもとられている。(軍属・家族に対する軍法会議の懲戒裁判権は現在でも否定されていないので、この点に着目して軍法に服するとの説明をすることとなろう。)刑事裁判権の実際の運用としては、軍属の犯罪について米軍当局は、米軍当局に第一次裁判権のある場合(3項)でも(例えば軍属の公務中の犯罪については公務証明を出さないとか第一次裁判権の不行使をわが方に通告して来るとかして)裁判権を行使しないのが現状である。従って、軍属・家族の犯罪には事実上わが国が専属的裁判権を行使している如き現象を呈している。
3 軍法に服する者については、国籍の如何が問われていないので日本国民との関係が問題となりうるが、この点につき、4項は、「前諸項の規定は、合衆国の軍当局が日本国民又は日本国に通常居住する者に対し裁判権を行使する権利を有することを意味するものではない。ただし、それらの者が合衆国軍隊の構成員であるときは、この限りでない。」旨規定し、この点につき合意議事録は、日米の二重国籍者で、米軍法に服しており、かつ、米国が日本に入れたものは、4項の適用上日本国民とみなさず、米国民とみなす旨規定している。従って、日本国民が軍法に服する者に該当する場合がたとえあったとしてもイその者が米軍人でない限り、又はロ米国籍も有し、かつ、米国が日本に入れたものでない限り、米軍当局の裁判権に服することはない。米国が日本に入れたものとは、心ずしも明らかではないが、米国の命令指示等により日本に入国した者と解されている。(注87)
(注87)津田実・古川健次郎「外国軍隊に対する刑事裁判権」十四頁。この点については、家族が右にいう米国が日本に入れたものに該当するのか否かが必ずしも明らかでない。第九条1項の規定からみる限り積極に解される。
4 1項aの規定は、軍法に服する者が日本の領域外で犯した罪につき日本国内で軍法会議に付することを排除していない(1項bの規定振りからしてこの点は明らかである。)。沖縄返還協定の合意議事録は、返還前の米軍人の犯罪につき米軍当局は、返還後もかかる犯罪につき裁判権を行使しうる旨規定しているが、これは、地位協定第十七条1項aからみれば当然のことを定めたものである(従って、単に合意議事録で処理した。)。
更に、1項aの規定自体としては、日本で犯した罪について日本国外に連れ出した上裁判することについては、何ら触れていないが、この点については、第十七条の他の規定上制約がある(後述)。
二 日本側の裁判権
1 日本の当局は、米軍人・軍属及びその家族に対して、日本の領域内で犯す罪で日本の法令で罰しうるものについて、裁判権を有する(1項b)。日本の領域内とは、安保条約第五条の「日本国の施政の下にある領域」と同義であって、従って、例えば返還前の沖縄は、含まれず、又、北方領土・竹島は除かれる。(注88) (注89)
(注88)例えばわが国の領空を通過中の米軍機の事故から生ずる刑事責任の問題も1項bの範ちゅうに入りうるものであることは明らかである。
(注89)わが国の港に寄港中の米軍艦船内の犯罪が1項bにいう日本の領域内で犯す罪に該当するか否かの解釈につき、ナト協定の場合の考え方を英国に照会したところ、右の如き犯罪は、軍艦上の犯罪には旗国の裁判権が及ぶとの一般国際法上の確立した原則で律せられるべきものであり、地位協定は、かかる犯罪の処理まで意図したものではないとの回答があった経緯がある(なお、以上の点についての解釈は、未だ国会等で議論されたことはない模様)。
2 1項bの規定は、米軍人等の日本国外での犯罪についてのわが国の裁判権を排除している。従って、例えばこれら米軍人等が来日前に刑法第二条(本法ハ何人ヲ問ハス日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス)に該当する罪(例えば偽造公文書行使、第二条五号)を犯したことがあっても、米軍人等としての身分で日本にある限り、日本側の裁判権はない。その限りで1項(b)は、刑法第二条を排除している訳である。(注90)沖縄返還協定の合意議事録は、返還前の米軍人の犯罪につき日本側は返還後裁判権を行使しない旨規定したが、これは、地位協定第十七条1項(b)からみれば、当然のことを規定したものである(従って、単に合意議事録で処理した。)。
(注90)津田実前掲書も同様の考えをとっている。十三頁。
以上、第十七条1項(a)及び(b)からすれば、例えば軍人が、公務中であるか否かを問わず、わが国において殺人を犯した場合、1項(a)によれば米軍当局が裁判権を有し(軍法第百十八条等)、1項(b)によればわが国が裁判権を有することとなる(刑法第一条1項は、「本法ハ何人ヲ問ハス日本国ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」と定める。前記の例の場合は、刑法第二十六章等の罪に該当する。)。これが、いわゆる裁判権の競合と称されるものであって、この競合の場合の問題を解決(日米のいずれが裁判権を行使するか)するのが第3項の規定である。
三 専属的裁判権
1 米国の軍当局は、米軍法に服する者に対し、米国の法令によって罰することができる罪で日本の法令によっては罰することができないもの(米国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する(2項(a))右の罪は、米国法令違反の罪ではあっても、日本の法令に違反するものでなく、従って、日本の法益は何ら害されていないのであるから、かかる罪につき米軍当局が専属的裁判権を行使しても、わが国として何ら差支えない訳である。
2 逆に、日本の当局は、米軍人・軍属及びその家族に対し、日本の法令によって罰することができる罪で、米国の法令によっては罰することができないもの(日本国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する(2項(b))。この点については、軍法第百三十四条との関係が、少くとも理論的には、問題となる。即ち、同条は、軍隊の秩序及び紀律を乱したり、軍隊の威信を害する性質の行為等を罰することとしているが、外国に駐留する場合、当該外国法令に違反する行為は、軍法の右規定により罰しうるのではないかとの考えがあるからである。この考え方に立てば、日本側が専属的裁判権を行使するケースはないことになる。しかし、実際にはかかる考え方は、米軍法会議自身によって否定されている模様である。(この点については、連邦高裁も軍法の右規定は憲法違反であるとの判断を昭和四八年三月行なっている。)(注91)
(注91)従って、実際には、例えば通常の交通違反(軍法では、酔払い運転、乱暴運転等については規定がある―第百十一条―のでその他の場合)については、日本側の専属的裁判権により処理されている。
3 2項及び3項の適用上、国の安全に関する罪には、(i)当該国に対する反逆、(ii)妨害行為(サボタージュ)、諜報行為又は当該国の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令の違反が含まれる(2項(c))。この点につき合意議事録は、両政府は、2項(c)に掲げる安全に対するすべての罪に関する詳細及びそれぞれ自国の現行法の規定でそれらの罪を定めるものを相互に通報すべき旨定めている。米側からはこの通報はなされていない模様であるが、米国法令にいわゆる「反逆罪」、「エスピオネージ」というような罪がこれに当ると考えられる。(なお、米軍当局が専属的裁判権を有するものとしては、右のほか、「逃亡罪」、「抗命罪」、「上官侮辱罪」等軍規律に関する罪がある。)
日本当局からは、口頭で日本に対する反逆及び妨害行為(サボタージュ)諜報行為又は日本の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令違反等なる旨通報している。具体的には、刑法上の内乱又は外患の罪、国家公務員法第百九条第十二号(公務上の秘密)、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪が考えられる。
四 競合裁判権の分配
日米両当局の裁判権が競合する場合には、3項(a)(b)(c)の規定が適用される(3項頭書)。
1 米国の軍当局は、次の(i)及び(ii)の罪については、米軍人又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する(3項(a))。
- もっぱら米国の財産若しくは安全のみに対する罪又はもっぱら米軍隊の他の軍人・軍属若しくはそれらの者の家族の身体若しくは財産のみに対する罪
- 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪
2 もっぱら米国の財産のみに対する罪とは、例えば米軍の倉庫から軍用食糧を盗んだような場合を指す。しかし、盗んだものが日本の国有財産であったような場合は、これに該当しない。又施設・区域内における放火であっても、それが日本国又は日本国民の所有にかかる建造物を焼いた場合には、右に該当しないことは勿論、また仮に米軍所有の建造物を焼いただけであっても、具体的に公共の危険を生じたような場合には、右に該当しないと考えられる。もっぱら米国の安全のみに対する罪とは、例えば施設・区域の中で米軍の機密を探知したような刑事特別法第六第に該当するような罪の場合を指す。もっぱら軍人・軍属又はそれらの者の家族の身体若しくは財産のみに対する罪とは、例えば軍人相互の傷害暴行等を指す。軍人相互のこれらの行為が同時に日本人を傷つけたりする場合は、これに該当しない。ここにいう「家族」とは、地位協定第一条にいう家族である。日本人妻も含まれる(従って、軍人がその日本人妻に傷害を与えた場合には、米側が第一次裁判権を有する。)。(注92)
(注92)以上の点については、津田実前掲書に詳しい。
3 公務執行中とは、単に勤務時間中という意味ではなく、公務執行の過程においてという意味であると解されている。公務とは、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって要求され又は権限付けられるすべての任務若しくは役務を指す旨合意されている(合同委員会「刑事裁判管轄権に関する事項」。なお、合意の本文においては、具体的にいかなる行為が公務中の行為に該当するかにつきかなり詳細な了解が記録されている。)。
4 3項(a)(ii)については、公務か否かを誰が認定するかが最も重要な問題である。この点につき合意議事録は、「米軍人・軍属が起訴された場合において、その起訴された罪がもし被告人により犯されたとするならば、その罪が公務執行中の作為又は不作為から生じたものである旨を記載した証明書でその指揮官又は指揮官に代わるべき者が発行したものは、反証のない限り刑事手続のいかなる段階においてもその事実の十分な証拠となる」趣旨を定めている。このように公務の認定が一次的には指揮官に委ねられているのは、事件解決の迅速性という面からする要請を考慮したものであると考えられている。尤も、米側の公務証明書に反証がある場合は、日本側検事正は直ちに米側に通知し、それで解決しない時は合同委員会で結論を出すこととなっている(合同委員会の前記合意)。更に、3項(a)(ii)に関する前記合意議事録は、米側の公務証明書は、いかなる意味においても日本の刑訴第三百十八条(裁判官の自由心証を定める。)を害するものと解釈してはならない旨定めているが、これは、裁判において前記の公務証明書には法律上の推定の効果が与えられないことを意味するものと解されている。
5 日本側は、3項(a)の(i)及び(ii)以外の罪については第一次の裁判権を有する(3項b)。具体的に述べれば、日本側は、先ず、家族の犯した罪については常に第一次裁判権を持つ。家族が例えば米軍人の身体に対して犯した罪(3項(a)(i)の如き)についても同様である。(なお、第十四条契約者に対しても常に日本側が第一次裁判権を持つ。第十四条8項)更に、軍人・軍属の犯罪であっても3項(a)(i)及び(ii)に該当しない罪については、日本側が第一次裁判権を持つ。
6 第一次の裁判権の意味は、当該権利を有する側がその権利を行使しないか又は放棄した場合を除き他方の側は、裁判権を行使しえないことを意味する。第一次裁判権を有する側が裁判権を行使するともしないとも明らかにしないまま事件を放置しておくことは、協定の趣旨に反する。第一次裁判権を有する国は、その権利を行使しないと決定した時はできる限りすみやかに他方の側の当局にその旨を通告しなければならない(3項c第一文)。合同委員会は、かかる場合の運用につき細則を定め、例えば米側が第一次裁判権を有する事件(軍人の公務中の犯罪等)でも日本人が被害者である如きものについては、かかる犯罪についての通知から十日以内に米軍当局が裁判権を行使するか否かを日本側に通告してこないときは、日本側が裁判権を行使できること等を定めている(合同委員会の前記合意)。
第一次裁判権を有する側の当局は、他方の側がその権利の放棄を特に重要と認めた場合において、その他方の側の当局から要請があったときは、その要請に好意的考慮を払わなければならない(3項c第二文)。3項cに関する合意議事録は、裁判権放棄の手続は、合同委員会が決定すべき旨規定し(第1項)、合同委員会は詳細な手続を定めている。更に、合意議事録同第2項は、日本側が第一次裁判権を放棄した事件の裁判及びa(ii)に定める罪(公務中の犯罪)で日本国・日本国民に対して犯されたものにかかる事件の裁判は、別段の取極が相互に合意されない限り、日本において、犯罪が行なわれたと認められる場所から適当な距離内で直ちに行なわれなければならない旨、及び日本側当局の代表者は、その裁判に立ち会うことができる旨定める。このような事件には、日本側としても国民感情もあり重大な関心があるということを前提にした規定である。この規定により、米側は、このような事件については、被告を日本国外に連れ出した上例えば米本国で裁判することはできないこととなる。(注93)
(注93)公務遂行中の軍人・軍属の行為は、軍隊の機関としての行為であるから、かかる行為には日本法令は適用されない旨前述した(第十六条の項参照)が、かかる行為が犯罪を構成し、米側が裁判権を行使しないときは、日本側が裁判権を行使することができるが、これは、右の行為を日本法令によって評価することを前提とすること勿論である。この意味では、右の行為にも日本法令は、いわば潜在的には適用されている訳である。これを「右の行為には法令の適用はあるが米側が不行使を決定しない限り裁判権は及ばない」と表現するか否かは言葉の問題である。ちなみに、英語の jurisdiction とは、右の場合、裁判権・管轄権という意味に加え、法令の適用自体の意味も含まれている如くである。
五 逮捕・身柄引渡し等の相互協力
1 日本側当局及び米軍当局は、日本の領域内における米軍人・軍属及びその家族の逮捕及び4項までの規定に従って裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて相互に協力しなければならない(5項(a))。この規定により日本側が協力するべき対象は、協定上日本側の裁判権の対象となる罪を犯した米軍人等に限られない。即ち、米側の専属的裁判権の対象となる罪を犯した米軍人等や日本国外で罪を犯し米側裁判権の対象となる米軍人等(これらの者が協定上の軍人・軍属及びその家族として入国したと観念される場合。なお、この点は、第一条の項で述べたところ参照。)のわが国における逮捕等についても日本側に協力義務がある。この点につき、刑事特別法第十八条は、米軍からの要請がある場合には、日本側当局は、日本の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき米軍人等を逮捕できるとの趣旨を定めている。なお、協定第十七条5項(a)の規定によれば、米軍当局が日本側の第一次裁判権の対象となる者を逮捕したときはその身柄を日本側に引き渡すべきこととなるが、5項(c)は、その例外を定めたものと解される。
2 日本側当局は、米軍人・軍属及びその家族を逮捕したときは、米軍当局にすみやかに通告しなければならない(5項(b))。この点については、日米友好通商航海条約第二条は、いずれかの国の領域内で他方の国民が抑留された場合には、その者の要求に基づき、もよりの地にあるその者の本国の領事官に直ちに通告されるべき旨定めているが、米軍人等については、地位協定上の通告を行なえば足りるものと解されている。なお、米軍当局が日本側の第一次裁判権の対象となる事件につき米軍人等を逮捕したときは、直ちに日本側当局に通告して来ることになっている(第十七条5項に関する合意議事録第2項)。
以上の点に関する通告の手続等については、合同委員会の詳細な合意がある(「刑事裁判管轄権に関する事項」)。
3 日本側が裁判権を行使すべき米軍人・軍属(家族が含まれていないことに要注意)たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が米側の手中にあるときは、日本により公訴が提起されるまでの間、米側が引き続き行なうこととなっている(5項( c))。米側の手中にあるときは、米側の刑事手続上米側に拘禁されている場合のみならず、より広い意味で身柄が米側により拘束されていれば足りるものと解される。又、日本側が裁判権を行使すべきとは、日本側が第一次裁判権を行使すべきの意である。日本側の裁判権にしか服さない者についての身柄拘束は、常に日本側が行なう(合同委員会の右合意)。家族については、日本側がこれを逮捕した場合と同様に取り扱われるべきものと解される。即ち、この点について5項に関する合意議事録第1項は、日本側が第一次裁判権を有する事件につき、日本側当局が米軍人・軍属及びその家族を逮捕したときは、その犯人を拘束する正当な理由及び必要があると思料する場合を除くほか、米軍当局による拘禁に委ねるべき旨規定している。(注94)
(注94)なお、同項ただし書は、日本側当局がその犯人を取り調べることができることをその釈放の条件とした場合には、日本側当局の要請があれば、いつでも取り調べることができるようにすべき旨及び日本側当局の要請があれば、日本側当局がその犯人を起訴したときにその身柄を日本側当局に引き渡すべき旨定めている。なお、又、米側が逮捕した場合でも、日本側が特に身柄を確保する必要があると認めて要請した際には日本側に身柄が引き渡されることになっている(合同委員会の合意)。
右において、正当な理由及び必要とは、証拠隠滅等のおそれのある場合等が該当するものと解される。
以上の規定により、日本側が第一次裁判権を有する事件であっても、米軍人・軍属及びその家族の公訴提起までの身柄の拘束は、日米いずれの側が逮捕したかに拘わりなく、一定の場合を除き、米側によって行なわれることとなるが、この点は、従来国会等において第十七条の規定中最も問題にされて来ている。ナト協定においては、協定本文には日米協定の第十七条5項(c)と同様の規定があるが、合意議事録に該当する規定はないので、比較上は日本の方がより制約されているが如く見えるが、実際には、米側は各国と別途の協定を締結する等を通じて日米協定とほぼ同様の権利を確保している。(注95)
(注95)イタリー、トルコ、イギリス、ギリシア等。
以上の点は、もっぱら米国との政治的妥協の産物であり(米議会において米国が第一次裁判権を放棄する範囲が広すぎるとの議論があり、これに対抗するためせめて身柄拘束に関しては米側権利を広くしようとしたこと)、説得力ある説明は必ずしも容易ではないが、少くとも(イ)食事・寝具等の風俗習慣等の違いから日本側としてもこれらの者を拘禁することは不必要な手数がかかること、(ロ)米側の拘禁に委ねても逃走のおそれなく、又取調べ上は支障なく、米側による身柄拘束は、いずれにしても日本側による提起までの間という暫定的なものにすぎないこと、(ハ)対象となる事件については米側にも第二次的には裁判権のあるものであり、第一次裁判権を有する側と第二次裁判権を有する側との間の均衡の問題として米軍人等を米側に暫定的に委ねても必ずしも不当とは考えられないこと(この点は、前述のとおり、日本側の裁判権にしか服さない者の身柄は常に日本側に引き渡されることになっていることからもいえよう。)等の理由によりある程度の説明は可能と考えられる。
4 日本側当局及び米軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出(犯罪に関連する物件の押収及び相当な場合にはその引渡しを含む。)について、相互に援助する。ただし、それらの物件の引渡しは、引渡しを行う当局が定める期間内に還付されることを条件として行うことができる(6項(a))。双方の当局は、裁判権を行使する権利が競合するすべての事件の処理(の結果)について相互に通告する(6項(b))。これらの規定の実施についての細則は、合同委員会において合意されている(「刑事裁判管轄権に関する事項」)。
5 米軍当局は、日本においてその裁判の判決を執行することができるが、死刑については、日本の法制が同様の場合に死刑を規定していない場合には、日本国内で死刑を執行してはならない(7項(a))。また、日本側当局は、米軍当局が第十七条の規定に基づいて日本の領域内で言い渡した自由刑の執行について米軍当局から援助の要請があったときは、その要請に好意的考慮を払うことになっている(7項(b))。
六 被告人の保護
1 被告人が「この条の規定に従って」日米いずれかの当局により裁判を受けた場合において、無罪の判決を受けたとき、又は有罪の判決を受けて服役しているとき、服役したとき、若しくは赦免されたときは、他方の側の当局は、「日本国の領域内において」同一の犯罪について重ねてその者を裁判してはならない。ただし、この項の規定は、米軍当局が軍人を、その者が日本側当局により裁判を受けた犯罪を構成した作為又は不作為から生ずる軍紀違反について裁判することを妨げない(8項)。この規定は、日米間での一事不再理を定めたものである。これは、「この条(即ち第十七条)の規定に従って」行われた裁判についての一事不再理であるから、日本側に第一次裁判権がある事件で、日本側がその放棄もせず又その不行使の通知もしていないのに米軍当局が先に勝手に裁判してしまった場合(又はその逆)には該当しないと解される(昭和四二年十月三日日本の最高裁判例。ナト協定関係国においても同様に解されている模様。)。この規定により、米軍当局により裁判された者については、わが国刑法第五条(「外国ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行為ニ付キ更ニ処罰スルコトヲ妨ケス」)の規定は、排除されることになる。なお、協定の右規定は、「日本国の領域内において」の一事不再理を定めるものであるので、日本側による裁判後(例えば無罪の場合)、米軍当局がその者を日本国外に連れ出した上裁判に付することはわが方の関知するところではない。
2 米軍人・軍属及びその家族は、日本側の裁判権に基づいて公訴を提起された場合には、いつでも、次の権利を有する(9項)。
- 迅速な裁判を受ける権利
- 公判前に自己に対する具体的な訴因の通知を受ける権利
- 証人対決権
- 強制的手続により証人を求める権利(証人が日本の管轄内にあるとき)
- 弁護人選択権又は無償で(又は費用の補助を受けて)弁護人を持つ権利
- 有能な通訳を用いる権利
- 米政府代表者と連絡し、及び自己の裁判に立ち会わせる権利(注96)
(注96)この点との関連で、9項に関する合意議事録は、米軍人・軍属及びその家族で日本の権限の下に拘禁されているもの(従って、公訴提起以前も含まれる。)に米国当局が要請すれば接見する権利があること(第二項)及び9項(g )の規定は、公開裁判に関する日本の憲法の規定を害するものと解釈されないことを規定している(第三項)。なお、右の裁判の立ち会いとは、刑訴上何らかの身分を与えられるというものではなく単なる傍聴者である。
右合意議事録第1項は、第十七条9項の(a)から(e)までの権利は、日本の憲法の規定により日本の裁判を受けるすべての者に保障されている旨述べるとともに、米軍人等は、これらの権利のほか、日本の裁判を受けるすべての者に対して日本の法律で保障するその他の権利を有するとして、具体的にわが憲法第三十四条及び三十六条から三十九条までの権利の一部を列示している。右において、協定本文に掲げられる権利と議事録に掲げられるものとの法的な差は、前者については協定自身により保障されているが、後者は、日本の憲法が変われば(基本的人権なのでこれが変更されることは考えられないが)その限りにおいて変りうるということにある。尤も、前者の権利も憲法・法律の枠内のものであることは、合意議事録第1項の頭書きにあるとおりで、その権利の具体的実現の手続は、憲法・法律の定めるところによる。(注97)
(注97)以上の点については、昭和四二年日本の裁判所が米軍人を被告とする裁判で、所在不明の被害者(検事調書作成後行方不明)を証人として調べず、その検事調書を刑訴第三百二十一条1項2号(供述者が所在不明でもその者の書面で署名・押印のあるものは証拠としうる。)により証拠として有罪の判決をしたことに対し、米側が協定第十七条9項(c)(証人対決権)に反すると抗議越し、これに対し、わが方は、右証人対決権の具体的実現の態様は、わが国の憲法・法律(この場合刑訴)によるべき旨回答した経緯がある(いわゆるハロルド・タッカー事件。本件経緯は未公表)。
七 警察権(施設・区域内とその近傍)
1 米軍の正規に編成された部隊又は編成隊は、施設・区域において警察権を行う権利を有する。米軍隊の軍事警察は、施設・区域において秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる(10項(a))。この規定は、次の二つのことを意味する。
(1)施設・区域内において米軍当局は、通常すべての警察権を有する。従って、通常すべての逮捕は、米軍当局によって行われる(10項に関する合意議事録第1項前段第一文)。
(2)日本の警察権の施設・区域内における行使は、原則として行ないえない。従って、日本側の裁判権にしか服さない者の逮捕でも施設・区域内においては米軍当局が行ない、その身柄は、日本側に引き渡される(同合意議事録第1項中段)。(刑事特別法第十条1項は、右規定を受けて、右の如き逮捕は、米軍の同意を得て行うか又は米軍に嘱託して行なうべき旨定めている。)
2 尤も施設・区域内における右の如き米軍警察権は、属地的に排他的な特権ではない。もし、施設・区域内における米軍警察権の内容が、施設・区域外における日本の警察権のそれのように完全なものであり、かつ、施設・区域内においては、その場所が施設・区域内であるという理由で、すべての者に対して米軍のみが警察権を有し、日本の警察権が排除されるというのであれば、そのような米軍警察権は属地的に排他的な特権というべきであり、施設・区域内に、わが国の統治権の一部が属地的に及ばない場合といわざるを得ない。
しかしながら、施設・区域内の米軍警察権の内容は、施設・区域外における日本の警察権のそれのように完全なものではない。すなわち、右の米軍警察権には米軍人等に対する関係では司法警察作用を含むすべての警察作用を含むが、右以外の者(日本人等)に対する関係では、少くとも司法警察作用を含まない(このことは、米軍警察権が属人的なものであることのあらわれであるといえよう。なお、かかる米軍警察の行為に対して日本人が反抗することは、日本法令上の公務執行妨害罪とならない。また、逮捕も、刑事手続としての逮捕でなく、実際上とり押さえるという意味と解釈すべきであろう)。
一方、日本の警察権は、これを施設・区域内において行使するに当っては、重大な罪を犯した現行犯人を追跡逮捕する場合(後述)を除き、米軍当局の同意を必要とするが、同意があれば、米軍人等に対しても、その他の者に対しても、発動し得るのであり、その場合には、わが国の法令によって与えられている権限をわが国の法令に従って行使するのであるから、施設・区域内においても、日本の警察権はその権限そのものが制限されているわけではなく、その行使の仕方が制約されているに過ぎない。換言すれば、属地的に権限そのものが制限されているのではなく、権限はあるが、これを現実に行使するに当っては、重大犯人追跡逮捕の場合を除き、管理者でありかつ限定的ではあるが警察権を有している米軍当局の意向を尊重して、その同意を求めるという手続を経た上で行使することとしているに過ぎないのである(右の同意は、それまで無かった権限を与えるものではなく、本来存する権限の行使につき必要とされる一つの条件と考えるべきである)
しかも、重大な罪の現行犯人を追跡して逮捕する場合は、施設・区域内においても、無条件にこれを行うことが協定上できるのであり(注98)、その場合には、通常の場合と同様わが国の法令に基づく権限をわが国の法令に従って行使するのである(これは、施設・区域内にも、日本の警察権が本来的に及んでいることのあらわれといえる)。
(注98)右合意議事録第1項前段第二文。なお、刑事特別法第十条2項は、この規定を受けて死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる罪に係る現行犯人を追跡して施設・区域内において逮捕する場合には、米軍の同意を得ることを要しない旨定めている。
以上のように、日本の警察権は、施設・区域内にも本来及んでおり、属地的にその権限そのものが制限されているわけではない。従って、特別の場合(重大な罪の現行犯人追跡の場合)には米軍当局の意思に拘わらずこれを行使し得るのであるが、その他の場合は、わが国が米軍に対し施設・区域の使用を認めている関係上、そのいわゆる管理権を尊重し、わが国の強制的権限を無条件に行使することを差控えることとしているのである。このことは、一国の軍隊が他国に駐留する場合、その軍隊に使用が許されている施設・区域には、被駐留国の官憲は、軍当局の同意がない限り原則として立ち入るべきではないとする国際法上の原則に基づくもので、ナト協定の下でも同様に考えられており、国際法的には当然のことといえるのであり、なんら不当とするに当らない。
3 米軍事警察は、施設・区域内で秩序及び安全の維持のため「すべての適当な措置」を執りうるとされているが、具体的に例えば催涙ガスの使用も認められるかという点が問題になったことがある。この点については、「すべての適当な措置」とは、通常の場合には日本の警察官職務執行法程度の内容の範囲内の措置が考えられ、従って、秩序及び安全の維持を確保するため必要な場合には催涙ガスを含む武器の使用も(正当防衛等右法令で定めるが如き際には)認められてしかるべきであるとの政府答弁が行われている。(注99)
(注99)昭和四五年五月七日、衆・外議事録十六頁。
4 米軍当局は、施設・区域の「近傍」において、当該施設・区域の既遂又は未遂の現行犯にかかる者を法の正当な手続に従って捕逮できる。これらの者で日本側裁判権にしか服さないものは、すべて直ちに日本側当局へ引き渡される(右合意議事録第1項後段)。右において「近傍」とは、施設・区域の安全を害する犯罪の既遂又は未遂を行ないうる程度に当該施設・区域に近傍した場所を意味することになっている(合同委員会の右合意)。(なお、武器使用については、後述の施設・区域外の場合と同様に考えるべきであろう。)
5 日本側当局は、施設・区域内にあるすべての者・財産について、又所在地の如可を問わず米軍財産について、捜索、差押え又は検証を行なう権利を行使しない(米軍の同意があれば勿論別である)。このような場合、日本側が希望すれば、米軍当局が右行為を行なう。これらの財産で米政府又はその附属機関(例えば第十五条機関)が所有又は利用する財産以外のものについて裁判が行われたときは、米側は、それらの財産を裁判に従って処理するため日本側当局に引き渡す(右合意議事録第2項)(注100)
(注100)なお、右合意議事録第1項前段第一文及び第2項では、「合衆国軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設及び区域」との表現が使用されているので、米軍が全く警備していない施設・区域では通常の逮捕・捜索等を日本側が行うことは排除されていないものと解される。
八 警察権(施設・区域外)
1 地位協定は、施設・区域外においても米側に軍事警察の使用を認めているが、かかる軍事警察の使用は、「必ず日本国の当局との取極に従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して」なされるべきこと、並びに「合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内」に限られるべきことが規定されている(10項(b))。施設・区域外の警察権は、米軍人等の逮捕等を含めすべて日本側が行うのが当然であるところ、この規定は施設・区域外の米軍人間の規律及び秩序の維持のためにはむしろ米軍警察を用いた方が実際的であるという点を考慮しつつ、他方では、かかる米軍警察の行動が日本側の警察権と衝突したり、日本の私人の権利等を侵害したりすることのないよう一定の条件を付することを目的としたものである。合同委同会の合意(「刑事裁判管轄権に関する事項」)には、右の条件につき詳細な規定を設けている。そのうちの主要点を次に述べる。
(1)米軍人等の現行犯の逮捕
(2)所在地の如何を問わず軍用財産等の安全に対する罪に関する現行犯については、日本の警察機関の措置を求めるいとまがないときには、その軍用財産の周辺で令状なくして逮捕し、又は、かかる行為を制止することができる。この場合、日本刑法の正当防衛・緊急避難に該当する場合にのみ武器(従って、催涙ガスも含まれると解される。)を使用できる。(従って、この場合には、米軍警察権は、日本人にも及ぶことになるが、右の逮捕、制止は、正当防衛的な自衛行為であって、一般にも条理上認められているところであり、かつ、又、現行犯人は、わが国の刑訴上、一般私人でも逮捕しうるのであるから、米軍当局によるこれらの自衛的な措置は当然のことである。)
(3)重大な罪の米軍人等の現行犯人を追跡逮捕するため必要なときは、令状なくして、施設・区域外の住居等(従って、日本人の住居も含む。)に立ち入ることができる。
(4)米軍人等が専属的に占有する場所(Places occupied exlusively by)においては、米軍当局はいかなる事件についても捜索又は差押を行うことができる。
(5)第十七条10項(
2 なお、米軍当局による施設・区域外での警察権の行使が協定に違反する場合(乱用等)には、当然合同委員会等で抗議することとなる。かかる当局の要員の行為が犯罪を構成する場合には、第十七条の規定により処理される。なお、損害が発生した場合には、第十八条の規定により損害賠償が行われる。
九 その他
1 安保条約第五条の規定が適用される敵対行為が生じた場合には、日米いずれの政府も、他方に対して六十日前に予告を与えることによって、第十七条のいずれの規定の適用も停止させることができる。この権利が行使された時は、両政府は、適用を停止される規定に代わるべき適当な規定を合意するため直ちに協議しなければならない(11項)。安保条約第五条の発動される如き事態には、軍事裁判権、軍事警察権の拡大が必要となることが考えられるので、かかる点を念頭において規定したものと考えられる。
2 第十七条の規定は、地位協定の効力発生前に犯したいかなる罪にも適用しない。それらの事件に対しては、行政協定第十七条の当該時に存在した規定を適用する(12項)。当然の経過規定である。行政協定第十七条は、昭和二八年十月二九日改正され、改正後は、地位協定第十七条と実質的に同文であるので、その時以後の事件については右経過規定は意味がないが、改正以前(米軍当局は、米軍人等のすべての犯罪につき専属的裁判権を有していた。)のものについて理論的な意味があった。
〔第十八条〕
第十八条は、地位協定の運用に関連して生ずる請求権の処理につき定める。本条の規定も、第十七条の場合と同様、ナト協定の規定と実質的に同一である。なお、本条については、5項の規定(米軍の活動から生ずる私人の請求権の処理)が最も問題となる。
一 防衛隊の財産に対する損害
1 日米各国は、自国が所有し、かつ、自国の陸海空の「防衛隊」が使用する財産に対する損害については、次のa又はbの場合には、他方の国に対するすべての請求権を放棄する(1項前段)。
- 損害が他方の国の防衛隊の構成員又は被用者によりその者の公務執行中に生じた場合
- 損害が他方の国が所有する車両、船舶又は航空機でその防衛隊が使用するものの使用から生じた場合。ただし、損害を与えた右車両等が公用のため使用されていたとき、又は損害が公用のため使用されている財産に生じていたときに限る。
2 第十八条を通じて使用されている「防衛隊」とは、日本については自衛隊をいい、米国についてはその軍隊をいうものと解されている(11項)。
3 又、第十八条を通じて「公務中」であるか否かが問題となる規定があるが、日本側につき自衛隊の構成員又は被用者の公務とは、わが国内法令により与えられた任務を遂行するためこれらの者に命じられた職務をいう。米側についてはその軍隊の構成員又は被用者の公務は、第十七条における公務の意味(法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって要求され又は権限付けられるすべての任務若しくは役務)と同様に考えてよいであろう。(注101)。
(注101)第十八条に相当するナト協定第八条の1項では、「北大西洋条約の運用と関連する任務の遂行中」云々と規定しているところ、これはナト諸国の場合は、ナトに供出された軍隊と然らざるものとがあるので、このように規定されたものと考えられるが、日米条約の場合は、米軍については、それが日本にあるのはとりもなおさず安保条約に基づくものであるが、日本側の場合には、これに対応する自衛隊の任務は安保条約に基づくものではないので「単に」公務としたものである。ただ、米側についても安保条約の実施に関連しての公務とは限定されていない結果、例えば、米軍による日本人の災害救助活動等は、他の要件を満せば、第十八条にいう公務と考えられる(この点は、第十七条の場合も同様。)。なお、公務中か否かの決定の問題については、8項に規定があるので後述する。
4 1項の規定は、2項との対比において、日本国内での財産の損害ばかりでなく、日本国外における場合にも適用されることは、文理上明らかである。(この点は、行政協定の第十八条2項が地位協定第十八条1項及び2項に該当する場合を併せて規定していた際に「日本国において所有する財産」としていたことからもいえる。)この点については「日本国における合衆国軍隊」の地位協定の趣旨に鑑みれば若干奇異であるが、他方、地位協定は安保条約の趣旨よりして日米の防衛隊が日本国外において共同で行動する場合等(公海上での共同演習等)をあらかじめ予想して右の如き規定振りをしたものと解されるので、右の文理解釈は妥当であると考えられる。(注102)
(注102)ナト協定も同様の規定振りをしているが、ナト条約自体が双務的であるので特に問題はない。
右の点については、昭和四七年八月、日米相互防衛援助協定の実施に関連する任務(具体的には本件援助により生産したミサイルの試験実施)により訪米中の自衛艦が米軍艦により衝突され破損するという事故があった際、米側は地位協定第十八条1項により処理すべく申し越した経緯がある。本件は、その後、両国の当局間で事実上処理されたが、本件は、右自衛艦の任務(広く解すれば安保条約との関係を考慮しうる)にも鑑み、米側提案通りに処理することも全く不可能ではなかったと考えられる(なお、本件経緯は未公表)。
5 海難救助についての一方の国の他方の国に対する請求権は、放棄される。ただし、救助された船舶又は積み荷が、一方の国が所有し、かつ、その防衛隊が公用のため使用しているものであった場合に限る(1項後段)。この規定は、海難救助の際の請求権の問題が個個の具体的場合に受けるべき報酬の額の決定等必ずしもその処理が容易ではないので、両国間の協力関係に鑑み、日米の国対国の問題である場合に限り(従って救助者が民間人の場合は本規定の枠外)これを相互に放棄することとしたものである。右規定の場合も日本国内における救助に限られない。なお、右請求権は、本来不法行為に基づき生ずるものではなく、従って、1項前段の請求権とその性格を異にするものであるが、一方の国の他方の国に対する請求権の放棄という点でその処理を同じくするものであるので便宜上1項の中に規定したものである。なお、又、右規定中、積み荷が公用のため使用中とは、現に積極的に公用に使用されていることを要するものではなく、防衛隊が使用するためであれば(例えば在日米軍の使用のため積載されていたジープ)足りると解される。
二 国有財産に対する損害
1 いずれか一方の国が所有する1項に規定される以外の財産で日本国内にあるものに対して1項に掲げるようにして損害が生じた場合には、両政府が別段の合意をしない限り、2項(b)の規定に従って選定される一人の仲裁人が、他方の国の責任の問題を決定し、及び損害の額を査定する。仲裁人は、又、同一の事件から生ずる反対の請求を裁定する(2項(a))。この項が対象とする国有財産が日本国外において損害を受けたとき(例えば、日本の公有船舶が公海上で米艦船に衝突された場合)には、この項の適用はなく、一般国際法によって処理されることとなる。他方、右の如き事故が日本の領海内で起った場合には本項によることは、5項(g)の規定振りからして明らかである(この点後述)。両政府の別段の合意としていかなるものが考えられるかは、必ずしも明らかではない。2項(b)以下の規定によらないことも合意できようが、いずれにしろ、わが方としては政府限りで処理しうるためには、国内法(特に国有財産法等)で認められる範囲内のものでなければならない。
2 仲裁人は、両政府間の合意によって、司法関係の上級の地位を現に有し、又は有したことのある日本人の中から選定される(2項(b))。仲裁人のための事務局の設置、その規模等の問題は、右の両政府間の合意によって処理されるものと考えられる。仲裁人の裁定は、日米双方に対して拘束力を有する最終的なものである(2項(c))。仲裁人が裁定した賠償の額は、5項(e)の(i)から(iii)までの規定に従って分担される(2項(d))。仲裁人の報酬は、両政府間の合意によって定め、両政府が仲裁人の任務の遂行に伴う必要な経費とともに、均等の割合で支払う(2項(c))。
3 右の場合において、日米双方は、いかなる場合においても千四百ドル又は五十万四千円までの額については、その請求権を放棄する。ドル対円の為替相場に著しい変動があった場合には、両政府は、前記の額の適当な調整について合意する(2項(f))。右控除額は、右の額を越えるすべての損害についても及ぶものである(右の額を越えない損害については、単に請求権の放棄となる。)。この場合控除の残額が5項(e)により分担される。(注103)
(注103)この点については、ナト協定第八条2項(f)は、「損害が次の額に達しない場合には、その請求権を放棄する。」とあるのでこの額を越える損害については、そもそも控除の必要はないとする考え方もあるが、ナト当事国間の解釈は前記のとおりの趣きであり(安保国会当時の擬問擬答)、わが国もこの解釈によって処理して来ている。
又、この解釈は、学者によっても支持されている(例えば Status of Military Forces under Current International Law, Serge Lazareff, p 289)。なお、ナト協定の意味が右のとおりであることは、第八条2項(f)第二文が「その財産が同一の事件において損害を被った他の当事国も、前記の額までその請求権を放棄する」と規定していることからもいえよう。
「為替相場の著しい変動」につきいかなる変動が「著しい」とされるかの基準はない。ナト諸国においても「著しい」変動による調整が行なわれたことは現在までない模様。なお、調整についての日米間の合意は、合同委員会の合意として処理されることとなろう。
4 1項及び2項の適用上、国が所有する財産であるか否かの判断は、当該国の国内法によるべきものである。この点、行政協定(同協定第十八条2項は、他方の側の公務中の行為から国有財産に対する損害が生じた場合の請求権は、相互放棄としている。)時代から懸案になっている問題として三公社の所有財産は、国有か否かというものがある。(注104)
(注104) 対米債権としては、米軍車両の列車に対する衝突、電柱に対する衝突等、債務としては、国鉄が洞爺丸事故により公務中の米軍人三八名に与えた損害が考えられる。
三公社が日本政府機関でないとする日本側論拠は、(1)設立は国家行政組織法によらない、(2)公共企業体として国の経営する事業体とは区別されている、(3)国家賠償法の適用を受けない、(4)財産は、国有財産法の適用を受けない等。米側がこれに反論する論拠は、(1)設立は商法によらない、(2)予算は国会に提出され、会計検査院の検査に服する、(3)主管官庁の監督に服し、総裁は内閣等の任命にかかる等。
ちなみに、三公社が政府機関でない場合には、米軍の公務中の行為による損害は、地位協定第十八条5項(行政協定も実質的に同文)により、又、三公社が米軍人に与えた損害は、いずれの協定にも解決の規定なく、通常の司法手続により処理される。政府機関である際は、前者については地位協定第十八条2項により処理され(行政協定では第十八条2項により日本側が請求権放棄)、後者については、地位協定第十八条4項(行政協定にも実質的に同文あり)により米側が請求権放棄。
5 1項及び2項の適用上、船舶について「当事国が所有する」というときは、その国が裸用船した船舶、裸の条件で徴発した船舶、又は拿捕した船舶を含む。ただし、損失の危険又は責任が当該当事国以外の者によって負担される範囲については、この限りでない(3項)。右のただし書きのうち、「損失の危険」は、被害の危険負担を意味し、「責任」は、加害責任を意味する。「当該当事国以外の者」とは、実際上主として船主又は保険会社である。ただし書き全体の意味は、たとえば、日本政府が裸用船した船舶は、3項本文により日本政府所有の船舶とみなされ、これが被った損害又はその使用により相手国財産に与えた損害に対する請求権は、第十八条1項又は2項の適用を受けるが、この船舶が例えば米国船舶により破損せしめられた場合において船主又は保険会社が被害の危険を負担することになっていたときはその範囲において右船舶は「わが国が所有する」財産と認められず、また、逆に、右船舶が米国船に損害を与えた場合において船主又は保険会社が加害責任を負担することになっている範囲において「わが国が所有する」船舶と認められないこととなる。従って、例えば、右の被害の事例において、この裸用船された船舶が自衛隊が使用しているものであり、加害米国船が国有の軍用船である場合には第十八条1項(b)の適用があり、わが国は、右被害から生じた米国に対する請求権を放棄することになるが、若し船主が損害につき保険をかけていたとすると、保険会社は右船主に保険金を支払い、その金額につき日本政府に対し求償することとなるが、この場合右保険会社による危険負担の限度で第十八条1項の適用が排除され、その限度で日本政府は請求権を放棄しないことになるから、日本政府は保険会社に対する支払額につきさらに米国政府に支払いを請求することができることとなる。
三 軍人の公務中の死傷
1 日米各国は、自国の防衛隊の構成員がその公務の執行に従事している間に被った負傷又は死亡については、他方の国に対するすべての請求権を放棄する(4項)。行政協定第十八条1項は右規定に相当する規定であるが、右の如き死傷が他方の国の軍人又は文民たる職員によるものであるときとして加害者についても規定しているが、この点は、地位協定の右規定が他方の国に国家責任のある場合を対象としていることは明らかであり、従って、公務執行中の他方の国の軍人又は文民職員による事故であることについては何ら相違はない。尤も加害行為につき何ら規定がないので、人による事故のみでなく、営造物の設置管理上の瑕疵に基づく等当該他方の国乃至その防衛隊が法律上の責任を有する人的損害の場合にも適用があるものと解される。
2 又、被害者については、行政協定は、軍人のほか「文民たる政府職員」(中央政府の職員を指すと合同委員会で了解されていた。)が含まれていた。地位協定では、この文言がないので、かかる者(日本人の場合)の損害は、5項で処理されることとなる。
3 4項の規定の対象となる死傷者の請求権の処理の問題は、当該請求権を放棄した国の国内問題である。例えば、わが国の場合は、被害者たる自衛隊員(又は家族等)は、(国家公務員災害補償法、国家賠償法、民法等により)損害賠償の請求を日本政府に対して行なうこととなる。すなわち、「地位協定の実施に伴う民事特別法」の例えば第一条は、米軍人又は被用者がその職務を行なうについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員又は被用者がその職務を行なうについて違法に他人に損害を与えた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる旨規定するが、右の如き自衛隊員は、直接にはこの規定に基づき国に賠償を求めることができる訳である。(なお、民事特別法第二条は、米軍の営造物等の瑕疵にかかる損害についても第一条と同様の趣旨を規定している。)(注105)
(注105) この点の考え方については、衆・安保特議事録二八頁参照。なお、4項については、請求権の放棄には外交保護権の放棄のみならず被害者個人が相手国に提起しうべき請求権の放棄も含まれるかという問題がありうるが、右の如き被害者の公務中の行為は、被害者の国の行為であるので、そもそも被害者個人の相手国に対する請求権は生じないものと解される。
四 米軍の公務中の行為による私人の損害
1 公務執行中の米軍人・米軍の「被用者」の作為・不作為又は米軍が「法律上責任を有する」その他の作為・不作為は事故で、日本において「日本国政府以外の第三者」に損害を与えたものから生ずる請求権(契約による請求権及び6項又は7項の規定の適用を受ける請求権を除く。)は、日本が5項の(a)から(g)までの規定に従って処理する(5項頭書)。一定の行為につき米軍が「法律上責任を有する」か否かの決定は接受国の法令による(ナト協定につきLazareff 前掲書三〇三頁)。日本については、5項(a)の「日本国の自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令」によることとなる。公務執行中の米軍人等の作為等は、米軍が「法律上責任を有する」ものの典型的なものとして例示されているに過ぎない。右からすれば、米軍の「被用者」には、軍属、直接雇用の日本人労務者が含まれることは明らかであるが、これに限らず、法律上米軍との雇用関係がなくともこれと選任監督の関係があれば足りると解され、従って、通常の基本労務契約による間接労務者も含まれる。又、第十五条機関の使用人も右の「被用者」に含まれることが行政協定時代より了解されている(合同委員会の合意「民事裁判管轄権に関する事項」)。
2 更に、右規定のうち「日本国政府以外の第三者」については、米軍人・軍属及びその家族、国連軍地位協定にいう国連軍の軍人・軍属及びその家族は右の「第三者」に含まれないことが了解されている(合同委員会の右合意)。これらの者が含まれないのは、これらの者に対する損害は、米軍自身により処理されるべき性質のものであるとの考えによる。同様に、米軍・第十五条機関の直接・間接の日本人労務者の公務執行中の損害に関しては、これら労務者は、右の「第三者」には該当しないと解される。(注106)
(注106) 尤も、昭和四一年十二月の合同委員会の合意は、間接雇用の労務者は右の「第三者」に含まれる旨合意した。従ってかかる労務者は、労災の対象になる如き損害については、労災保障によるか本項によって保障を受けるかのいずれにもよりうることとなった。
又、米政府職員で米軍人・軍属でない者及び米政府自身の財産が損害を被った場合にも米軍内部の問題として処理されるべきものであるので、右の「第三者」には該当しないと解される。
3 契約による請求権の除外については、かかる請求権の処理は、別途なさるべきであるとの考えによる。かかる請求権としては、契約に基づく債務履行の請求権及び債務不履行に対する損害賠償の請求権が含まれる。請求者は、かかる請求権につき直接米軍を相手にわが国の裁判所に訴を提起することはできるが(10項但書)、実際には10項に定める合同委員会の調停により解決がはかられるものと考えられる。(注107)
(注107) 合同委員会の合意の「演習場の立入に関する事項」には、生計目的のために立入りを許可された私人がその立入りの結果射撃等により傷害を受けた場合、米側に故意重過失のない限り、米側は第十八条5項の責任を負わない旨の規定があるが、右の如き私人があらかじめ請求権放棄を行なっていない限り合同委員会の右の如き合意の妥当性には疑問がある。又、右の合意が、日本政府は右の私人に対し補償はするが、米側の分担分につき米側を免責としたものに過ぎないとするものであったとしても、合同委員会の合意によって日本政府の協定上の請求権を放棄しうるかについては疑問がある。
4 5項頭書の対象となる請求は、「日本国の自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令」に従って、提起し、審査し、かつ、解決し、又は裁判する(5項(a))。右の法令については、現在自衛隊の行動から生ずる請求権の処理に関する特別立法はないので、国家賠償法によることとなるが、同法第四条は、一定の場合には民法によることも定めるので民法の相当条文(具体的には第七一五条、第七一七条、第七一八条等)もこれに該当する。この点については、原子力損害賠償法が右の「日本国の法令」に該当するか(自衛隊は、原子力軍艦を保持していないから、原賠法は、適用されず、従って、米原子力軍艦による事故の救済は不十分なものとなるのではないか)との点が問題とされたことがある。
しかし、5項(a)の規定の趣旨は、米軍の行動が自衛隊の行動であったものとした場合に、その行動による損害の賠償の請求権に関する日本の法令を適用するということであって、理論的に自衛隊の行動に適用になれば足り、原子力軍艦を現に自衛隊が保持しているかどうかという問題とは関係がない。従って、原子力損害の賠償に関する法律もここでいう「日本国の法令」に該当する。(右法律は、国の保有する原子力施設についても適用があるので、自衛隊も国の機関として適用が排除されるものではない。)(注108)
(注108) 右の趣旨の政府答弁については、昭和三九年九月十七日、衆・外議事録十一頁参照。
5 次に、5項の規定は、米軍の故意又は過失による損害についてのみ適用があるのか又は米軍が地位協定によって与えられる権利の正当な行使(例えば施設・区域の適法な使用等)に伴なって生じた損害にも適用があるかという問題がある。この点について国家賠償法は、国又は公共団体が賠償責任を負うのは、公務員が故意又は過失により違法に他人に損害を与えた場合、又は公の営造物の設置若しくは管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合となっている(民事特別法第一条及び第二条が同様の規定をしているのは右を受けたものである。)ので、人による損害については、過失責任主義であり、営造物による損害については、特定の人の故意又は過失がなくとも右規定の適用があり、従って、この場合には無過失責任が認められることとなる。右によれば、米軍の通常の適法な行為から生ずる損害については、5項によっては(従って、第十八条によっては)解決できないこととなる。地位協定がかかる損害の処理を規定していないのは、かかる米軍の適法行為による損害(通常の飛行活動による騒音から生じる損害、その他通常の活動が農林漁業に与えるべき損害)は、米軍にその責を帰することはできず、他方、かかる損害は、日本が米軍の駐留を認めたことから当然期待されるものであるので、専ら日本内部で処理されるべきものであるとの考え方によるものである。「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律」(いわゆる「特損法」)及び「防衛施設周辺の整備等に関する法律」は、右の考え方に基づき制定されたものである。
なお、原賠法は、無過失責任主義をとっている(第三条)ので、米原子力軍艦の事故についてはこれにより補償が行なわれることとなる。(注109)
(注109) 米原潜の寄港に関する昭和三九年八月十七日付米側エード・メモワールは、「事故が発生した場合の補償については、地位協定の規定に従って措置するものとする。地位協定第十八条5項(a)の規定に基づいて、一九六一年六月十七日の日本国法律第一四七号(注:原賠法)は、同法が日本国の船舶に適用される限度において、通常の原子力潜水艦に係る原子力事故で、放射能汚染による疾病を含め負傷又は死亡をもたらしたものについての請求の処理に対してもひとしく適用される。」旨確認している。
6 日本は、5項(a)の対象となるいかなる請求をも解決できるものとし、合意され(和解を意味するものと解される。)、又は裁判により決定された額の支払を日本円で行なう(5項(b))。このような支払又は支払を認めない旨の確定裁判は、日米双方の国に対して拘束力を有する最終的のものとする(5項(c))日本が支払をした各請求は、その明細並びに5項(e)の(i)及び(ii)による分担案とともに、米側当局に通知する。二箇月以内に回答がなかった時は、その分担案は、受諾されたものとみなす(5項(d))。
5項の(a)から(d)まで及び2項の規定に従い請求を満たすために要した費用は、日米双方が次のとおり分担する(5項(e))。
- 米国のみが責任を有する場合には、裁定され、合意され、又は裁判により決定された額は、その25%を日本が、その75%を米国が分担する。
- 日米双方が責任を有する場合には、右の額は均等に分担される。損害が日米いずれかの防衛隊によって生じ、かつ、その損害をこれら防衛隊のいずれか一方又は双方の責任として特定できない場合は、右の額は均等に分担される。
- 比率に基づく分担案が受諾された各事件について日本が六箇月の期間内に支払った額の明細書は、支払要請書とともに、六箇月ごとに米側当局に送付する。その支払は、できる限りすみやかに日本円で行わなければならない。
7 右規定のうち、5項(e)の(i)の分担が頻繁に問題とされる。即ち、米国のみが責任を有する場合に、何故日本も25%を分担しなければならないのかという点であるが、この点についてほ、(イ)米軍は、日本の防衛に寄与するためわが国に駐留しているところ、米軍の公務中の行為による損害は、(個々の軍人等の故意・過失による場合であっても)安保条約の運用との関連で生じたものであること、(ロ)請求権の処理を接受国の法律に従って行なうことに鑑み、受入国としても一部を負担することが公平な額の決定に資することとなること(即ち、受入国も一部負担となれば、額の決定も合理的なものとなる)、(ハ)ナト諸国間においても同様に処理されていること等によって説明を行なうことができる。(注110)
(注110) 従来主として右の(イ)及び(ハ)によって説明している。衆・安保特、四月七日議事録五頁、昭和三九年四月十日、衆・内議事録五頁等参照。なお、5項(e)の規定は、2項の場合にも適用されるところ、日本のみに責任ある場合(例えば自衛隊員が公務執行中に米政府財産に損害を与えた場合)には、理論的には日本のみが100%負担することになるが、これは不公平ではないかとの問題が考えられるが、この点は、米政府の通常財産が日本で損害を受けるという実体はあまり考えられないので、実際上は問題ないとして説明することとなろう。
8 米軍の軍人又は披用者(日本の国籍のみを有する被用者を除く。)は、その公務の執行から生ずる事項については、日本においてその者に対して与えられた判決の執行手続に服さない(5項(f))。米軍人等の公務中の行為は、米軍の機関としての行為と観念されるから、地位協定上明文で認められる場合を除き日本の裁判管轄権に服するものではないと考えられる。行政協定は、かかる行為については、「日本国において訴を提起されることがない。」旨明らかにしていた。地位協定の右規定によれば、訴は提起されうるが強制執行には服さないということになるが、地位協定の当該規定はナト協定を踏襲したものであるところ、その意味は必ずしも明らかではない。しかし、いずれにしても、米軍人等の公務中の行為にかかる損害については、日本政府を被告として訴訟ができるのであるから、被害者としても米軍を相手とする訴訟には実質的利益はなく、被害者保護に欠けるということはない(参・安保特、六月十二日、議事録二九頁)。なお、「披用者」から日本人が除かれているのは、米軍の機関として行動した場合であっても日本人である限り日本の裁判手続に完全に服するということを念の為規定したものである。しかし、この場合も、損害は、日本政府によって保障されるのであるから、米軍の被用者たる日本人を相手とする訴訟には実質的利益はない。
五 海事損害
1「この項(5項)の規定は、(e)の規定が2に定める請求権に適用される範囲を除くほか、船舶の航行若しくは運用又は貨物の船積み、運送若しくは陸揚げから生じ、又はそれらに関連して生ずる請求権には適用しない。ただし、4の規定の適用を受けない死亡又は負傷に対する請求権については、この限りでない。」(5項(g))
この(g)の規定(ナト協定も同文)は、分りにくく立法技術的に拙劣であり批判に値するが、その意味は、要するに、米軍艦船によるわが国領海内の日本の私人の船舶等に対する物的な損害の問題は、5項によらず一般国際法(従ってこの場合は旗国法たる米国法)によって解決するが、人的な損害(死傷)は、被害者保護のため特に迅速な救済を必要とするのでこの場合も5項によって解決するということである。これを詳述すれば、次のとおり。
2「この項(5項)の規定は、(e)の規定が2に定める請求権に適用される範囲を除くほか」とは、右の如き米軍艦船による日本の私人の船舶に対する物的損害には5項の規定全体が適用されないが、2項で定める如き場合(例えば米軍艦船が日本の通常の国有財産たる公有船舶に物的損害を与えた場合)には、同じ物的海事損害ではあるが、5項の関係規定、即ちこの場合は分担率を定める5項( e)の規定が依然として適用されるという意味に過ぎない。(即ち、右の如き除外を規定しなければ、2項で定める如き海事損害には、5項(c)の分担率が適用されないかの如き印象を与えるのでこれを避けるべく念の為除外規定をおいたものである。)
3「ただし、4の規定の適用を受けない死亡又は負傷に対する請求権については、この限りでない。」とは、物的海事損害については、5項の規定によらないが、人的損害については5項によって解決するということ、尤も損害を被った者が公務執行中の自衛隊員である場合には、5項によらず4項によるということを意味するに過ぎない。
4 通常の物的海事損害にかかる請求権の処理がナト協定でも日米協定でも地位協定によっては処理されないこととされているのは、右の如き損害は額も巨大になり、専門的知識を必要とし、法律関係も複雑になりがちなので、通常の陸上損害とは別途の扱いをすることが妥当と認められたからである。(注111)
(注111) 衆・安保特、四月七日議事録五頁、参・安保特、六月十二日議事録二十頁。尤も、行政協定では、5項(g)の如き例外規定がなかったので、右の如き海事損害も5項(行政協定では第十八条3項に該当)で解決できる建前になっていた。この点は、地位協定の方が日本国民に不利になった(日本で裁判を受けられない)のではないかとの議論があるが、これに対しては、地位協定第十八条は、全体としてナト協定を踏襲したものであるところ、ナト協定にみられる如く海事請求権の除外は、西欧諸国を通じて一般的な考え方であったので、この点についてもナト協定の規定をそのまま採用したものであると説明する以外にない(昭和三六年五月二六日、衆・内議事録七頁)。
右の如く除外された請求権は、一般国際法によって処理されることとなる。即ち、国際法上一国の軍艦又は公船が他国の裁判権に服さないことは確立した原則であり、その与えた請求権の処理は、旗国法によることとなる。これら請求権を解決する米国国内法としては、米原潜の寄港に関する前述の米側エード・メモワールにおいても確認されているとおり、合衆国公船法、合衆国海事請求解決権限法及び合衆国外国請求法がある(注112)。損害を被った日本国民は、米国に対して右の法律に基づき直接賠償の請求を行うこととなるが、日本政府がその場合のあっせんその他必要な援助を与えることを目的とした「特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法」が制定されている。
(注112)右の米国法律の概要は次のとおり。
- (公船法)
- 公船法には、司法的救済及び行政的救済の二つの方法が定められている。司法的救済については、日本国民は、米国のいかなる地方裁判所に対しても米国を相手として訴を提起することができる。(米法典七八五条)しかして、公船法は、手続法であるから、訴の提起された米国裁判所は、適用のある法規及び法理全体を実体法として判断を下すこととなる。公船法に基づく行政的救済については、米国の司法長官は、同法に基づいて現に訴訟が行われている請求を仲裁し、示談し又は解決する権限を与えられており、金額上の制限は定められていない。(米法典七八六条)(この行政的仲裁は、通常の海事損害については過失主義を建前としているといわれる。)他方、この手続は、公船法に基づく訴訟手続が進行しているときにとられる点において他の二法による行政的救済と趣きを異にしている。
- (海事請求解決権限法)
- 同法(米法典七六二二条)によれば、海軍長官は、海軍艦船の生ぜしめた損害を百万ドルをこえない範囲内であれば同長官限りで行政的に解決しうることになっている。ただし、この額をこえうるものについても、議会より支出承認を得れば解決しうる。(この法律に基づく解決にあたっては、過失主義を建前としているといわれる。)
- (外国請求法)
- この法律は、友好関係の維持・促進の見地から請求の迅速な解決をねらったもので、その方法は、行政的救済である。すなわち、三軍の長官は、それぞれ、一万五千ドルの範囲内ならば行政的に請求を解決しうることになっており、また、これをこえる額については、議会の支出承認を得た上で同様の解決をなしうることになっている。(米法典二七三四条)(外国請求法の場合には、米国政府が損害の原因であることをもって足り、責任の立証を必要としない。)
なお、米原子力軍艦による原子力損害が人身に及ぶ場合は、原賠法第三条により無過失責任主義が適用されるが、米本国法で解決されるべき海事損害には無過失責任主義が適用されるのかという問題がある。この点については、公船法による司法的救済の場合に米国の裁判所が必ず無過失責任原則に基づく判決を下すものと断定すべき明確な根拠はない一方、原子力損害のように異常に大きな災害の場合にも、一般の船舶の衝突の場合と同様に過失責任のみを認めることになると考えるのは当をえないであろう。公船法及び海事請求解決権限法による行政的救済の場合には、過失責任を建前としているといわれているが、外国請求法の場合には、米国政府が損害の原因であることをもって足り、責任の立証を要しないとされているので無過失責任を認める立場と解される。
5「船舶の航行若しくは運用」のうち、運用(operation)とは、波止場に停泊しているときの船舶の状態をいうものと解される。「貨物の船積み、運送若しくは陸揚げ」のうち、運送(carriage)とは、船積みから陸揚げまでの間の運送であり、陸揚げ(discharge)とは、船舶からはしけを用いて陸揚げする場合、船―はしけ―陸の全過程を含むものと解される。従って、右の海事損害には、海上のみでなく港の施設等における事故も含まれることがある訳である。(昭和三六年十月五日、衆・内議事録六頁)。
なお、5項(g)の対象となる加害船舶は、協定第五条1項で定義される米軍用船舶であるとの答弁がある(昭和三六年五月二六日、衆・内議事録八頁)。
6 5項(g)により5項の規定を除外した海事損害とは、もともと船舶の衝突等海事法上の問題として処理されるものであったところ、日本では沿岸のノリ養殖、たこつぼ等ナト協定では本来予想されていない事情があり、これらの損傷まで5項の適用除外とすることは、5項(g)の立法趣旨に反し実際的ではないと考えられたので、これらのいわゆる小規模海事損害は5項により処理されるべき旨を確認した口上書が昭和三五年八月二二日に日米間で取り交わされている。即ち、右の口上書は、5項(g)の解釈を確認したものと説明されている。(注113)
(注113)本件口上書が地位協定署名(昭和三五年一月)後半年以上経て交わされたのは、協定署名後になって右の如き解釈の必要性が認識されたためである。
なお、本件口上書の理由、経緯、内容等かつて国会で非常に問題とされているが、審議の模様については、昭和三六年十月五日、衆・内議事録六頁、同十月三一日、参・内議事録三頁等参照。
なお、又、右口上書の内容は、昭和三七年十一月一日付けの官報に告示されているが、その告示の全文は次のとおりである。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十八条第五項(a)から(f)までの規定は、次の種類の損害に対する請求に適用されることが日本国政府及びアメリカ合衆国政府の間に確認された。
昭和三十七年十一月一日
防衛施設庁長官 林一夫
一 沿岸海域における海産動植物の増養殖に対する損害
二 漁網に対する損害
三 二十トン未満の船舶に対する損害で一件二千五百合衆国ドル以下の請求に係
るもの四 類似の損害で合同委員会を通じて合意されることのあるもの
なお、四の合同委員会を通じて合意されたものは、次のとおりである。(1)二十トン未満の船舶の船荷に対する損害で一件二千五百合衆国ドル以下の請求に係るもの。ただし、船舶とその船荷が同一の請求の所有に属するときは、当該船舶及び船荷に対する請求は、一件の請求として取り扱われるものとする。
(2)えびかご、たこつぼ、はえなわ、かきかご、えり・やな及びおだ並びに魚、えび、たこその他の海産動物を捕獲するために漁業者が使用する類似の措置に対する損害」
7 分担の問題については、小規模海事損害は、5項の適用があるので5項(c)により分担されることは明らかであるが、5項(g)により除外される海事損害の補償は、全額米国により負担されることとなる(昭和三六年五月二十六日、衆・内議事録五頁)。又、小規模損害の補償は、5項により処理されるのであるから、補償額には(米本国法による場合のような)限度はない(前記議事録六頁)。なお、右口上書の中には、「二十トン未満の船舶に対する損害で一件二千五百合衆国ドル以下の請求に係るもの」との文言があるが、この額については、第十八条2項(f)の場合と同様、為替相場に著しい変動があった場合には当然修正することになるとの政府答弁がある。(注114)
(注114)昭和三六年十月五日、衆・内議事録十頁。
六 軍人等の公務外の行為による損害
1 日本における不法の作為又は不作為で公務外のものから生ずる米軍の軍人又は被用者(日本国民である被用者又は通常日本に居住する被用者を除く。)に対する請求権は、6項の(a)か(d)までの規定により処理する(6項頭書)。米軍人等の公務外の行為は、いわば私人としての行為であるから、かかる行為から生ずる請求権の問題は、通常の司法手続きにより、解決することとすることも考えられるが、軍人等は、その職業からして移動性を持っており、通常の訴訟によっては被害救済の目的を実際は果たし難いので、地位協定は、右の如き請求権の処理についても特別の手続を定めたものである。なお、被用者とは、5項頭書にいう被用者と同様に考えられるが、日本国民又は通常日本に居住する者は除かれる。けだし、これらの者の公務外の行為から生ずる請求権の処理が通常の日本人の場合と異にする理由はまったくないからである。
2 日本側当局は、6項頭書の如き請求権に関するすべての事情(被害者の行動を含む。)を考慮して、公平かつ公正に請求を審査し、及び請求人に対する補償金を査定し、並びにその事件に関する報告書を作成する(6項(a))。その報告書は、米側当局に交付するものとし、米側当局は、遅滞なく、慰謝料の支払を申し出るかどうかを決定し、かつ、申し出る場合には、その額を決定する(6項(b))。右の場合、日本側の査定は、米側を法的に拘束するものではないが、米側の慰謝料の決定の(判読不明)慰謝料の申し出があった場合において、請求人がその請求を完全に満すものとしてこれを受諾したときは、米側当局は、自ら支払をしなければならず、かつ、その決定及び支払った額を日本側当局に通知する(6項(c))。6項の規定は、支払が完全に満すものとして行なわれたものでない限り、米軍人・被用者に対する訴えを受理する日本の裁判所の裁判権に影響を及ぼすものではない(6項(d))。従って、被害者は、当初から、又は呈示された慰謝料を不満として訴訟を提起できる訳である。この点は、9項(a)の規定からも明らかである。
3 米軍の車両の「許容されていない使用」から生ずる請求権は、米軍が「法律上責任を有する」場合を除くほか、6項の規定に従って処理される(7項)。「許容されていない使用」とは、使用の許可を与えられないで使用した場合及び公用以外の用途に使用した場合をいうものと解される。「法律上責任を有する」とは、不許可使用等をさせたことに米軍が責任を有する(監督不行届き等)場合であり、かかる場合には、5項によることは当然である。
4 第十八条を通じて米軍人等の一定の行為が公務中であるか否かは、重要な意味を持つことは明らかである。公務中であるか否かの決定について、行政協定第十八条4項は、「各当事者は、……その人員が公務の執行に従事していたかどうかを決定する第一次の権利を有する。」旨規定していた(国連軍協定第十八条4項も同じ)が、地位協定にはかかる規定はない。しかし、地位協定においてもこの点は、同様であろうと解される。かかる第一次的な決定に他方の側に異議がある場合には、8項の規定によることとなる。即ち、同項は、米軍人・被用者の不法の作為又は不作為が公務中のものであるか否か、又、米軍車両の使用が許容されていたものか否かについて紛争が生じた時は、その問題は、2項(b)の仲裁人に付託するものとし、この点に関する仲裁人の裁定は、最終的なものとする旨定めている。
七 民事裁判管轄権・調停
1 米国は、日本の裁判所の民事裁判権に関しては、5項(f)に定める範囲(即ち、公務中の行為)を除くほか、米軍人・被用者に対する裁判権免除を請求してはならない(9項(a))。施設・区域内に日本の法律に基づき強制執行を行うべき私有の動産(米軍が使用している動産を除く。)があるときは、米側当局は、日本の裁判所の要請に基づき、その財産を差し押さえて日本側当局に引き渡す(9項(b))。民事特別法第五条は、右の規定を受けて、右の如き動産については米側に引き渡しを要請すべき旨定めている。
2 日米双方の当局は、第十八条の規定に基づく請求の公平な審理及び処理のための証拠の入手について協力する(9項(c))。(なお、この点との関連で述べれば、米側は、米軍人等の公務執行中の行為につき米軍人等が証人等として日本の裁判所に出頭することを拒否するとの態度をとっている模様)
3 米軍による又は米軍のための資材、需品、備品、役務及び労務の調達に関する契約から生ずる紛争でその契約の当事者によって解決されないものは、調停のため合同委員会に付託することができる。ただし、この項の規定は、契約の当事者が有することのある民事の訴えを提起する権利を害するものではない(10項)この但書により右の如き紛争については、直接米軍を相手に訴訟を起こすことも可能であると解される。
八 その他
1 2項及び5項の規定は、「非戦斗行為」に伴って生じた請求権についてのみ適用する(12項)。ここにいう「戦斗行為」とは、安保条約第五条が発動され、これに対処するための「戦斗行為」を指すものと解され、この場合12項の意味は、安保条約第五条により米軍が現にわが国防衛義務を直接に履行している状況においては、米軍の公務中の行為から生じる右の如き民事上の請求権の解決方法も地位協定の一般規定によることは妥当でなく、かかる事態に応じた別途の処理に委ねることとするとの意であると考えられる(ちなみに、ナト協定においても、日米協定の第十八条2項及び5項と同様の規定が「戦争による損害」には適用ない旨定められている。第十五条1項。)。
「戦斗行為」の意味は、以上の通りであるから、これが事前協議の交換公文にいう安保条約第五条以外の場合の「戦斗作戦行動」と関係ないことは明らかである。(注115)
(注115)「戦斗行為」が安保条約第五条の場合を指すとの答弁については、昭和三六年十月三十一日、参・内議事録四頁。なお、この際、右の解釈については米側にも意見を聞いてみるとの答弁が行われている。ちなみに、朝鮮動乱の際米軍機の事故によって被害が発生し、米側は、作戦命令遂行中の事故であるから「戦斗行為」に該当するとして日本側の見解と対立したことがあり、このことからすれば、おそらく米側は、事前協議問題となる「戦斗作戦行動」を「戦斗行為」に含める考えであろう。
2 第十八条の規定は、この協定の効力発生前に生じた請求権には適用しない。それらの請求権は、行政協定第十八条の規定によって処理する(13項)。民事請求権の処理について行政協定と地位協定の規定には実質的に相違するところがあるのでこの規定には意味がある。行政協定時代の懸案(特に、三公社関係)が依然として未解決であることは前述したとおりである。
(その5に続く)
- その1 (速報385号)
- その2 (速報388号)
- その3 (速報392号)
- その4 (速報394号)