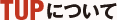DATE: 2006年2月14日(火) 午前10時36分
人狩りの恐怖のうちに過ごした一夜
戦火の中のバグダード、停電の合間をぬって書きつがれる若い女性 の日記『リバーベンド・ブログ』。イラクのふつうの人の暮らし、女 性としての思い・・・といっても、家宅捜索、爆撃、爆発、誘拐、検 問が日常、女性は外へ出ることもできず、職はなくガソリンの行列と 水汲みにあけあけくれる毎日。「イラクのアンネ」として世界中で読 まれています。すぐ傍らに、リバーベンドの笑い、怒り、涙、ため息 が感じられるようなこの日記、ぜひ読んでください。(この記事は、 TUPとリバーベンド・プロジェクトの連携によるものです)。 http://www.geocities.jp/riverbendblog/ (TUP/リバーベンド・プロジェクト:池田真里)
無法者どもの襲撃
数日前、私たちは従妹の誕生パーティーにおばの家に呼ばれた。Jは16に なったところで、おばは私たちを遅い昼食とケーキに招待してくれた。とても 小さな集まりだった…私を含む3人の従姉妹たち、私の両親、隣人でもあ るJの親友。昼食はとても美味しかった…おばはバグダードでも指折りの コックのひとりだろう。彼女はJの誕生日のために、イラク伝統料理で、私た ちの好物であるドルマ(コショウその他の香辛料で味付けした米・肉・タマネ ギをぶどうの葉で包んだもの)、味付けご飯、詰め物をした鶏、それにサラダ を準備してくれていた。ケーキは買ったものだったけど…それは人なつこ そうな顔をした魚の形をしていた。Jの父親は彼女が魚座ではなく水瓶座だっ たことを忘れて選んだのだった。私たちが間違いを指摘すると「2月生まれは みんな魚座だと思ったんだよ」と、彼は釈明した。
ローソクを吹き消す時、電気が消え、私たちは暗闇で彼女を囲んで立ち、ふ たつの違う言語で“ハッピーバースデイ"を歌った。彼女はギュッと目を閉じ て短いお願い事をし、それから一息でローソクの火を吹き消した。彼女は贈り 物を開け始めた…クマのパジャマ、男の子のバンドのCD、キラキラ飾り のついたセーター、赤やベージュの通学用バッグなどなど、典型的なティーン エイジャーへの贈り物だった。
でも彼女を一番喜ばせたのは、彼女の父親からのプレゼントだった。すべて を開け終わった後、彼は彼女に、小さいけれどかなり重い銀色の包みを手渡し た。彼女は急いでそれを開け、喜びにあえぎながら言った。「お父さん、ステ キだわ!」彼女は微笑みながら、それをガス灯にかざして見せびらかした。そ れは、コルク抜き、爪切り、栓抜きの全部揃ったスイス製のアーミーナイフだ った。
「お前が出歩く時、護身用にバッグに入れて持ち歩けるだろ」と彼は言った。 彼女は微笑んで、慎重に刃を抜きだして言った。「見て、刃が綺麗で、まるで 鏡みたい!」私たちはオーッとかワーと言って賞賛し、T(別の従姉妹)は、 スイス軍がピンク色のを作り始めたら、私も欲しいと言った。
私は16歳の誕生日に何を貰ったか思い出そうとしたけれど、それがどんな 種類のナイフでもなかったことは確かだわ。
午後8時までには、私の両親とJの隣人は帰宅し、私とTと24歳の従姉妹 はのこって、一晩一緒に過すことにした。Jの小さな弟を寝かしつけて気がつ いたら2時だった。彼は、分を超えてケーキとお菓子を食べ過ぎて、砂糖が彼 を2時間ほど暴れん坊にさせたのだ。
私たちは居間に集まったが、おばと彼女の夫であるSおじさんは眠っていた。 TとJと私は、ケーキを全部消化してしまうまでは寝ないと誓って、静かに喋 ったり、ラジオで歌番組を捜していた。Tはぼんやりと携帯電話をいじって、 友人にメールを送ろうとしていた。「あら、受信地域じゃありませんだって。 これホントに私の携帯?」Jと私はふたりして自分の携帯電話を確かめた。「 私のも使えないわ」Jが首を振りながら答えた。二人が私の方をみたので、私 の携帯にも受信可能とでていないと伝えた。Jは突然何かを思い出したように 「うぅ〜」と警戒するような声をたてた。「R、あなたの横にある電話をチェ ックしてみて?」私は横にある固定電話の受話器をあげ、息を殺して発信音を 待った。何も聞こえない。
「発信音が聞こえない…でも、今日早い時間にはあったわ、私、インター ネットにつなげてたもの」
Jは眉をひそめてラジオの音量を下げた。「前にもこういうことがあったわ」 と彼女は続けた。「この地区で掃討作戦があったとき。」突然シーンとなって 私たちは耳を澄ました。何も聞こえない。いくつかの通りの先の発電機の音と、 犬の遠吠えが聞こえる。でも、普段と何も変わりはない。
Tが突然背筋を伸ばして座りなおした「あれ聞こえる?」大きく目を見開い て彼女は尋ねた。最初、私には何も聞こえなかったけれど、そのうち自動車か 乗り物の音がゆっくり近づいてくるのがわかった。「私も聞こえるわ!」と、 立ち上がって窓に駆け寄りながらTに返した。暗闇の中に、あちこちの窓越し にみえるほの暗いランプの光の向こうには何も見えなかった。
「ここからじゃ何も見えない、きっと大通りだわ!」Jは跳び上がって彼女の 父親を揺り起こしに行った。「お父さん、お父さん、起きて。この地区に強制 捜査が入ってるんだと思うの」Jが両親の部屋に走りながら叫ぶのが聞こえた。 おじはすぐに起き、何時かねと尋ねながらスリッパとローブを探して歩き回る のが聞こえてきた。
その間に、車の音は大きくなってきた。私は2階の窓から近所がいくらか見 えるのを思い出した。Tと私は静かに階段を這いあがった。おじが5種類の鍵を キッチンのドアからはずしている音を聞いた。「おじさんは何をしてるのかし ら?」とTが尋ねた。「ドアには鍵をかけておくべきじゃないの?」私たちが 窓の外を見ると、いくつかの通りの先に照明がきらめいているのが見えた。何 軒かの家に視界を遮ぎられて彼らがどこから来たのかはっきりとはわからなか ったけれど、何か尋常でないことがこの一帯で起きていることは確かだった。 車の音はますます大きくなり、それと共に、ドアがガチャガチャ鳴り、時々照 明が閃いていた。
私たちがドタドタ階下に降りると、Jとおばが暗闇であわてふためいていた。 「どうすればいい?」そわそわと手をもみながらTが尋ねた。一度だけ私はお じの家で強制捜査に遭った経験があるが、あれは2003年のことだった。そ れにアメリカ人によるものだった。イラク人によるものと思われる強制捜査に 遭遇するのは、これが初めてだ。
おばは穏やかではあったが、憤慨しているのがわかった。「ろくでなしたち の、この地域での強制捜査は、この2ヵ月で3度めよ。私たちにはいつまでた っても平和も静寂もないわ。」寝室のドアの前に立って私はおばがベッドを整 えるのを見ていた。彼らは、スンニ派、シーア派、キリスト教徒の入り混じっ た隣人の中で暮らしている。このあたりは80年代後半に開けた比較的新しい 地域なのだ。ほとんどの隣人たちはお互いに長年見知っている。「私たちには あの人たちが何を求めているのかわからないわ…ラー イラーハ イッラ ッラー(神は唯一である)」(訳者注:どうしてよいかわからない時や助けを 求める時など、イスラーム教徒は無意識にアッラー(神)の名を唱えている)
彼らが準備するのを見ながら、私はぎこちなく立っていた。Jはすでに彼女 の部屋で着替えながら、私たちにも同じようにするように叫んだ。「あいつら が家に入ってきたとき、パジャマ着ていたくないでしょ。」
「どうして?やつらはカメラ班でも連れてくるわけ?」と、Tが弱々しく微笑 みながらユーモアを試みた。いいえ、とJがセーターを着ながらくぐもった声 で答えた。「前回やつらは、寒さの中、外で私たちを待たせたのよ」私はおじ のSが外にでて、道に面した門の大きな南京錠をはずしている音を聞き、「ど うして鍵を全部はずしてしまうの、J?」と闇の中で叫んだ。
「もし3秒以内に門を開けなければ、けだものたちがドアを壊すからよ。それ からやつらは庭と家中を荒らしまわるのよ…この前あいつらは3軒先のか わいそうなアブーHの家のドアをぶち破って、彼の肩を折ったの。」Jは完全 に着替えを済ませ、ジーンズとセーターの上にローブを羽織っていた。寒かっ た。
おばも着替えを済ませて、3歳のいとこBを運び下ろすために2階に行こう としていた。「騒ぎで目を覚まさせたり、暗闇で彼の周りにろくでなしたちが いるのを見つけさせたくないからね」
20分後、私たちはみな居間に集まっていた。石油ストーブと隅にある小さ なランプの光をのぞいて部屋は暗かった。私たちはみんな着替えて毛布にくる まり、神経質に待っていた。Tと私は床に座り、おばとおじは長椅子に座って、 Bは彼らの間で毛布にくるまれていた。Jは彼らの向かいの肘掛け椅子に座っ た。もう午前4時近くだ。
手入れ部隊が近づくにつれて、外の騒音はだんだん大きくなってきた。ドア をあけろと怒鳴ったり、ドアを銃でガンガンたたく音が時々聞こえてきた。
前回のおばの地区の強制捜査では、彼らの住む通りからだけでも4人の男性 を連れ去った。二人は20代初めの学生で、一人は法学部、そしてもう一人は 工学部の学生だった。そして、三人目は60代初めのお祖父さんだった。罪状 も、何の問題もなかった…彼らはただ外に出るように命令され、白い小型 トラックに乗せられ、他の地区からの男の人たちのグループと一緒に連れ去ら れた。家族はそれ以来彼らの消息を聞くことはなく、彼らが死体で発見される ことを予測して、日に何度も死体保管所を訪れている。
「何も問題は起こらないわ」おばは私たちひとりひとりを見ながら、厳しい表 情で唇をかみ締めて言った。「あなたたちが余計なことを言わなければ、入っ てきて、見回すだけで行ってしまうでしょう」彼女はSおじさんに目をとめて いた。彼は黙っていた。彼は煙草に火をつけ、深く吸いこんだ。Jが言うには、 彼は10年も煙草をやめていたのに、2ヵ月前にまた吸い始めたということだ った。「身分証明書は持ってる?」要求されるはずなので彼に尋ねた。彼は答 えなかったけれど、静かに頷いた。
私たちは待った、ただ待った…私はうとうとし始め、夢には兵士と車と 袋をかぶせられた男たちが散りばめられた。「やつらはもう来るわ」というT の声で目が覚めた。3時間ほども眠ったかしらともうろうとした頭をあげた。 腕時計にちらっと目をやると、まだ午前5時になっていなかった。「まだ来 ない?」と私は尋ねた。
おじは台所を歩き回っていた。私は窓の前で止まったり、行ったりきたりす る彼のスリッパの音を聞いた。おばはまだ寝椅子の上でBを腕に抱いて優しく 揺らし、祈りを唱えながら座っていた。Jは最後のチェックをし、貴重品を隠 し、ハンドバッグを居間に集めて、「前回の手入れの時、やつらはお父さんの 携帯電話を持って行ったわ。あなた達は携帯電話を身につけていてね」と言っ た。
心臓が耳の中で鼓動を打っているような気がした。そして石油ストーブの近 くに行き、指やつま先にとりついて離れないような寒さを何とかしようと試み た。Tは毛布にくるまって震えていた。私は彼女にヒーターの方にくるように 手招いたが、彼女は首を横に振って「わ…わたし……さ、さ、寒 くないわ」と答えた。
彼らは10分後にやって来た。大きなガラガラいう音を庭の門で鳴らし「門 を開けろ」と怒鳴り散らしながら。外にいるおじが大声で「開けます、開けま す」というのが聞こえた。次の瞬間には、彼らは家の中にいた。突然家は、ど かどかと足を踏み鳴らして部屋々々に押し入って怒鳴り散らす見知らぬ男たち でいっぱいになった。もう滅茶苦茶だった。庭に軍用懐中電灯が見えたかと思 うと、光が玄関から入ってきた。おじが外で、彼の妻と「子どもたち」が家の 中にいるだけだと、彼らに大きな声で言っているのが聞こえた。何を捜してい るのか?何か不法行為があったのか?と彼は尋ねた。
突然、彼らのうちの二人が居間に入ってきた。私たちは全員おばのそばのソ ファに座っていた。いとこのBは目覚めていて、恐怖に目を見開いていた。彼 らは大きな軍用懐中電灯を持っていた。彼らのひとりが私たちにカラシニコフ 銃を向けて「お前らの他に誰かここにいるか?」と、おばに吠えた。「いいえ、 私たちのほかには外であなたたちと一緒にいる夫だけです、家を調べればいい わ」Tが、どぎつく輝く軍用懐中電灯の光を遮ろうと手をあげたが、男の一人 が怒鳴りつけたので、彼女の手は弱々しくひざの上におちた。まぶしかったの で目を細めて窺ったところ、彼らはマスクをつけ、目と口だけを出しているこ とがわかった。私は従姉妹たちをちらりと見て、Tがほとんど息をしていない のに気付いた。Jは凍りついたように座っていて、その目は何も見ていないよ うだった。私は彼女がセーターを後ろ前に着ているのにぼんやりと気づいた。
彼らのひとりは私達にカラシニコフ銃を向けて立っていて、他のひとりは戸 棚を開け、中をチェックした。私たちは黙っていた。唯一聞こえるのは、おば の震えた囁くような祈りの声と、恐怖に目を見開いた小さなBが指をしゃぶる 音。残りの兵士たちが家を歩き回り、タンスやドアや戸棚を開ける音が聞こえ た。
外にいるSおじさんの声を聞きたかったのだけれど、耳障りな兵士の声が聞 こえてくるだけだった。居間に座っている時が永遠に続くように思われた。ど こを見ていれば良いのかもわからなかった。武器を持った男を見つめたらまず いとわかっているのに、その男のほうについ目がいってしまう。私は足元の新 聞に目をやり、逆さから見出しを読もうとしてみた。Jを再びちらりと見ると、 彼女の心臓は激しく鼓動を打っていて、私の母が今日贈ったばかりの銀のペン ダントが、彼女の鼓動にあわせて、胸の上でドキンドキン波打っていた。
突然誰かが外から大声で何か叫び、それは終わった。侵入してきたのとほぼ 同じ速さで彼らは立ち去った。バタンバタンとドアが閉まり、部屋はだんだん 暗くなっていった。私たちは再び暗闇にとり残され、ソファから動く気力もな く、門の前に2人の男を歩哨に残して男たちが立ち去っていく音を座ったまま 聞いていた。
「お父さんはどこ?」Jの言葉で、私たちは彼のスリッパの音が道から聞こえ てくるまで、しばらくの間パニックに陥った。「お父さん連れて行かれたの?」 彼女の声はうわずっていた。やっと家に戻ってきたおじは憔悴しきっていた。 彼の顔は暗い家の中で見てもひどく青ざめているのがはっきり判った。おばは 居間に座って静かにすすり泣いていた。Tが彼女を慰めていた。「どの家にも 神聖な場所なんてもうないわ…眠ることもできないし、住んでいられない わ。家の中が安全でないっていうんなら、いったいどこに安全な場所があるっ ていうの?けだもの!ろくでなし!」
数時間後、私たちは2軒先の隣人が亡くなったことを知った。アブーサーリ フは、70代の男性で、イラク人の傭兵が襲撃した時、心臓発作を起こしたの だった。彼の孫はすぐに彼を病院に連れて行くことができなかった。なぜなら 兵士たちは捜査がすむまで拘束していたからだ。彼の孫が後で言ったところに よれば、その日イラク軍が手入れを行っている間、アメリカ軍がこの地区を包 囲して彼らを守っていた。これはアメリカ軍との共同作戦だったのだ。
彼らは、おばの地区だけからでも少なくとも12人の、19歳から40歳ま での男たちを連行した。後ろの通りには50歳以下の男のいる家などひとつも ない。弁護士、技術者、学生、普通の労働者達はみんな新生イラクの「治安部 隊」によって連行されてしまった。彼らに共通する唯一の事実は、彼らがスン ニ派の家族であることだ(確かではない2つの場合を除いては)
私たちは衣類を洋服ダンスに戻したり、なくなったものの検査(腕時計、真 鍮のペーパーナイフ、それからウォークマン)をしたり、絨毯の泥と土を掃除 するのに一日費やした。おばは狂ったように「汚い、汚い、汚い…」と言 いながら、何もかも掃除し消毒していた。Jは、二度と彼女の誕生日を祝わな いと誓った。
ほんの1ヵ月前、おもしろいことがあった。私たちはどこかのアラビヤ衛星 テレビの番組――たぶんアラビーヤだわ、でコマーシャルを見ていた…。 そこではイラク治安部隊の広告をしていて、テロリストの襲撃があった場合、 イラク人が通報することになっている電話番号をリストアップしていた。… 強盗や誘拐からあなたを守る警察ならこの番号へ…テロリストからあなたを 守る国家警備隊や特殊部隊へはこちらの番号へ…って、でもね…
新生イラクの治安部隊から守ってもらうためには、一体誰を呼べばいいわけ?
午前12時43分 リバー
(翻訳/リバーベンド・プロジェクト:ヤスミン植月千春)
—-