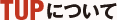FROM: hagitani ryo
DATE: 2006年5月7日(日) 午後7時58分
☆文明の利器の伝播と普及、あるいは因果の法則にも似て……★
有益性と簡便性のゆえに、またたく間に広く普及する発明品を、現代文明の
“利器”と定義するならば、イラクをはじめ、バリやジャカルタ、オクラホ
マ、紛争や対立のあるところで広く使われている自動車爆弾もそのひとつに
あたるでしょう。それにしても、これは米軍ご自慢のスマート爆弾の性格と
さほど変わらず、生身の人間の殺傷を狙い、巻き添え被害をいとわない、な
んというおぞましい大量殺人兵器なのでしょう。本稿は、1920年の
ウォール街における荷馬車爆弾の炸裂を紀元とする歴史を振り返るものです
が、二部構成になっていて、当パート1は、1980年代、レバノンにおけ
るヒズボラによる対米仏闘争までの自動車爆弾の連鎖をつづっています。
余談ですが、本稿の筆者、マイク・デイヴィスの著作『感染爆発――鳥イ
ンフルエンザの脅威』が、5月7日付け朝日新聞書評欄にて紹介されていま
す。筆者は、現代文明がもつ構造的な危険性を常に見つめているようです。
井上
凡例: (原注)[訳注]〈ルビ〉《リンク》
―――――――――――――――――――――
トムグラム:
マイク・デイヴィス、自動車爆弾の歴史を語る
[トム・エンゲルハートによるまえがき]
ニューヨーク・タイムズのデーヴィッド・ブルックスが、3月23日付け論
説記事《*「傷つき、地に落ちた構想」》に、「ナショナル・レヴュー誌の
リチャード・ロウリーが『勝手にしやがれ』主義タカ派と名づけた勢力の台
頭」について書いた。ブルックスは、こういうタカ派を「自動車爆弾や漫画
騒動を目にして、はたしてイスラムはほんとうに平和の宗教なのかといぶか
る」類の保守派と性格づけた。歴史の効用のひとつは、この考えを、入り口
のところで点検しなければならないことにある。マイク・デイヴィスが言う
「ありふれた都市テロの実用兵器」のせいで、イスラムが「平和の宗教」と
考えられないとしたら、イスラム教徒ジハード戦士たちは、少なくとも、ユ
ダヤ、キリスト教徒、ヒンドゥ教徒、アナーキスト、フランス人入植者、マ
フィア、アイルランド共和国軍構成員、CIA工作員、その他、あまり平和
とは言えない物騒な自動車爆弾魔たちの列に加わっていることになる。
http://heartsoulandhumor.blogspot.com/2006/03/what-do-republicans-believe.html
そこで、トム・ディスパッチと連れだって、私たちの世界の現代史の流れへ
と、とてもユニークで、予想もつかない船旅に乗り出すことを検討なさって
はいかがだろうか。自動車爆弾は、いかにも現代に特有の兵器に思えるの
で、80年にわたる曲解にみちた歴史をもつと知る人がいないほどである。
だが、最近の仕事に、鳥インフルエンザに関する比類のない重要な著作、
“Avian flu, The Monster at Our Door”《1》、そして、世界のかなりの
部分が急速に都市化し、しかも同時に非産業化している状況に関する驚くべ
き分析の書“Planet of Slums”《2》があるマイク・デイヴィスは、ほと
んどいつも意表をつく仕事を見せてくれる。今週、トム・ディスパッチは、
私たちの時代の実に恐ろしい現象のひとつに数えられる自動車爆弾の歴史を
俯瞰し、闇に包まれた現代史の隅ずみに明るい光をあてるデイヴィスの記事
を二部構成でお届けする。いつの日か、この記事は増補されて、小冊子にま
とめられる予定があり、デイヴィスは、過去半世紀間の自動車爆弾作戦につ
いて、本稿に取り上げられたものの他にもエピソードはないか、情報を求め
ている。トム
1.『感染爆発――鳥インフルエンザの脅威』柴田裕之・斉藤隆央訳、紀伊
国屋書店
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9980525479
2.仮題『スラムの惑星』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/1844670228
貧者の空軍力――
自動車爆弾の歴史(パート1)
――マイク・デイヴィス
ブダの荷馬車(1920年)
「貴様らは俺たちに慈悲心などはてんで見せなかった! 俺たちも同じ目に
あわせてやる。貴様らを吹っ飛ばす!」
――アナーキストからの攻撃予告(1919年)
1920年9月の暖かいある日、マリオ・ブダという名のイタリア人アナー
キストが、何か月か前に、ふたりの同志たち、サッコとヴァンゼッティが逮
捕[*]されたことで、復讐を胸に秘め、ウォール街ブロード通りの角に近
い、J・P・モルガン社の真向かいに荷馬車を停めた。ブダはそしらぬ顔で
馬車を降り、人知れず、昼休み時の雑踏に消えた。数ブロック先で、仰天顔
の郵便夫が「政治囚に自由を! さもなくば、貴様らに確実な死を!」と脅
し文句が踊る不審なビラを見つけていた。名乗りに「アメリカのアナーキス
ト戦士たち」とあった。近くのトリニティ教会の鐘が正午の時報を打ちはじ
めた。鐘が鳴りおわったとたん――ダイナマイトと鉄屑を詰め込んだ――馬
車が爆発し、榴散弾〈りゅうさんだん〉の火の玉と化した。
[1920年、現金輸送車を襲った強盗殺人の嫌疑で逮捕されたイタリア系
移民のアナーキストたち、ニコラ=サッコとバルトロメオ=ヴァンゼッティ
が、証拠不十分のまま、国内外からの抗議にもかかわらず、27年に処刑さ
れる]
「馬と荷車はバラバラになって吹き飛んだ」と、米国アナーキズムに関する
名高い歴史研究者であり、この実話を掘り起こしたポール・アヴリックは書
いている。「オフィスの窓からガラス片が雨のように降りそそぎ、路面から
遠く12階上層に張られた日除けが炎に包まれた。巨大な塵の雲が一帯を包
みこみ、人びとは命からがら逃げまどった。モルガンの社内では、警備部の
トーマス・ジョイスが、自分のデスクもろともに漆喰〈しっくい〉と壁材の
瓦礫の下敷きになって死亡した。外の街路には、たくさんの死体が散らばっ
ていた」
40人の死者、200人を超える負傷者のなかに、目当てのJ・P・モルガ
ンはいなかった――稀代の搾取王はスコットランドに構える狩猟小屋に出か
けて、留守だった――と知ったとき、ブダはガッカリしたはずだ。それにし
ても、いくらかの盗品ダイナマイト、一山の屑鉄、それに老いぼれ馬をそろ
えた貧しい移民が、首尾よくアメリカ資本主義の牙城に未曾有の恐怖を持ち
こんだのである。
彼のウォール街爆弾は、アナーキストたちが半世紀にわたり夢見てきたダイ
ナマイト製の復讐天使の極致であり、チャールス・バベッジ[1792-1871。
イギリスの数学者]のディファレンス・エンジン[コンピュータの原型]に
も比すべき、時代の想像力をはるかに超えた発明でもあった。残忍な戦略爆
撃がありふれたものになり、空軍が貧民街の迷宮くまなく反乱勢力を追いつ
める光景が日常的になってはじめて、ブダの手になる「地獄の仕掛け」の真
に過激な将来性の全体像が理解されうることだろう。
ブダの荷馬車は、本質として、自動車爆弾の原型――都市環境のおよそどこ
でも匿名性に隠れたまま、高価値標的に間違いなく届く範囲に大量の高性能
爆薬を運ぶ、人目を引かない車両の最初の使用例――だった。筆者に断定で
きたかぎりでは、1947年1月12日、パレスチナの街ハイファで、ス
ターン団がトラックに満載した爆薬を英国警察署に送りこみ、死者4名、負
傷者140人を出したときまで、同様な事件は再発していない。スターン団
(右翼シオニスト[ユダヤ主義者]民兵組織・イルグーン団を割って出たア
ブラハム・スターンが率いる分派)は、その後まもなく、パレスチナ人殺害
のためにもトラックや自動車の爆弾を使うようになり、この独創的な蛮行
は、ただちにパレスチナ民族主義の側に立って戦う英国軍脱走兵たちによる
報復を呼んだ。
それを契機に、車両爆弾は――サイゴン(1952年)、アルジェ(62
年)、パレルモ(63年)で世に聞こえる殺戮〈さつりく〉を招くなど――
散発的に使われるようになったが、地獄の門がほんとうに開いたのは、19
72年、暫定アイルランド共和国軍(IRA)が、言い伝えによれば、たま
たま間に合わせに、最初の硝酸アンモニウム燃料油(ANFO)自動車爆弾
を造ったときだった。この新世代爆弾の製造に必要なのは、ありふれた工業
資材と化学肥料だけであり、コストは安上がり、しかも爆発力は驚くほど効
き目があった。これが都市テロを職人技から工業レベルに発展させ、鉄筋コ
ンクリート高層ビルや住宅地の完全破壊だけでなく、都市中心部全域に対す
る持続的な電撃作戦を可能にした。
つまり、自動車爆弾は、突如として、都市全域の住民を恐怖に落とすだけで
なく、条件によっては、都市の重要拠点や中枢に壊滅的打撃を与える能力に
おいて空軍力に匹敵する準戦略兵器になった。じっさい、1983年のベイ
ルートで、米大使館や海兵隊の営舎を壊滅させた自爆トラック攻撃は――少
なくとも地政学的な意味で――戦闘爆撃機隊と米第七艦隊との連合作戦の火
力をしのぎ、レーガン政権にレバノンからの撤退を余儀なくさせている。
1980年代のレバノンにおいて、ヒズボラが、米国、フランス、イスラエ
ルの先進的な軍事テクノロジーに対抗するために採用した、容赦のない、目
を見張るような自動車爆弾戦術は、十指にあまる他の集団を勇気づけ、反乱
とジハード[聖戦]をそれぞれの出身国の都市圏に持ち帰らせることになっ
た。新世代の自動車爆弾戦士たちの一部は、1980年代中期、カブールを
占領していたロシア人たちを脅かす目的で、ムジャヒディンを訓練するため
に、サウジアラビアが資金を出し、CIAとパキスタン諜報機関(ISI)
とが設定したテロ訓練校の出身だった。1992年から98年の間に、13
の都市で16件の大規模な車両爆弾攻撃が発生し、死者が1050人、負傷
者は1万2000人近くに達した。地政学的な見地にかぎれば、もっと重大
なことに、IRA[アイルランド共和国軍]とガマア・アル・イスラミア
[イスラム原理主義運動の一派]とが、世界経済を左右する二大中心地――
ロンドンのシティ(1992、93,96年)とマンハッタン南端部(93
年)――に数十億ドル相当の被害を与え、世界の再保険業界に再編を余儀な
くさせた。
あのウォール街の最初の虐殺から85年、新しい千年紀に入って、自動車爆
弾は、iPod[マッキントッシュ社の携帯音楽機器]やHIV-AIDS
[ウィルス感染による後天性免疫不全症候群]とほとんど変わらない、ごく
ありふれたものとして世界に蔓延し、ボゴタ[コロンビアの首都]からバリ
[インドネシア]にいたる、あちこちの都市の路面に爆発孔〈クレーター〉
を残している。自爆トラックは、かつてヒズボラの専売特許的な兵器だった
が、スリランカ、チェチェン/ロシア、トルコ、エジプト、クウェート、イ
ンドネシアへと採用地が拡大した。都市テロ攻撃の統計グラフのどれを見て
も、自動車爆弾攻撃を表す曲線は、指数関数的にと言っていいほどに急激な
上昇を見せている。米軍占領下のイラクは、もちろん容赦のない地獄であ
り、2003年7月から05年6月までの2年間の車両爆弾による――主と
して民間人からなる――死傷者の数は9000人を超えている。その後、自
動車爆弾攻撃の発生件数は激増し、2005年秋には月あたり140件に達
し、バグダードでは06年の元日だけで13件になった。路傍爆弾、つまり
IED[即製爆破装置]が米軍装甲車両に対する最高に効果的な仕掛けであ
るとすれば、自動車爆弾は、モスクの前やマーケットでシーア派民間人を殺
傷し、破滅的な宗派間戦争を煽るための格好の武器になっている。
一般車両と見分けのつかない兵器による包囲状況にあって、行政や金融の機
構は“鋼鉄環状防衛線”や“グリーン・ゾーン”の内部に引きこもっている
が、ますます悪化する自動車爆弾の問題は手に負えないようだ。盗まれた
核、サリン・ガス、炭疽菌は「若干の危惧」かもしれないが、自動車爆弾
は、ありふれた都市テロのための実用兵器なのだ。ところで、その系譜を論
じる前に、ブダの荷馬車を、これほどまでに恐ろしく、また疑いなく恒久的
な都市治安の破壊手段の起源に仕立てた特性を概観しておくことは有益であ
ろう――
1.車両爆弾は、驚くべき威力と破壊効率を備えた隠密兵器である。トラッ
クやバン、さらにはSUV[スポーツ汎用車]ですら、在来型1000ポン
ド爆弾の数発分に相当する爆薬を主標的の玄関先まで運ぶことが容易にでき
る。しかも発明の才に富む爆弾作りがあれこれ不断にいじくるおかげで、そ
の破壊力はいまだに進化途上にある。私たちは、致死爆風範囲が200ヤー
ド[180メートル]におよぶトレーラー爆弾や、マンハッタン中枢を幾世
代にわたり放射能汚染するのにじゅうぶんな量の核廃棄物でコーティングさ
れた“汚い爆弾”のじっさいの恐怖をまだ体験していない。
2.車両爆弾は桁外れに安価であり、盗難車と400ドル相当の肥料、それ
に闇市場の電子機器が揃えば、40人や50人の人たちが殺される。199
3年の世界貿易センター・ビル攻撃の首謀者、ラムジ・ユーセフは、一番高
くついた経費は長距離電話の料金だったと自慢げに供述している。爆発物そ
のもの(尿素500キログラム)には3615ドルかかり、それにプラスし
て、304cm長のライダー・バンのレンタル料が日額59ドルだった。そ
れにひきかえ、海外におけるテロ攻撃に対するアメリカの古典的な反撃手段
になっている巡航ミサイルは、一発のお買い上げ、一金110万ドル也。
3.自動車爆弾攻撃を準備するのは、作戦として簡単である。ティモシー・
マクベイとテリー・ニコルスは政府や闇組織による秘密の支援を受けていな
かったと信じるのを、いまだに拒んでいる向きもあるが、かの有名な電話
ボックスにいた二人の男――警備員と農業者――は、銃器展示サイトをた
どって入手した説明書や情報によって、首尾よく計画をまとめ、恐怖のオク
ラホマ・シティ連邦政府ビル爆破を決行したのだ。
4.“最高照準精度”の空襲爆弾でさえも同じだが、自動車爆弾は本質的に
無差別攻撃手段であり、“付随的[または、巻き添え]被害”はどうしても
避けられない。攻撃の論理が、“緊張戦略”を遂行するために、または単に
社会を混乱させるために、無辜の民を殺傷し、最大範囲にまでパニックを広
げることであれば、自動車爆弾は理想的である。だが、IRAとスペインの
ETA[Euskadi ta Askatasuna=バスクの分離独立をめざす運動]とがそ
れぞれ独自に悟ったように、自動車爆弾は、大義の道徳的信頼性を破壊し、
大衆的支持基盤を損なう点においても同じように効率的である。自動車爆弾
は本質的のファシストの兵器なのだ。
5.自動車爆弾は匿名性に優れ、最少限の司法証拠しか遺さない。ブダは平
穏無事にイタリアの故郷に帰り、ウィリアム・バーンズやJ・エドガー・
フーヴァー、そして捜査局(後にFBIと改称)が、10年にわたり次から
次へと紛いものの手掛かりを追いかけたあげく、笑いものになるにまかせ
た。ブダの後継者たちの大半も、身元割れや逮捕を免れている。ついでに言
えば、CIAやイスラエルのモサド、シリアのGSD、イランのパスダラ
ン、パキスタンのISIなど――皆がみな、このような装置を用いて言語を
絶する虐殺行為に手を染めながら――みずからの仕業であることを隠蔽した
いと願っている連中にとって、自動車爆弾は、匿名性のゆえに、おおいに推
奨される手段である。
前触れの爆発音(1948年〜63年)
「赤の時限爆弾、サイゴン中心部で炸裂」
――ニューヨーク・タイムズの見出し(1952年1月10日付け)
スターン団の構成員たちは暴力を熱心に学ぶ輩であり、1917年以前のロ
シア社会主義革命党、マケドニアのIMRO、イタリアの黒シャツ党といっ
たテロリストの伝統に足を踏み入れ、ムッソリーニの崇拝者を公言するユダ
ヤ人だった。パレスチナにおけるシオニスト運動の一番過激な極右――ハガ
ナ[英軍と共闘したユダヤ地下組織]に対立する“ファシスト”、英国に刃
向かう“テロリスト”――として、彼らは道徳的・戦術的に外交的配慮や国
際世論に縛られていなかった。彼らは、作戦行動の独創性と攻撃の意外性の
ゆえに、熱烈な、また当然の評判を得た。シオニスト主流派と英国の労働党
政府との間で結ばれる和解をすべて阻止するための作戦行動の一環として、
1947年1月12日、彼らはハイファの中央警察署の内部で強力なトラッ
ク爆弾を炸裂させ、144人の死傷者を出した。3か月後、テル・アヴィヴ
でこの戦術を再現し、盗んだ郵便トラックにダイナマイトを詰めて、サロナ
警察営舎を爆破した(死者5人)。
1947年12月、パレスチナ分割を定めた国連決議につづいて、ハイファ
からガザまで、ユダヤ人社会とアラブ人社会の間で全面戦争が勃発した。聖
書時代のイスラエルの復興に値しないものはすべて拒否していたスターン団
は、大規模テロ兵器としてトラック爆弾を初登場させた。48年1月4日、
アラブ人の服を着たふたりの男たちが、オレンジ運搬を偽装したトラックで
ヤッファ[50年にテル・アヴィヴに併合]の中心街に乗りいれ、パレスチ
ナの地方政府と貧しい子どもたちの給食施設が入居しているニューセライ・
ビルの間近に停車した。彼らは最寄りのカフェに入り、涼しい顔でコーヒー
をすすって時間を潰し、爆発する瞬間の数分前に現場を離れた。
「その時、轟きわたる爆発が市街を揺さぶった」と、アダム・レボウは自著
のヤッファ史に書く。「割れたガラスや砕けた石組みは時計塔広場を越えて
吹き飛んだ。ニューセライの中壁や外壁は崩れて、瓦礫の堆積と捩れた梁
〈はり〉が残された。一瞬の静寂のあと、叫び声が聞こえはじめた。26人
が殺され、数百人が負傷した。大半は民間人であり、慈善食堂で食事中の子
どもたちも大勢いた。爆弾は、他のビルに移っていたパレスチナ人の地元指
導者を仕留め損なったが、この残虐行為が、住民に恐怖を叩きこみ、最終的
に逃げ出すきっかけを作ったという点では大成功をおさめた」
これがパレスチナ人たちを挑発し、同じ手口の無慈悲な報復に走らせた。ア
ラブ高等委員会(the Arab High Committee)は独自の秘密兵器――金髪の
英軍脱走兵の集団――を抱えていた。元警察部隊兵長のエディ・ブラウン
は、兄弟をイルグーン団に殺害されている脱走兵であるが、ヤッファ爆弾事
件の9日後、彼が率いる同輩数名が郵便配達トラックを奪取し、それに火薬
を積んで、ハイファのユダヤ人居住区の中心部で爆発させ、50人の人びと
を負傷させた。その2週間後、ブラウンは盗んだ車のハンドルを握り、警察
の制服を着用したパレスチナ人が運転する5トン・トラックを先導して、英
軍やハガナが設けた検問所をなんなく通過し、エルサレム新市街に入った。
運転係はトラックをパレスチナ・ポスト社の前に停め、導火線に点火したう
えで、ブラウンの車に乗り換えて離脱した。同紙の本社ビルは壊滅し、死者
1名、負傷者20名の惨事になった。
事件を記録したアブデル・カデル・エル・フセイニによれば、アラブ高等委
員会の軍事部門の指導者は――はからずもスターン団に促された――これら
の作戦の首尾に意を強くして、6名の英国人脱走兵たちに実行させる次の野
心的な作戦を承認した。「今回は、3台のトラックが使われ、盗んだ英軍の
装甲車が随伴し、その銃座には、警察の制服を着た若い金髪の男が立ってい
た」 この時も、車列は検問所を無事に通過して、ベンヤフーダ街のアトラ
ンティック・ホテルに乗りつけた。団員たちは、応対に出た詮索好きな夜警
を殺害し、3台のトラックの爆破装置を起動したあと、装甲車に乗り込んで
逃亡した。爆発は巨大そのものであり、それに比例して被害も凄まじく、死
者は46人、負傷者は130人に達した。
この種の攻撃を可能にする窓―― 一方の側から他方へ移動する機会――
は、パレスチナ人たちとユダヤ人たちとが総力戦に備えはじめるにつれ、時
をおかずに閉じようとしていたが、最後の攻撃は、暗殺の道具としての自動
車爆弾の輝かしい未来を告げるものになった。3月11日、星条旗を掲げ、
いつもの運転手がハンドルを握ったアメリカ総領事の公用リムジンが、厳重
に警備されたユダヤ政府庁舎の中庭への乗り入れを許可された。運転してい
た、アブ・ユセフという名のキリスト教徒のパレスチナ人は、シオニストの
指導者、ダヴィド・ベン・グリオンの殺害を望んでいたが、リムジンは爆発
の直前に場所を移されてしまっていた。それでも、ユダヤ財団基金の職員1
3名が死亡し、40人の人びとが負傷した。
アラブ人たちとユダヤ人たちの間の、短期間に終わったものの、熾烈だっ
た、この自動車爆弾の応酬は、両者間の闘争の集団的な記憶に残ることに
なったが、1981年になって、イスラエルと、その同盟者、ファランヘ党
[*]とが西ベイルートを爆弾攻撃で脅かす――眠れる竜、シーア派を挑発
して目覚めさせる――まで、大規模には再開されることはなかった。話は変
わるが、ほんものの続編はサイゴンで演じられていた。1952年から53
年にかけての一連の自動車やオートバイを用いる爆弾攻撃は、グレアム・グ
リーンの小説『静かなアメリカ人』の筋書きに借用され、[主人公の]CI
A工作員、オールデン・パイルが、(爆弾攻撃実行の責を問われるべき)
ヴェトミン[ヴェトナム独立同盟]と(社会の安全保障達成がおぼつかな
い)フランスを両方ともに排除して、親米派政党が台頭することを画策する
ために、秘かに調整していたものとして描かれている。
[Phalange=レバノンのキリスト教徒主体の右派政党。フランコ政権下のス
ペインで唯一の合法政党(Falange)にちなんで命名]
実在の“静かなアメリカ人”は、(フィリピンの小農コミュニストに対する
勝利を収めたばかりの)対ゲリラ戦術専門家、エドワード・ランズデール大
佐であり、実在の“第三勢力”指導者は、大佐の弟分で、カオダイ[*]信
仰集団のトリン・ミン・ツエ大将だった。ツエの伝記作家は、将軍が「車両
に積みこんだ時限装置つきのプラスチック爆弾や、二輪車のフレームの中に
詰めた爆薬を使った、サイゴンにおけるテロリストの非道な攻撃の多くを教
唆していた」ことは疑いないと書いている。「特筆すべき例として、195
0年、リ・アン・ミン[ツエの軍隊]がサイゴンのオペラ・ハウスの前で複
数の自動車を爆発させている。これらの“時限爆弾”は50キログラム爆弾
を流用したものと伝えられ、フランス空軍が使い、不発だったものを、リ・
アン・ミンが回収したのである」
[1920年ごろ、ヴェトナムで起こった信仰運動。キリスト教・仏教など
のさまざまな宗教の要素を採りいれた雑多な教義だが、民族運動の側面をも
つ]
ランズデールはCIAのアレン・ダレスによってサイゴンに派遣されたのだ
が、その数か月前に、(ライフ誌掲載の、両足を吹きとばされた人力車夫の
直立した死体の世にも恐ろしい写真によって永遠に記憶されることになる)
オペラ・ハウスの残忍な事件が発生していて、これは公的にはホー・チミン
の仕業とされている。ランズデールは、こうした巧妙な(ガソリン・タンク
の隣に仮設された区画に爆薬を隠すという)攻撃の発案者は、ツエ将軍であ
るとじゅうぶん気づいていたが、それでもなお、このカオダイ軍閥の首領を
ワシントンやジェファーソンに匹敵する愛国者だと持ち上げていた。下手人
はフランスの工作員かヴェトミンの細胞のどちらか定かでないが、ツエ将軍
が暗殺されたあと、あるジャーナリストに向かって、ランズデールは彼を
「善人だった」と賛美して語っている。「彼は穏健な人物だった。きわめて
優秀な将軍だった。われわれの味方だった。彼には2万5000ドル注ぎこ
んだ」
模造品であろうと、改造品であろうと、自動車爆弾は、戦火にまみれた、も
うひとつのフランス植民地――黒い足[pied noirs=ヨーロッパ系北アフリ
カ人]、つまりフランス人入植者にとって、終末期のアルジェ――に再登場
した。1952年から53年にかけてのサイゴンで苦い思いを味わったフラ
ンス軍将校たちの一部も、ラウル・サラン将軍が率いるOAS
(Organisation de l’Arme Secrete=秘密軍事組織)の幹部になっていた。
61年4月、OASは、アルジェリアの反乱勢力との和解交渉に傾いていた
フランス大統領シャルル・ドゴールに対する蜂起に失敗したのにつづいて、
配下の退役落下傘部隊や外人部隊の侮りがたい経験を総動員して、テロ――
紛れもないプラスティーク[プラスチック爆弾]の祭典――に走った。OA
Sが指定した敵には、当のドゴール、フランス治安部隊、共産党員、(哲学
者・活動家のジャン=ポール・サルトルなどの)平和活動家、そしてアル
ジェリアの民間人が含まれていた。62年5月、最強最悪の自動車爆弾が、
波止場で仕事を求めて並んでいたイスラム教徒の沖仲仕62人を殺害した
が、これは、すべての黒い足を海に追いはらうというアルジェリア人たちの
意思を固めるのに役立っただけである。
自動車爆弾が次に登場したのは、シシリー島のパレルモだった。マフィア・
パレルモ本部のドン、アンジェロ・ラ・ベルベラがアルジェリアの爆弾事件
を注意深く見守っていたことには疑いの余地がないし、1963年2月に、
ライバルのマフィア、“リトルバード”・グレコに対して衝撃的な攻撃を仕
掛けたときには、なんらかのOASの専門技術を借用していたとすら考えら
れなくもない。グレコの拠点はパレルモ郊外のシアクリであり、そこで彼は
子飼いたちの一団によって厳重に警護されていた。ラ・ベルベラは、アル
ファロメオ・ジュリエッタの助けを借りて、この障害を取り除いた。「この
華奢な、フォードア、ファミリー・サルーンは――『優美、実用的、快適、
安全、簡便』と広告に謳われる――イタリアの経済的奇跡の象徴のひとつ
だった」と、ジョン・ディッキーが彼のコーザ・ノストラ[マフィア犯罪組
織]史に書いている。爆薬を搭載した一台目のジュリエッタはグレコの家を
爆破した。数週間後、二台目のジュリエッタは、グレコの主だった仲間の一
人を殺害した。グレコの殺し屋たちが反撃に出て、5月にミラノでラ・ベル
ベラに傷を負わせた。お返しに、ラ・ベルベラの野心的な若頭たち、ピエト
ロ・トレッタと(後にすべてのマフィア構成員のなかで最大の著名人にな
る)トマーゾ・ブシェッタが威力を増強したジュリエッタを差し向けた。
1963年6月30日、もはや何台目か分からなくなったジュリエッタが、
TNT火薬を詰めこまれ、シアクリ周辺のタンジェリン[柑橘の一種]畑の
ひとつに放置されていた。後部席に、導火線つきのブタン容器がはっきり見
える状態で置かれていた。その朝、近くの町で別のジュリエッタが爆発して
いたので、警戒態勢に入っていたカラビニエリ[警察隊]は、陸軍技術部隊
に支援を要請していた。「2時間後、2名の爆弾処理専門官が到着し、導火
線を切断して、車に近づいても安全であると断言した。だが、マリオ・マ
ローサ中尉がトランク内を検分しようとしたとき、積みこまれていた大量の
TNTを起爆してしまった。周辺数百メートルにわたり、タンジェリン果樹
を焦がし、裸にした爆発によって、中尉、その他6名がバラバラになって吹
き飛ばされた」(今日、パレルモ地域における爆弾犠牲者を慰霊する数基の
碑のひとつによって、事件現場を知ることができる)
この“第一次マフィア戦争”が1964年に終結する前に、シシリア住民は
ジュリエッタを見かけるだけで身震いするのが習い性になり、自動車爆弾は
マフィアの恒久的な十八番〈おはこ〉の演目になった。自動車爆弾は、81
年から83年にかけて、さらに激しい流血になった第二次マフィア戦争、別
称“マタンサ(Matanza=屠殺)”でふたたび採用され、世間を騒がせた一
連の“大型裁判”でコーザ・ノストラ幹部たちの有罪判決が出たあと、その
牙は一般公衆に向けられた。無差別的に猛威をふるう――たぶん“トラク
ター”・プロヴェンツァーノと配下のコルレオーネ出身ギャングが手配した
――自動車爆弾事件のなかで最も悪名高いものは、フィレンツェの中心市街
にある世界的に有名なウフィツィ美術館を損傷し、5人の通行人を殺害、他
に40人を負傷させた93年の爆発である。
“黒色火薬”
「われわれが立っていた場所で、ガタガタ震動を感じることができた。その
時、たいしたことに立ち会っていると悟ったのだが、そいつはそこから広
がっていったんだ」
――古参の元IRA構成員が最初のANFO[亜硝酸アンモニウム燃料油]
自動車爆弾を語って
第一世代の自動車爆弾――ヤッファ/エルサレム、サイゴン、アルジェ、パ
レルモで使われたもの――でさえ、(通常、数百ポンドのTNT火薬に相当
する最大威力があり)じゅうぶんな破壊力をもっていたが、盗まれた産業用
または軍事用の火薬を入手する必要があった。だが、職人技の爆弾作りたち
は――調合するさいの危険性の高さはよく知られているが、安価な経費でほ
ぼ無制限の破壊力が見込める――自家製の代用品に気づいていた。硝酸アン
モニウムは、どこでも売られている化学肥料や工業原料であるが、並外れて
高い爆発性を有しているのは、1921年、ドイツ、オッパウの化学工場で
発生した――240キロメートル離れた地点で衝撃波が感知され、工場の立
地点には巨大な爆発孔だけが残された――爆発とか、テキサス・シティの惨
事(600人が死亡し、町の90パーセントの建築物が損壊)といった偶発
的な異変で目撃されたとおりである。硝酸アンモニウムは、500キログラ
ム単位で、金廻りのきわめて悪いテロリストでさえも、なんとか購入できる
金額で売られているが、それを燃料油と調合して、ANFO爆薬を製造する
のは、71年末に暫定アイルランド共和国軍が知ったように、少しばかりの
厄介さではすまされない作業を要する。
「まったくの偶然によって、自動車爆弾は(再)発見された」と、ジャーナ
リストのエド・マローニは彼の作品『IRA秘史』に書く。「だが、ベル
ファストIRAがそれを採用したのは、偶然によってではなかった。197
1年12月の下旬、IRAの補給局長、ジャック・マッケイブが、ダブリン
北部郊外にある自宅ガレージで、“黒色火薬”の名で知られる、肥料を基材
にした実験的な自家製の混合物を、シャベルを使って調合していたさい、こ
れが爆発し、彼が重傷を負ったとき、すべてのできごとの連鎖がはじまっ
た。(暫定軍の)総司令部は、この混合物は危険すぎて扱えないと警告した
が、すでにベルファスト部隊は現物を受け取りずみであり、それに信管と時
限装置を付けて自動車の中に仕込み、ベルファスト中心街のどこかに放置す
ることによって廃棄したことにしようというアイデアを思いついた者がい
た」 なりゆきまかせの爆発は、ベルファストの指導部に強烈な印象を与え
た。
“黒色火薬”は――まもなくIRAが安全な扱い方法を習得したことにより
――地下組織の軍隊を供給サイドの制約から解き放った。自動車爆弾によっ
て強化された破壊能力は、志願兵たちが逮捕されたり、誤って吹きとばされ
たりする公算をさらに減じたのである。ANFO自動車爆弾合同作戦は、言
うなれば、思いがけない軍事革命であり、しかも同時に、政治的・倫理的危
険を招く恐れと背中合わせのものだった。「仕掛けの大きさそのものが、作
戦上の不注意または失策による民間人殺害のリスクを急激に増やした」とマ
ローニは強調する。
それでも、ショーン・マックスショフェイン率いるIRA軍事評議会は、こ
の新兵器の将来性はあまりにも魅力的であり、容赦のないしっぺ返しが、ど
のような形で自分たちに逆流してこようとも、心配するにおよばないと見
た。じっさい、自動車爆弾は、IRAが、英国政府に対して勝利するかどう
かは別にして、最終的な軍事反抗勢力であるとする、1972年時点の最高
首脳部の大半が共有していた幻想を補強した。そういうことで、72年3
月、2台の自動車爆弾がベルファストの都心に送りこまれ、続けて、警告を
装って虚偽事実を告げる電話があり、それに惑わされた警察は、うかつにも
爆発地点のうちのひとつの方向へ人びとを誘導したため、治安部隊員2名お
よびに5人の民間人が殺害された。一般市民の抗議やロイヤル・アヴェ
ニュー歩行者天国の即時通行止め措置にもかかわらず、新兵器に寄せるベル
ファスト旅団の熱意は衰えをしらず、指導部は、北アイルランドの正常な経
済活動を突発的な停止に追いこむことを狙った大規模な攻撃を謀議した。
マックスショフェインは、「この上なく獰猛〈どうもう〉で情け容赦のな
い」攻勢が「植民地基盤」を破壊するだろうと豪語した。
7月21日の金曜日、IRA志願兵たちは、もはや門を閉ざした中心街の周
辺に、20台の自動車爆弾を残したり、爆薬を隠したりして、およそ5分間
隔で順次に起爆するように調整した。最初の自動車爆弾が、ベルファスト北
部、アルスター銀行の前で爆発し、通りがかりのカトリック教徒の両足を吹
きとばした。一連の爆発が、鉄道駅2か所、アックスフォード通りのアルス
ター・バスターミナル、あちこちの鉄道分岐点、ケイブヒル道路のカトリッ
ク/プロテスタント両教徒混住地区に被害を与えた。「爆弾攻撃のまっ只中
にあって、ベルファスト中心部は、砲撃下の市街にも似て、次つぎに爆発が
起き、窒息性の煙が雲になってビル群を包み、パニックになった買い物客た
ちのヒステリックな叫び声をかき消すかのようだった」 民間人たちが爆発
から逃げまどい、今度は別の爆発によって押し戻されているときに、次つぎ
とかかってくるIRAがらみの警告電話が混乱の度をさらに深めた。7人の
民間人と2名の兵士たちが殺され、130人以上の人びとが重傷を負った。
“血の金曜日”は、それ一発で経済的な必殺パンチにならなかったが、北ア
イルランド経済が、とりわけ民間部門や海外からの投資を呼びこむ魅力を損
なうなど、急激に重大な打撃をこうむることになる「常軌を逸した」爆弾攻
撃作戦のはじまりになった。その日のテロ攻撃はまた、当局筋にベルファス
ト中心市街地を囲う対自動車爆弾“鋼鉄環状防衛線”を強化することを余儀
なくさせ、これが他の各地の要塞化居住区や将来の“グリーン・ゾーン”の
原型になった。1870年代にダイナマイト・テロ攻撃の創始者になった彼
らのご先祖、フェニアン[*]の伝統において、アイルランド共和国主義者
たちは、都市ゲリラ戦争の教則本にまたもや新しいページを書き加えた。外
国、とりわけ中東にいるIRAファンたちは、ANFO自動車爆弾と、都市
/地域経済全体に対して果てしなく続けられる爆破作戦における、この兵器
の採用という二重の改革をつぶさに注目していたに違いない。
[Fenians=1858年、米国とアイルランドで結成された、アイルランド
共和国の建設をめざす秘密結社。2〜3世紀の伝説、フェニアン武士団にち
なむ]
だが、アイルランドの国外で今ひとつ理解されていなかったのは、IRAの
自動車爆弾が共和国運動そのものにもたらした傷が大きかったことである。
血の金曜日は、IRAの英雄的な負け犬といった大衆受けするイメージを大
きく損ない、一般のカトリック教徒たちに深い嫌悪感を植えつけたし、英国
政府にとっては、ロンドンデリーにおける血の日曜日の大虐殺や審理なしの
拘留にまつわって世界中から糾弾されていたのが猶予されることになった。
おまけに、英国軍は、大規模なモーターマン作戦を発動するための申し分の
ない口実を得た。センテュリオン戦車隊に先導された兵力1万3000の部
隊がロンドンデリーとベルファストの“封鎖”区域に進入し、共和国運動の
手から街路の支配権を奪還したのである。同じ日に、ロンドンデリー郡クラ
ウディ村で、残虐にも、また不手際なことに、自動車爆弾攻撃が8人の死者
を出した。(プロテスタント王党派の民兵集団は――警告などという手間を
いっさいかけず、故意に敵側の民間人を狙っていたが――血の金曜日やクラ
ウディ事件を、1974年5月17日の午後のラッシュアワーに合わせて、
ダブリン市街に対する3連発の自動車爆弾攻撃を強行し、一日の犠牲者数と
しては“騒乱”期間を通して最大の死者を出した事件の免罪符にもちだして
いた)
ベルファストにおける総崩れによって、IRA指導部は大幅に入れ替わった
が、自動車爆弾の威力が戦闘の情勢を一変させるという、積荷崇拝カルト
[*]にも似た信念を一掃することはできなかった。モーターマン作戦のた
めに、そして血の金曜日が招いた猛反発のために、守勢にまわることを余儀
なくされたIRAは、攻勢に出ようとして、英国の権威の中心そのものに対
する襲撃を決意した。ベルファスト旅団は10台の自動車爆弾をダブリン=
リヴァプール間フェリー航路経由でロンドンへ送りこむ計画を立て、若い2
姉妹、マリオン、ダラース・プライスを含む、前歴のきれいな新顔志願者た
ちを実行部隊に仕立てた。思いがけない障害があり、ロンドンに到着したの
は、車4台だけだった。1台はオールド・ベイリー[中央刑事裁判所]の前
で爆発した。もう1台は、ダウニング街10番地の首相官邸に程近いホワイ
トホール[官庁街]のまん中で爆発した。180人のロンドン市民が負傷
し、1人が死亡した。IRAの爆破実行部隊の8名は程なく逮捕されたが、
西ベルファストの貧民街で高く称揚され、作戦は、暫定軍による、その後の
ロンドン爆破作戦の嚆矢になり、1992および93年、巨大な爆発がロン
ドンのシティー[金融街]を粉砕するまでになって、世界の保険業界を震撼
させた。
[現代文明の産物を満載した船舶または飛行機に乗って、先祖たちが来訪
し、労働と白人支配から解放されるというメラネシア特有の信仰]
地獄の厨房(1980年代)
「われわれは神の兵士であり、死は切なる望み。われわれは今にもレバノン
をヴェトナム化するだろう」
――ヒズボラ声明
1980年代初期のベイルートを措いて、ひとつの都市が、これほど数多く
のたがいに争いあうイデオロギー、宗教・宗派信条、地域対立感情、さらに
は諸外国による陰謀や干渉が入り乱れる戦場になった例は、世界史を見渡し
ても皆無である。レバノンの民族間戦争(例えば、シーア派住民vsパレス
チナ人)は、内戦(マロン派[キリスト教系]vsイスラム教徒とドルーズ
派[イスラムの一宗派])の一環であり、その上層に地域紛争(イスラエル
vsシリア)や代理戦争(イランvs米国)があり、さらに冷戦が大前提に
なっているという、フラクタル[任意の一部分が常に全体と相似する図形]
構造のマトリョーシカ[ロシア民芸品の入れ子人形]みたいな複雑さに比べ
れば、ベルファストの――武装3陣営(共和国派、王党派、英国)とそれぞ
れの分派が関与する――三つ巴紛争といえども、単純明快である。例えば1
971年時点において、西ベイルートひとつを取っても、58ものそれぞれ
別個の武装集団が並存していた。熱帯降雨林は植物進化の実験場だが、これ
ほど大勢の人たちが、これほど多く異なった道理により、たがいに殺しあお
うとしていたベイルートは、都市暴力テクノロジーの実験場になった。
1981年の秋、レバノンからのパレスチナ解放機構(PLO)の追放をめ
ざすイスラエルの戦略の明白な一環として、自動車爆弾が西ベイルートのイ
スラム教徒居住区を恒常的に脅かしはじめた。イスラエルの秘密諜報機関、
モサドは、それ以前にも、(例えば、1972年7月の、小説家、ガッサン
・カンファニの謀殺に見るように)ベイルートでパレスチナ人の指導者たち
を暗殺するために自動車爆弾を使っていたので、イスラエルが大虐殺を支援
していることを示す証拠が浮上しても、だれもことさらに驚かなかった。中
東学者、ラシド・ハリディの言葉を借用すれば、「取り押さえられた運転者
たちが公衆の面前でいろいろと白状したので、これらの事件(自動車爆弾攻
撃)は、イスラエルやそのファランヘ党同盟者たちがPLOの脱出を狙う圧
力を強化するために利用したものであることが明確になった」
ジャーナリストのロバート・フィスクは、「強大な(自動車)爆弾が土砂を
吹きとばし、路面に14メートルの爆発孔を残し、まるまる一街区のアパー
ト群を崩壊させた」とき、ベイルートに居合わせていた。彼はこう続ける
――「ビルはまるで蛇腹仕掛けのように崩落し、50人以上の現住者たちを
圧殺したが、その大半は、南レバノンから逃げてきたシーア派避難民だっ
た」。自動車爆弾犯人のうちの数人が拘束され、爆弾は、FBIや英国の特
別工作部局(the British Special Branch)に相当するイスラエル機関、シ
ン・ベット[Shin Bet=総合公安局]が用意したものであると白状した。だ
が、こうした残虐行為がPLOとレバノンのイスラム教徒との間にテロの楔
〈くさび〉を打ちこむことを狙っていたとしても、(後にイスラエル空軍は
民間人住宅地に対するクラスター爆弾攻撃を強行したが、これと同じよう
に)イスラエルの非公式の同盟者だったシーア派を、先鋭で断固たる敵にま
わすという意図に反した結果を招いただけだった。
1982年半ば、イスラミック・アマルが他の小規模な親ホメイニ諸集団と
合同し、シーア派武装組織のニューフェイスとして登場したのが、ヒズボラ
(Hezbollah)である。ヒズボラは、ベッカ渓谷でイランのパスダラン
[Pasdaran=革命防衛隊]による訓練と助言を受け、南ベイルートのシーア
派スラムに深く根ざした先住民抵抗運動、ならびにイランの神政革命の出先
機関という二つの顔をもっている。専門家のなかには異説を支持する向きも
あるが、イスラミック・アマル=ヒズボラは、1983年のベイルートにお
ける米軍やフランス軍に対する壊滅的な攻撃の主役であり、そのさいにイラ
ンとシリアの支援を受けていた。ヒズボラによる悪魔的な新機軸は、IRA
由来のANFO自動車爆弾に神風攻撃を結合した――自爆志願ドライバーを
使って、ベイルートの大使館ロビーや兵営に、また後には南ベイルートのイ
スラエル軍検問所やパトロール部隊に向かって、爆薬搭載トラックを突っこ
ませた――ことだった。
PLOの安全な市街地脱出を保証するためと謳って、ベイルートに進駐した
多国籍軍が、内戦において多数派イスラム教徒=ドルーズ派住民に敵対する
マロン派政府の、先ずは暗黙の、次いで公然の同盟軍に変質した結果、米国
とフランスは、ヒズボラ、さらにはその黒幕、シリアやイラン共通の標的に
なった。レーガン大統領の政策に対する最初の報復は、1983年4月18
日、2000ポンド[約900キログラム]の爆薬を搭載したピックアップ
が、突然の急ハンドルで車の行きかう往来を横切り、ベイルート臨海部の米
国大使館に向かう進入路に入ったときに敢行された。仰天した守衛を尻目
に、運手者はトラックを急加速し、玄関ドアを突き破った。「ベイルート標
準に照らしてさえ、ものすごい爆発であり、窓を粉ごなに粉砕した」と、元
CIA工作員、ロバート・ベーアは書く。「沿岸から5マイル[約8キロ
メートル]の沖合に投錨していた米艦ガダルカナルが震動で身震いした。グ
ラウンド・ゼロ[爆心地]では、7階建ての大使館の中心部が空中数百
フィートの高さに吹き上げられ、永遠と思える間、そのまま停止し、粉塵、
人体、裂けた調度品、紙片の雲となって崩落した」
優秀な諜報の結果だろうか、あるいは単なる幸運の賜物だろうか、爆弾攻撃
は、CIAの近東担当情報部員、ロバート・エームズの大使館訪問と時を同
じくしていた。爆発は、彼をCIAベイルート分局駐在員6名全員ともろと
もに殺害した(「彼の腕は、沖合1マイルの海上で、指に結婚指輪をはめた
まま浮かんでいるところを発見された」)。「CIAがこれほど大勢の部員
を一発の攻撃で失ったのは、未曾有のできごとだった。これは、情報部に
とって、いつまでも取り返しがつかない悲劇だった」 また、この攻撃のた
め、ベイルートのアメリカ人たちは情報入手に支障をきたし、フランス大使
館やキプロス島の英国海外傍受基地から情報の断片をあさるしかなくなっ
た。(1年後、ヒズボラは、CIA分局長の後釜、ウィリアム・バックレイ
を誘拐して、処刑し、CIAベイルート駐在員に対する虐殺を完成した)
その結果、情報部は“車両爆弾の親玉”の襲来を予見することがまったくで
きなくなった。
ロナルド・レーガンの国家安全保障問題顧問、ロバート・マックファーレン
は、ベイルート駐留米海兵隊の司令官、ジェラティ大佐による進言を受け
て、第6艦隊に、ベイルートの背後の丘陵に置かれたレバノン陸軍部隊陣地
を強襲していたドルーズ派民兵団に対する砲撃の開始を命令した――このよ
うにして、米国は、反動的なアミン・ジェマイエル政府の側に立って、厚顔
にも紛争に介入することになった。1週間後、国際空港に隣接する元PLO
本部を転用した米軍営舎、“ベイルート・ヒルトン”で、メルセデスの5ト
ン・ダンプカーが砂袋を積んだ海兵隊衛兵たちの脇を突破し、衛兵詰所をぶ
ち抜いて、建屋の一階に突入した。ダンプの搭載兵器は、信じがたくも1万
2000ポンド[約5400キログラム]の高性能爆薬だった。「これは地
球の表面で(人為的に)起爆した非核爆発としては史上最大のものだったと
言われている」 エリック・ハメルは、彼の海兵隊上陸部隊の歴史に次のよ
うに書き継ぐ――「爆発の勢いが、まず4階建て構築物全体を持ち上げ、そ
れぞれが円周15フィート[約4.6メートル]の太さをもち、おびただし
い数の1.75インチ[約44ミリメートル]鉄筋で補強されたコンクリー
ト製支持円柱の基部を裁断した。空中に浮かんだ建物は、次いで下から順に
崩落していった。激烈な衝撃波と燃えるガスの玉が全方向に急膨張した」。
海兵隊(および海軍)の死者数241人は、軍にとって1945年の硫黄島
決戦からこのかた最大の一日あたり損失だった。
一方、もうひとりのヒズボラ神風特攻隊員が、爆薬を搭載したバンを西ベイ
ルートのフランス軍営舎に突っこませ、8階建て構築物を倒壊させ、兵士5
8名を殺害した。空港の爆弾が、ジェマイエルを支援する米国に対する報復
であるとすれば、この二番手の爆発は、イラン攻撃用のシュペル・エタン
ダール攻撃機やエクゾセ・ミサイルをサダム・フセインに供与すると決定し
たフランスに対する仕返しだった。レバノン現地のシーア派の不満とテヘラ
ン政府の考える国益との間の境目は判然としないが、12月中旬、2名のヒ
ズボラ構成員に18名のイラク人シーア派が合流して、クウェートの米大使
館を自動車爆弾で攻撃するにおよんで、ますますぼやけたものになった。フ
ランス大使館、空港の管制塔、基幹的な製油所、外国人居住地区もやはり標
的になっていたので、この作戦は、明らかにイランの敵に対する厳しい警告
だった。
海兵隊前進基地に対する手痛い攻撃に加えて、ベイルートのフランス施設に
対する今一度の攻撃が繰り返されたのを機に、1984年2月、多国籍軍は
レバノンから撤退しはじめた。これは、レーガンの仰天きわまりない地政学
上の敗北だった。ワシントン・ポストのボブ・ウッドワード記者による、歯
に衣きせぬ言葉を借りれば、「ズバリ言って、わが国は尻尾を巻き、レバノ
ンから逃げ出したのだ」。ニューヨーク・タイムズのトーマス・フリードマ
ンが、「1万2000ポンドの爆薬と盗難トラックだけ」で、レバノンにお
けるアメリカの権威が帳消しになったと追い討ちをかけた。
(本稿――優に一冊の本になる研究の予備的な素描――は、来年刊行のマイ
ケル・ソールキン編、ルートレッジ社(Routledge)2007年刊
“Indefensible Space: The Architecture of the National Insecurity
State” [仮題『防衛不能な空間――国家安全保障不全状況の構造』]に収録
の予定)
[筆者]
マイク・デイヴィス(Mike Davis)は、カリフォルニア州サンディエゴ在
住。最新著作――
“The Monster at Our Door: The Global Threat of Avian Flu” (The New
Press)
『感染爆発――鳥インフルエンザの脅威』柴田裕之・斉藤隆央訳、紀伊国屋
書店
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9980525479
[同サイトにある著者紹介――1946年カリフォルニア州フォンタナに生
まれ、サンディエゴの近くで育った。精肉工場の工員や長距離トラックの運
転手などを経て、労働運動の活動家に。その後、リード大学とカリフォルニ
ア大学で歴史学を学ぶ。辛口の社会批評家として知られ、現在はカリフォル
ニア建築大学で都市論を教えている]
“Planet of Slums” (Verso)[仮題『スラムの惑星』]
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/1844670228
(本稿は、自動車爆弾の歴史・パート2「翼を生やした自動車爆弾」に続
く)
[原文]
Tomgram: Mike Davis on the History of the Car Bomb
posted April 12, 2006 at 12:23 am
http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?emx=x&pid=76140
Copyright 2006 Mike Davis
[翻訳]井上利男 /TUP