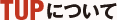FROM: hagitani ryo
DATE: 2006年11月23日(木) 午前0時48分
☆人命や道義よりも石油が大事★
ダルフールのジェノサイドとその背景については、昨年9月配信のTUP速
報539号「資源戦争の現場、ダルフール」《*》に詳述されていますが、
本稿はその続編にあたり、ダルフール紛争におけるブッシュ政権の不作為を
告発しています。今回の中間選挙で野党・民主党が上下両院ともに主導権を
奪還した結果、米国の外交政策がまっとうな方向に修正されるかどうかを見
るための試金石のひとつが、これからの対スーダン政策の推移になることは
間違いないでしょう。井上
http://groups.yahoo.co.jp/group/TUP-Bulletin/message/585
参考資料:
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ダルフール紛争
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%B4%9B%E4%BA%89
凡例:(原注)[訳注]《リンク》〈ルビ〉
トム通信:
デイヴィッド・モース、
ダルフールをめぐるブッシュ政権の「宥和[*]策」を語る
抗マスメディア毒・常設サイト「トムディスパッチ」
2006年9月25日
[〈ゆうわ〉=不和を避けるために、相手の要求を受け入れること。譲歩。
歩み寄り]
[トム・エンゲルハートによるまえがき]
奇妙ではないか? 私たちの世界が時として、たったひとつのものに集約さ
れてしまう。今のご時勢、どんな話題を取り上げても――例えば、ダルフー
ルのジェノサイドを語ってみても――遅かれ早かれ、石油を論じていること
になる。今この瞬間、世界はエネルギー争奪戦に遭遇している。これをこれ
までの2世紀間にわたる軍拡競争に相応する21世紀版の競争だと考えてみ
よう。エネルギー資源の兆しや情報のあるところ、どこでもこの黄金(黒
い)をめざす狂乱の突進を目にすることになる。
中東は世界の中核的油田地帯であるが、エネルギー需要が増大し、エネル
ギー資源枯渇の不安も増大する世界にあって、中央アジア《1》と並んで、
アフリカがにわかに石油開発の焦点になっている。ほどなくペンタゴンが独
自の米軍アフリカ司令部を置くことを公表する見込みである《2》。それに
続き、この大陸に新たな基地設営の動きが見られるはずだ。このようななり
ゆきは、いつも決まって大統領の対テロ世界戦争の文脈に沿って説明される
が、基本的にはエネルギー対策である。
1 http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/HI23Ag02.html
2 http://www.atimes.com/atimes/Front_Page/HI21Aa01.html
デイヴィッド・モースが以下に指摘するように、これはわが国だけのことで
あるとはとても言えない。例えばスーダンでは、ヨーロッパ人に加え、中国
人も今では重要な顔触れになっている《1》。ダルフールで進行している大
量虐殺は、石油開発に深くかかわっている《2》ことが明らかである。8月
下旬、ブッシュ政権はイラク戦争反対に対する「宥和」攻勢でアメリカの中
間選挙シーズンの幕を開けた。スーダン情勢の専門家であるモースは、この
「宥和」攻勢を、ダルフールにおけるジェノサイド、ならびに同地域におけ
る石油争奪戦という文脈のなかで考察する。トム
1 http://www.afrol.com/printable_article/21316
2 http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?pid=14239
石油が動機の宥和策
ブッシュ政権とダルフール
――デイヴィッド・モース
今、ブッシュ政権は自分のイラク戦争を批判する勢力に対して「宥和」攻勢
《*》をかませることを習いにしている。スーダンに対する大統領の姿勢を
つぶさに見てきた人なら、このことの深い皮肉がわかるだろう。
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/30/AR2006083000704.html
ブッシュ大統領は、世界の「イスラム教ファシスト」をナチスの後継者とし
て目の敵にしながら、みずからの立場は第二次世界大戦期のルーズヴェルト
やチャーチルになぞらえている。先日、彼は「われわれはみずから望まな
かった戦争に従事していますが、これはわれわれが遂行しなければならない
戦争であり、われわれが勝つ戦争なのです」と明言した。
彼のいわゆる「みずから望まなかった」戦争が、捏造証拠にもとづいて、
「衝撃と畏怖」の先制攻撃をもってはじまったこと、あるいは彼の政権が世
界のイスラム過激主義を抑えるどころか、その炎を煽りたてた《*》ことは
横に置いておこう。あの「宥和」攻勢に焦点を絞っていただきたい。私たち
の目を、ジョージ・ブッシュ本人とその姿勢に反対する大統領批判派から、
スーダンの不穏な西部地方、ダルフールに転じてはじめて、この攻勢の意味
がどのようなものであれ見えてくる。
http://www.nytimes.com/2006/09/24/world/middleeast/24terror.html?ei=5094&en=22b7a0941b08007f&hp=&ex=1159156800&partner=homepage&pagewanted=print
敵性イスラム教ファシストとはだれか
単純に、ジョージ・W・ブッシュ本人の言葉に語らせてみよう。彼にも疑わ
しきは罰せずの原則を適用し、彼がお気に入りのレッテル「イスラム教ファ
シスト」で意味しているのは、世界13億人のモスレムということでのイス
ラム教徒ではなく、自分たちの世界観を他に押しつけようとする原理主義モ
スレムだけであるということにしておこう。
どこかのイスラム主義政府が「ファシスト」の悪名に値するとすれば、19
89年に軍事クーデターでスーダンの支配権を奪取し、現在の統治者、オマ
ル・アル=バシール中将を擁立した民族イスラム戦線(NIF)の政府は、
まさしくそれだ。アフリカ黒人が歴史的に奴隷とされ、現在も奴隷化され、
社会の周辺に置かれている国で、NIFは北部のアラブ人エリートの人種的
優越性を前提とするご大層な綱領を掲げて支配権を握った。首都ハルツーム
の中央政府を支配したNIF政党は、キリスト教徒や南部に住む土着宗教信
者も十把ひとからげにしたスーダン全国民に、シャリーア、すなわちイスラ
ム原理主義の律法を押しつけようとしたのである。
[シャリーア=イスラム教徒の社会で伝統的に定めてきた法で、コーラン
(アッラーの啓示)、スンナ(開祖ムハンマドの言行録)、ムハンマド以後
の権威による説もまじえたものを根拠にしている。女子性器切除のように
コーランに根拠をもたない土着の慣習も加わっている。なお「原理主義」と
いう用語が一般に乱用されているが、これは一部のキリスト教プロテスタン
トが、福音書の奇跡と旧弊な戒律(同性愛敵視など)を恣意的に選んで信じ
るもので、原語のfundamentalismにも「原理」という意味はない。より原語
に忠実な訳としては「根本主義」。これをイスラムの運動にあてはめるのは
不当で、こちらは「復古主義」と言うべきだろう]
NIFの野望は、国土面積がほぼ100万平方マイル[250万平方キロ
メートル]もあるアフリカ最大の国にとってさえ、あまりにも大きなもの
だった。その野望は大陸全域、さらには中東にも広がった。1990年代に
は、ハルツームは国際テロリストたちの温床になり、そのなかにオサマ・ビ
ン=ラディンもいた。バシールはスーダンをアフリカ全体のアラブ化とイス
ラム化のための出発点と見なしていた。彼の政党の「全体主義イデオロ
ギー」は、貪欲とないまぜになってハルツーム政府を動かし、南スーダンで
新たに発見された油田を横取りするために、1980年代初期に支配領域境
界線を引き直すという簡単な方便を用いて南部に渡すことを拒ませた。これ
が引き金になって熾烈な内戦が勃発し、それが22年間継続して、南部の貧
しい黒人自給自足農を主体とする推定200万人のスーダン民間人の生命を
奪った。その大部分は、食糧供給が断たれたさいの餓死者だった。今、同様
な理由により、この悲劇がスーダンの最貧地域ダルフールで再現され、進行
している。
ハルツーム側の人種差別は、南北間内戦では、宗教的側面のために不明瞭に
なっていたとしても、ダルフールでは、アラブ人イスラム教徒が黒人イスラ
ム教徒を殺しているので、まったく誤解の余地はない。これまでの3年間、
馬やラクダにまたがり、武装したアラブ民兵が、ハルツーム政府の支援と政
府軍機の空襲による援護のもと、ダルフールの非アラブ人農村地帯を襲撃し
て、住民を殺し、レイプし、井戸に毒を入れ、牛や家財を略奪し、住宅やモ
スクを焼き、生存者をその土地から追い払うという民族浄化の焦土作戦をお
こなってきた。今では、人口のおよそ半分、約350万人の難民化したダル
フール住民が、全面的に外部からの食糧援助に頼って暮らしている。
一方、NIF支配下の政府は、ダルフールでの軍事作戦がジェノサイドの性
格を帯びていることをハルツーム市民に知られることを、さまざまな手段
――スーダン国内報道の検閲、新聞の発禁処分、活動家に対する拷問、海外
のジャーナリストに対するビザ発給拒否――を駆使して防いでいる。
要するに、ここに見られるのは、経済的・軍事的規模はかなり異なっている
としても、ナチス・ドイツと著しく類似した全体主義体制なのだ。これはま
たサダム・フセインの体制よりももっと残虐な体制であると言っても間違い
なく、しかももっと拡張主義的な政策を掲げている。つまり、過去にテロリ
ストを後援したことがあり、国連がダルフールに介入するなら、ジハード
[聖戦]を発動すると脅すようなゴロツキ国家である。今年の早い時期、オ
サマ・ビン=ラディンは、世界のテロリストたちに向けて、ハルツーム支援
に駆けつけるようにと呼びかける指令を発した。スーダンは、アル=カイダ
との正真正銘の――捏造したものではない――結びつきをもっている。言い
換えれば、ハルツームは、ブッシュ氏が敵性「イスラム教ファシスト」に望
むに違いないすべての条件に適っている。
本物の「イスラム教ファシスト」の脅威に対するブッシュの反応
2004年9月、当時の国務長官コリン・パウエルが、ダルフールの状況を
「ジェノサイド」と表現しながら、わが国はこの地域に「死活の利害がな
い」ので、アメリカは軍事介入しないと断ったのは周知のとおりである。こ
れまでの2年間、この政治的現実主義による論理の歪曲が米国の対スーダン
政策を支えてきた。「死活の利害がない」という主張が信頼性をもつように
見えるのは、1997年にビル・クリントン大統領[当時]が国務省のテロ
支援国家リストにスーダンを加えたときに課した制裁処置のおかげである。
これらの制裁処置は今も有効であり、スーダンと取引をおこなったアメリカ
国民に対する重い罰金や実刑を含んでいる。
ジェノサイドというパウエルの表現は衝撃的であり、「死活の利害がない」
という付言がハルツーム政府にアメリカの不介入を保証したにせよ、当時の
ヨーロッパの外相たちに欠けていた道徳性のある素直さを示すものだった。
ブッシュ大統領も2004年9月21日の国連総会演説でこの言葉を使っ
た。「世界は、スーダンのダルフールで凄まじい苦難と恐るべき犯罪を目撃
しており、私の政府の認定では、これはジェノサイドです」
強い言い方ではある。しかし後から考えると、これは[アメリカの]保守派
キリスト教徒をなだめる選挙対策用の飴玉として念入りに練られた発言と見
ることも可能だ。彼らは、スーダン内戦でハルツーム政府が南部のキリスト
教徒に対してしかけた攻撃に年来の不満を抱いていたからである。
2004年[大統領]選挙が終わると、虐殺は続いているのに、アメリカ政
府はダルフールについて口を閉ざしてしまった。2005年3月はじめにハ
ルツーム政府はビザ発給を停止し、なおも続いていた虐殺を外国人が目撃す
るのを不可能にしてしまった。NGO・国境なき医師団の2人の幹部職員
は、ハルツーム政府はレイプを軍用武器として用いているという報告をオラ
ンダで配布しただけで、「国家反逆」罪で投獄された。ブッシュは沈黙した
ままだった。
ホワイトハウスが指導性を発揮しないので、米連邦議会は「ダルフールの平
和および説明責任に関する法案」をめぐる駆け引きで2005年の大半を費
やしていた。この超党派の法案は、当初はそうとうに強い威力をもってい
た。クリントン政権の時代に定められ、対象を通商のみに限っていた現行の
制裁に、広範囲の規定を加えたのである。新しい制裁によって米国政府は、
国連決議によるスーダンに対する武器売却の禁止をめざし、ダルフール上空
に飛行禁止空域を設定し、「スーダンの石油産業部門」を動かすための特に
指定しない方策を探し、人道援助団体職員のダルフール被災地入りを保証し
たとして記録に留められるはずだった。それよりさらに的を得ていたのは、
ジェノサイドに責任を負うスーダン政府の個々の人物を特定して、海外資産
の凍結と旅行制限を課することになっていた点である――まさしくこれは、
そういう人物が恐れる類の拘束だった。国際刑事裁判所(ICC)に起訴さ
れる可能性があるなら、なおさらである。
総合的に見て、これら強力な制裁は、議会承認を経たなら、そして国連安全
保障理事会で採択されていたなら、あるいはジェノサイドを直ちに終息させ
ていたかもしれない。ところが、これが安全保障理事会をすんなり通ってい
たかどうかには疑問がある。ロシアと中国はスーダンに武器を売却してい
る。中国、英国、フランスはスーダン石油資源の開発に深くかかわってい
る。じっさい、1997年の制裁措置のもと、すでにアメリカ企業が対スー
ダンとの取引を禁じられていることを考えると、このような米国提出の決議
案は利己的なものに見られたかもしれない。
だが、ここで問われるべきことはこうだ――ブッシュ大統領は法案を支持し
たのか?
答えは――まるっきり正反対。議会の委員会では、ホワイトハウスからの圧
力のため、ほとんどすべての制裁案がひどく弱められるか、あるいは退けら
れたのである。石油産業部門に対する禁輸の可能性に触れた文言は消され
た。個人を標的にする諸条項は、戦争犯罪人をICCに訴追する権限を大統
領に与えるとする単一の条項に置き換えられた。この政権がICCに敵対し
ていることを考えれば、こういう見通しはとても期待できない。この最終版
にいたって、法案は骨抜きになっていた。これは資金不足のアフリカ連合ダ
ルフール監視団にささやかな資金――贖罪金――を提供したが、他に見るべ
きものはなかった。
大統領は、間違いなく国家の道義的な姿勢を明確にしていたはずであり、何
万人もの命を救ってさえいたかもしれない法案を支持しなかったことによっ
て、自分が抽象論で罵倒している「イスラム教ファシスト」にほかならない
相手に対決せず、譲歩する道を選んでいた。
これが、政権を握って間もないころ、ルワンダのジェノサイドに対するビル
・クリントン前大統領の不作為に言及した報告資料の余白に「私の任期中に
こんなことはない!」と殴り書きした、あのジョージ・W・ブッシュと同じ
人物だったのだ。この文言は、サマンサ・パワー、その他の記者たちによっ
て、自分が大統領の職にあるかぎり、このような惨事を容認しないという
ブッシュの宣言と解釈された。もしそうなら、彼のこれまで2年間の後退
は、なおさら惨憺たるものだということになる。だが、この殴り書きには、
もうひとつ別の解釈も可能である。ルワンダの事態は他人の在任中のできご
とだった、と胸をなでおろした気持を表したものと見ることもできるから
だ。
油田登場
ブッシュ政権が発足した当時、じっさいにどれほど多くの石油がダルフール
の不毛な赤土のサヴァンナの下に眠っているのか、少なくとも外部世界には
知られていなかった(スーダン政府が予備的な地質調査を委託していたにせ
よ、不十分な内容だった)。ダルフールはテキサス州の4分の3の面積があ
り、その地での武力衝突が、国土の広大な地域に地質学専門家たちが入るの
を阻んでいた。しかし、2005年初めには、村落が破壊され、住民たちが
土地から一掃されたため、石油探査の方途が開かれた。
2005年4月まで、ダルフールの油脈は地域の南東の隅にしかないとされ
ていた。だが、新たに実施された地震探査の結果、意外な事実が判明した。
2005年4月19日のこと、スーダン政府エネルギー省のモハメド・シ
ディグ広報官が、既存の油田地帯から数百キロメートル北西のダルフール北
部で産出量の多い油井が新たに掘削されたと発表した。その一帯に原油産出
量が日産50万バーレルにも達すると期待できる巨大な油層が存在すること
を探査データが示していたのである。このダルフール油田の発見によって、
スーダンの石油埋蔵量はほぼ倍増した。
たぶん石油の新発見と同じぐらい驚くべきことは、このニュースがロイター
通信で簡単に報じられただけで、世界の報道機関に取り上げられなかったと
いう事実だろう。おそらく読者も、この発見について、トムディスパッチの
この記事で初めて知ったはずである。それでもこれが、ダルフールをめぐる
ブッシュ氏の不可解な後退の理由の一端を説明するかもしれない。
すでにブッシュ政権は、大統領の対テロ世界戦争で採りうる作戦についての
情報を共有するために(と主張して)、ハルツーム政府との緊密な関係を築
いていた。2005年4月の油田発見が、この外交努力に拍車をかけたよう
であり、その1か月後に米国中央情報局がジェット機をハルツームに飛ばし
て、バージニア州ラングリーのCIA本部での秘密会議に、スーダンの情報
部長官であるサラー・アブダラー・ゴシュ少将を招いた理由もそこにあるか
もしれない。
ロサンジェルス・タイムズがこの会合を暴露すると、政界は大騒ぎとなった
(また国務省は、ゴシュを戦争犯罪人として逮捕すべしとする一派と政府の
路線を追従する他派とに分裂した)。コンドリーザ・ライス国務長官は、ア
メリカ政府が「対テロ戦争」での協力のためにテロリスト体制と「より緊密
な繋がり」をもつ理由を説明するという厄介きわまる役回りを担った。スー
ダン側は、間もなく米国の制裁が解除されるものと期待を表明した。
2005年6月のスーダンで、契約に署名するために、インド、フランス、
マレイシア、中国、英国、日本、スウェーデンの石油企業関係者たちが群れ
をなして来るのが見られたのに、アメリカ企業関係者たちは、1997年制
裁条項のため、公式には傍観者の立場に置かれていた。ビジネスマン殺到は
ひとつにはダルフールの新油田発見が引き起こしたものだが、同時に待望の
南北和平協定が7月に発効する予定で、内戦がそれで終結するということも
あった。
政権分担合意の一端として、反政府軍指導者だったジョン・ガランがスーダ
ンの副大統領の座に据えられ、石油収益はハルツームのスーダン政府と現在
の南スーダン半自治区政府との間で分配されることになった。すでにガラン
は英国のホワイト・ナイル社という新しい石油企業と取引契約を結んでい
て、スーダン政府が、フランスの巨大石油企業、トタール社との間で締結し
ていた契約を廃止していた。内戦の時期に戦闘が激化したとき、トタールは
スーダン南部から撤退していた。ロンドン株式市場におけるホワイト・ナイ
ル社の株価は高騰した。トタール社は裁判に訴えると脅した。
「死活の利害がない」
アメリカ企業はスーダン石油の争奪戦に表立って参入することはできなかっ
たが、多くは制裁の抜け道を見つけていた。ひとつの方法は少数者所有であ
る。例えば、ヒューストン[テキサス州]に本社を置くブッシュ再選運動の
大口献金企業、マラソン・オイル社は、フランスのトタール社の共同出資企
業のひとつである。ジョン・ガランがホワイト・ナイル社との契約に署名す
ることによって、そのような思惑の裏をかく前に、マラソン・オイル社は、
油田地帯でのトタール社の事業に参画することを期して、スーダン政府に対
する払い込みを再開していた。
それに加えて、おそらくいくつかの――ペーパー・カンパニーを含む――外
国籍企業が、制裁解除を待つ米国籍企業の繋ぎになっていたことだろう。そ
ういう「外国籍」企業のひとつは、ヴァージン諸島で登記され、営業用住所
がスイスになっていて、そのオーナーはアメリカの石油王フリードヘルム・
エロナート、過去にエクソン・モービルの隠れ蓑だったことのある人物であ
る。エロナートがダルフール石油を獲得する取引の中心人物であったこと
は、BBC4[*]の番組で明らかにされている。彼が実刑や罰金を回避で
きたのは、スーダン南部からダルフール中心部を貫いて西に広がる広大な地
域の採油権に関する大儲けの契約をスーダン政府と締結する直前に、国籍を
アメリカから英国に移したからにほかならない。ダルフール新油田の発見の
結果、その契約は今や10億ドル単位の値打ちがある。この取引は英国の人
権活動団体から大変な非難を浴びたが、米国メディアはほとんど関心を示さ
なかった。
[ニュース・教養番組専門の英国放送協会ラジオ局]
「エロナートはダルフールや政治問題に関心がありません」と元同僚はBB
Cに語った。「彼の関心は金儲けなのです」
それにしても、エロナートは自分個人の利益のためだけで動いていたのだろ
うか? それとも、なんらかの第三者のための仲介者だったのだろうか?
ここに疑惑がある。制裁条項を回避するために使える口実はさまざまだが、
たいがい、ペテンや賄賂、あるいはもっと悪質な手口が付きものである。エ
ロナートのような者はこうしたいかがわしい世界で栄えるかもしれないが、
エクソン・モービルほどの巨大石油企業が、このようなまさしく「帳簿外」
のプロジェクトに深入りするわけにはいかない。だから、ブッシュの大統領
選挙運動に資金を提供し、彼の石油中心のエネルギー政策を作成したその業
界が、今、スーダンとの国交を正常化するように、この政権に圧力をかけて
いるのに違いないのだ。それも、ただちに正常化するようにと。アフリカ石
油の世界的な争奪戦が熾烈化すると、エロナートのようなやり手が吹っかけ
る代価は上がる一方になる。
2005年の7月、ジョン・ガランは、歓呼の声をあげる大群衆の支持者た
ちを前にスーダン副大統領に叙任された。新時代の幕があがった。その3週
間後、ヘリコプターの墜落で、彼は死んだ。ハルツームで、また南スーダン
の首都ジュバで、暴動が勃発した。墜落の真相はいまだに調査中である。こ
れまでスーダン南部の治安は保たれているが、それはかろうじてといったと
ころ。石油は今でも南北間の係争の種として残っている――そして、スーダ
ン政府は油田地帯に自軍兵力を置いている。
これまで述べたことのすべてが、ダルフールにはきわめて大きな利害がか
かっていること、米国はスーダンに「死活の利害」をもたないという言い分
は完全な偽りであることを示している。石油は別にしても、スーダンは大き
な国であり、アフリカの最貧国のひとつで、金やウランをはじめ未開発の鉱
物資源が眠っている。この国は、アフリカの角[*]をにらみ、他の10か
国と国境を接する戦略的に重要な地理学的位置を占めている。現在、スーダ
ンの最大貿易相手国は中国である。
[アフリカ大陸の東北端。ソマリア、ジブチ、エチオピアの一部を含む]
市民運動や識者たちは今でもコリン・パウエルの「ジェノサイド」という発
言を引き合いに出すが、ブッシュ政権はこの言葉を使おうとしない。今年の
4月にスーダンを訪問したロバート・ゼーリック国務次官は、ダルフールに
関する公式見解をバッサリと撤回した。「大変な事件が連続しました」と彼
は言った。「ご存知のように、それについては論争になっています。これは
ジェノサイドか、(国連が)法律論的に分析し、ジェノサイドではなく、人
道に対する罪であると結論しました」
ゼーリックの側からすれば、これは無意味な言葉の詮索ではなかった。ジェ
ノサイドと認定すれば、国連は1948年の集団殺害の防止および処罰に関
する条約を遵守することが求められただろう。ゼーリックの言い逃れは、
ブッシュ政権の政策転換を示しているようだった。ダルフール住民はどれほ
ど死亡したのかと質問されて、彼は6万から16万人ぐらいだろうと答え
た。責任のある立場の専門家による推定は、確かに大きな開きがあるが、2
0万から50万人の範囲である。だがゼーリックは、まるでだれかに死者の
数を3分の1に減らせと指示されたかのようだ。ところが、ブッシュその人
は先週の国連演説でこの言葉を使っている。政権内部で見解が一定していな
いのかもしれない。
石油が動機の宥和策
米国籍石油企業とスーダンとの間にある障害は、ダルフールのジェノサイド
に尽きる。
それでは――道義的理由はさておき、実益上の理由から言っても――なぜ、
ホワイトハウスは大量虐殺を止めさせるために断固とした処置をとらなかっ
たのだろうか? またなぜ、今年の5月、失敗することが目に見えていたの
に、米国政府はスーダン政府とダルフールの反政府団体の協定の仲介に手を
貸したのだろうか?
二つ目の疑問のほうが答えは簡単だ。ダルフール和平協定は大急ぎで交渉が
進められた。ハルツーム政府代表団は席を立つと言って、交渉打ち切りの脅
しをかけた。反政府諸党派は慌てふためいた。面目をつぶされたくない気持
と不安に駆られた彼らは、意見の相違を押し隠し、大急ぎで文書を作成した
が、それに署名したのは反政府4集団のうちの2派だけだった(対照的に、
南北内戦に終結をもたらした包括的和平協定の成立にこぎつけるまでには、
何年間にもわたる多くの交渉が必要だった)。ダルフール和平協定のもたら
したものは、スーダンと米国の両政府が努力したと言えるようにする政治的
アリバイだけだった。
では、より困難なほうの問題に移ろう。なぜブッシュ大統領は大量虐殺を止
めさせるために本気で影響力を行使しないのか?
一番同情的な推測は、大統領が、スーダン南部のキリスト教徒の殺害に逆上
している保守的キリスト教界の支持層と石油業界の後援者たちとの間で板ば
さみになっているというものである。実は、ブッシュは身動きならなくなっ
ているのかもしれない。それは、ビル・クリントンが、ルワンダの大量虐殺
を前にして、そうなってしまったのと同じだろう――また、世界は、人間が
互いになしうる最悪の行為に直面するとき、多くの場合、身動きとれなくな
るものである。
仲裁に入ることを考えようとすると、ブッシュは、アメリカの失敗――ソマ
リアでクリントン政権がしくじった国家建設、イラクとアフガニスタンにお
けるブッシュ自身の失敗、さらには政治問題に軍事的解決策を当てはめよう
とする試みに内在する失敗――という不安を呼びさまされるのかもしれな
い。
だが、これはありそうにない話だ。ジョージ・W・ブッシュは自分に与えら
れた道義的に不可避の義務の何たるかがわかっていない、彼と彼の政権の閣
僚は純粋に実益一点張りの考え方をしているとしたほうが、はるかにありそ
うなことだ。もっとあけすけに言えば、この政権は、行動を伴わない心配の
ポーズで押し通すのが一番簡単だ――つまり、政治的コストを最小限に抑
え、スーダン政府にできるだけ早く仕事を終えさせることだ――と思ってい
るのかもしれない。
確かに「しているふり」がブッシュのふるまいの特徴である。何か月にもわ
たり活動家団体から強い要求を受けたすえ、ようやくスーダン派遣特使を任
命し、今月初めに国連に対し、民間人保護を任務とする強力な平和維持軍を
ダルフールに送ることを公式に要請した。ブッシュはNATO軍が強制的に
施行する飛行禁止空域を支持するとついに報じられた。だが、こうした処置
は1年以上も前に議会が要求した制裁措置からは程遠い。いまなお目立って
欠けているのは、個人に対する制裁である。
最後に、国連の内部でも外部でも一番求められているのは、まさしく多角的
で平等な外交だが、それは、この政権が一番理解していないように思われる
事柄である。ブッシュ本人は、弱いものいじめと武力――あるいは、スーダ
ンの場合で言えば、その裏側としての宥和政策――だけしか理解していない
ようである。
石油を動機とした宥和策は確かになによりも非難されるべきである。現実に
直面するとき、この大統領は、紛れもない自分の悪夢の「イスラム教ファシ
スト」に立ち向かうのを明らかに避けている。
[筆者]デイヴィッド・モースの記事や論稿は、ディセント、エスクワィ
ア、フレンヅ・ジャーナル、ネーション、ニューヨーク・タイムズ・マガジ
ン、プログレッシブ・ポピュリストの各誌、オルターネット、カウンターパ
ンチ、マザー・ジョーンズ、サロンなど、さまざまなオンライン報道サイト
に掲載。彼の前回のトムディスパッチ記事“War of the Future: Oil
Drives the Genocide in Darfur” 《*》は広く転載され、数か国語に翻訳
されている。目下、ダルフール情勢に関する書籍を執筆中。
*TUP速報539号「資源戦争の現場、ダルフール」 050903
http://groups.yahoo.co.jp/group/TUP-Bulletin/message/585
[原文]
Tomgram: Morse on Bush Administration “Appeasement” in Darfur
posted September 25, 2006 at 9:49 am
http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?emx=x&pid=124232
Copyright 2006 David Morse
[翻訳]井上利男 /TUP
–