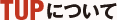◎宗派や共同体の境界を超えて団結する市民社会
シリアは今、どうなっているのか、そして、どこに向かっていくのか。
大統領を退陣に追い込み旧体制を崩壊に導いたチュニジア、エジプトの民衆蜂起の炎が、シリアに火をつけて1年、父ハーフィズ・アサドの時代から40年続く アサド大統領の独裁体制打倒を求める市民の蜂起に対し、アサド政権は、リビアのカッザーフィ大佐同様、軍を動員して強権的に弾圧、市民に対する体制側の攻 撃・迫害によって非暴力の大衆デモは武装蜂起へ至り、体制のなりふりかまわぬ弾圧を招来し、シリアは今や内戦的状況を呈している。反政府勢力は国際的介入 を要請し、諸外国は、軍事的直接介入こそ行っていないものの、それぞれの思惑で、反政府勢力を支援、虎視眈々と成り行きを注視している。
国連・アラブ連盟が解決の糸口を探るが、介入は目下のところ功を奏さず、反政府勢力に対する政府の攻撃はむしろエスカレートしている。
独裁打倒に立ち上がった市民を虐殺する政府軍というメディアの言説に対し、蜂起は諸外国の策謀、国民はアサドを支持しているという対抗言説も流布 し、混迷するシリア情勢同様、シリアをめぐる言説状況もまた錯綜している。だが、一連の「アラブの春」のなかで、シリアでは終わりの見えない、長い悲劇の 春が続いていることだけは確かであり、その悲劇の犠牲者が、長く、アサド独裁体制の犠牲者であった市民であることも事実である。
この混迷するシリア情勢を私たちはどのように理解し、考えればいいのか。
その一助となることを願って、1970年から40年以上にわたり中東情勢に関する情報と分析を提供し続けるMERIP(中東研究情報プロジェクト) の最新中東レポートから、蜂起から1年を迎えたシリア情勢をまとめたピーター・ハーリングとサラ・バーグの分析を以下に紹介する。私たちが、混沌のシリア 情勢を理解する上で、ひとつの包括的視座を与えてくれるだろう。
前書き:岡真理、翻訳:荒井雅子 /TUP
〔 〕:訳注
シリア政権崩壊の先にあるもの
2012年3月3日
ピーター・ハーリング&サラ・バーク
シリアで蜂起が始まってまもなく1年になろうとしているが、それは、アラブ諸国の一連の蜂起の中で、もっとも悲劇的で影響が大きく、先の見通せない 事態となっている。2011年3月シリア全土の町や村で抗議デモが発生して以来、国内危機がシリアの将来をめぐる戦略的闘争と絡み合い、多大な犠牲が払わ れてきた。
バッシャール・アサド政権は、40年にわたる支配〔訳注〕へ の深刻な脅威となりかねないものは何であれ押さえ込もうとあがいて市民を弾圧し、数千人の死者を出した。さらに多くが今も投獄されたままだ。政権は国民の 対立を煽り、抗議行動をする人々に破壊工作者とかイスラーム主義者、外国の陰謀の加担者というレッテルを貼ることで、政権への支持をかき集めた。支持基盤 にさらに梃入れをするために、支配者一族の出身母体である少数宗派、アラウィ派の抱く恐怖を利用して、紛争に宗派的色合いをもたせた。体制側のこうした策 のために、街頭に出る若者たち――さらに、少数だが常にいる離反兵――がますます武器を手にするようになり、反体制派の多くも国外に財政的、政治的、軍事 的支援を求めることになった。武装反乱によって現政権支持者集団に少なからぬ死傷者が出て、政権は比較にならない強大な武力で反撃した。
〔訳注:父のハーフィズ・アサドが実権を掌握して以来。二男のバッシャールは2000年、父の死に伴い、後継大統領に就任した〕
一連の経緯は政権が抗議運動を貶め拒絶するのに都合がよく、政権は名目だけの改革から弾圧を強める方へ舵をきって悪循環に油を注ぎ、散発的な衝突が 内戦になりかけている。ある意味で言えば、政権はすでに勝利を収めたのかもしれない。不満を抱いて抗議する人々に武器をとらせ、国際社会に彼らへの支援を 提供するよう仕向けたことで、政権は自らの支配体制への最大の脅威と見えたもの、すなわち根本的な変化を求める、ほとんど常に平和的だった草の根の運動の 姿を醜くゆがめることに成功したのだ。一方別の意味で言えば、政権はすでに敗れたのかもしれない。シリア国民を広く代表する層を敵として扱い、国外の敵対 勢力に行動の正当化を与えたことで、打ち負かすにはあまりに強大な反対勢力連合が築き上げられることになった。少なくとも、バッシャール・アサドは父親の 遺産を無に帰したと言わざるを得ない。ハーフィズ・アサドは、(1970年の権力奪取から2000年の死まで)30年を超える執拗な外交によって、かつて は中東戦略ゲームの賞品扱いされていたシリアを、一人前の参加者にした。だがバッシャールの強硬姿勢で、1年も経たないうちに事態は覆り、当事者だったシ リアは諸外国などの勢力争いの場と化すだろう。
2月はじめ、政権はシリア第三の都市ホムスの反乱側地区に対して強力な武器を使用し、攻撃をエスカレートさせた。ホムスは宗教的混合のもっとも進ん だ都市で、蜂起の拠点となっていた。攻撃の強化を後押ししたのはロシアと中国で、両国は2月4日、アラブ連盟が構想し欧米が支援した国連安全保障理事会決 議の採択を妨げた。決議では暴力を非難し、交渉による解決として、アサドが代理人に権力を委譲した後、代理人が選挙に先立って統一政府を発足させるという プランを提案するはずだった。シリアの不安定化を恐れ、シリア国内の闘争を欧米との抗争とみなすロシア政府は、政権が現在の抗議運動と始まりかけた武装反 乱の両方を押さえ込むことに成功するだろうと考えている。そうすれば、シリア政権は国の支配を再び宣言し、少なくとも反体制派の重要勢力に政権側の出す条 件で――できればモスクワで――交渉に応じさせることができるだろうとロシアは踏んでいる。
支配力を失う
そうはなりそうもない。散発する流血の闘いの背後にあるのは、2300万人を抱えるこの国が政権の支配からすり抜けていく図だ。11ヶ月間、暴力的な威嚇と何の意味もない改革の提示をない混ぜにしてきた政権は、抗議デモをくじけさせることがまったくできなかった。
政権による改革の口約束は、しぶしぶなされた遅きに失するものである上に、ほとんど中身のないものであることが繰り返し明らかになった。たとえば 2011年4月、緊急事態法を解除したが、抗議する市民に対する銃撃や恣意的拘束は止まなかった。市民を迫害し、蜂起勢力のまます激しい怒りを買っている 治安維持組織を厳しく取り締まることは、政権の支配力を削ぎかねないとして、改革の対象からはずされた。支配者一族の正統性を欠く統治を揺るがしかねない 方策はすべて、一律に論外とされている。変えることができるのはもっとも意味のないものだけだ。確かに今後、バアス党の役割は低下することになるだろう が、そもそもシリアはすでにバアス党による一党支配の国家ではなく、一握りの一族が多数の治安維持組織によって支配する国家なのだ。彼らは長きに渡って、 米国の帝国主義とイスラエルの占領に対するレジスタンスを、明確な政治的ビジョンに代わるものとして利用してきた。もっとも従順な反体制派に対しては、立 法部門への参加と、おそらくは内閣への参加も認めるだろう。だが本当の決定は、どのみち大統領宮殿で行われる。政権は、改革の範囲を狭く設定した。政権に よる「対話」の呼びかけは、この成り行きに正当性をもたせることだけを狙ったものだ。
改革どころか、政権は事あるごとに社会を「瀬戸際」に追いつめてみせる。抗議が始まるや否や、治安維持組織の要員が宗派対立を警告するポスターを掲 げた。国営メディアは、抗議行動が最初に発生した南部の都市ディルアのモスクで武器が見つかったというヤラセ報道を流し、また4月18日のホムスでの座り 込みは小カリフ国家樹立の企てであると騒ぎ立てた。シリア市民に対するこうした操作は、内戦の脅威をちらつかせれば、市民も国外関係者も崩壊を食い止める 唯一の防波堤として現状の権力構造の保持に同意するに違いないと政権が踏んでいるということを意味する。10月のインタビューでアサドは、中東における 「激震」や「数十ものアフガニスタン」の脅威を繰り返し口にした。政権の言い分を煎じ詰めれば「わが亡き後は洪水」ということになる。
この恫喝が奏功するかどうかは疑わしい。あまりに多くのシリア市民が、抗議行動の中で(あるいは日常的に銃撃にさらされる葬儀の際に)殺害された友 人を葬り、政権の身の毛のよだつ刑務所(一貫して投獄者の気力をくじくどころか急進化させている)をたらい回しにされ、自宅の破壊や略奪を目の当たりにし ている。シリア市民は、どんな犠牲を払っても――すでに膨大な犠牲が出ている――決して止めるつもりはないと言う。国内戦線を修復不能なまでに弱体化させ た政権は、高まる国外からの圧力にも脆弱だ。特に、イランの影響力の要という役割を担うシリアとずっと敵対してきた米国とサウジアラビアにとっては、夢見 ることもかなわなかったシリアの政権交代の機会が訪れている。
政権が、自らの支配構造を破壊し、国を荒廃させ、シリア国外をも巻き込むことになる内戦を引き起こして、引き合わない勝利を手にすることはあるかも しれない。そうなれば、アラブの春というもっとも驚くべき民衆の力の獲得にとって悲しい結末となる。2011年、抗議行動がチュニジア、エジプト、リビア を揺るがしていたとき、シリア市民自身をはじめ多くの人々が、シリア人は政治への関心を失っているものと思い、蜂起は起こらないと考えていた。だが蜂起は 起こったのだ。ディルアで政権終われと落書きをした数人の小学生が拘束され拷問されたとき、北西部のディルアからイドゥリブで、地中海岸から東部のデイ ル・アル=ザウル(デリゾール)で、そして砂漠から肥沃な平野部に至るまで小さな町々や村々で、抗議する人々が街頭に出た。人々の求める「政権転覆」は、 当初は「体制の変革」を意味したが、エスカレートする暴力を受けて、「大統領処刑」へと変わっていった。現政権が何らかの未来を提示できるという希望は 粉々に砕け散った。
多数派であるスンナ派アラブ人を取り巻く民族的・宗派的多様性からすれば、シリアは崩壊する運命にあると見る人は多い。長く内戦に苦しむ分断された イラクやレバノンとの類似性がしばしば指摘される。だが、もし機会に恵まれればシリア社会は、ハーフィズ・アサド が1970年に無血クーデターで権力の座について以来支配を続けてきた世襲政治の終わりを目にすることができると考えるのはあながち間違いではない。すべ ては、深刻な政治的危機が、それに劣らず深刻な社会的苦境になりつつあるときに、社会が悪の権化に降伏するのか、それとも立ち向かうのかにかかっている。
闘い
シリアをめぐる闘いでは、二つの対称的な論法が相対している。政権とその支持者、同盟者にとっては、シリアは病弊だらけとまではいかないにせよ未成 熟な社会だ。彼らによれば――証拠は本当のものもあれば捏造されたものもあり、たいていは針小棒大に言われているが――、シリア社会には、反政府感情を煽 る、宗派的、原理主義的、暴力的な風潮があり、容赦ない権力構造でしか押さえ込めないとなる。バッシャール・アサドを追放するがいい。代わりにやって来る のは、内戦か、あるいは、トルコや湾岸諸国への義理に縛られ欧米に売り渡されたイスラーム主義者の覇権かどちらかだ。社会はまだ変化する用意が整ってな い、枷をはめた今の状態がちょうどいいのだと政権支持者は論じる。 ヒズブッラー(神の党)とイランは、人々の支持を醸成して継続的な影響力を確保しようとするかわりに、抗議行動を当初からもっぱら外国による陰謀という歪 んだレンズを通して見ることにし、政権がそれを弾圧できるというほうにすべてを賭けている。
対照的に反政権派は、政権の体質からすれば、いかなる変化であれあらゆる変化は望ましいと言う。アサド王朝は権力の座にある40年の間、次第にシリ アを一族の財産のように扱うようになり、国富を収奪してますます限られていく取り巻き連中に分け与えてきた。植民地主義から受け継いだ「分断して統治せ よ」の伝統に則って、政権は皮肉にも、社会の中の分裂を拡大させ、また真の国家意識の支柱となるのを恐れて国家組織を弱体のままとどめ、さらにアラウィ派 という一少数派を重用した治安維持組織を設けて、締め付けを強めてきた。数万人もの死者を出した1982年のハマへの砲撃が如実に示すように、反対派を時 には極度の残虐さで抑圧した。バッシャール・アサド がいなくなれば、シリアはようやく、抑えつけられてきた経済的潜在能力を発揮し、共同体間の自然な調和と開かれた民主的な政治体制への熱望を自由に表現す ることができると反対派は主張する。彼らに言わせれば、湾岸諸国と欧米は政権交代に、シリア国内だけでなく中東全域のすべての問題の解決を見ている。武器 の中継路をシリアに依存しているレバノンの抵抗運動ヒズブッラーがついに無力化され、イランも手ひどく弱体化され、いわゆる穏健派アラブ諸国が力をつけ る。
二つの論法は両立しないように見えるが、どちらにもいくばくかの真実はある。政権も国外の反体制派も互いに相手をすべての悪弊の元凶と非難しているが、どちらもステレオタイプに流されているところがある。
危機が始まって以来、政権はこれまでにもまして宗派性を強め、ますますほしいままに振る舞い、残忍性を増している。平和的な抗議行動が突きつける異 議申し立てを脅威と感じた政権の諜報・武装治安組織ムハーバラート――約束どおり裁判にかけられたメンバーはほとんど一人もいない――はしばしば、犯罪者 や武装集団を追うときよりも執拗に、非暴力の進歩派活動家を追跡している。ムハーバラート は国中で、暴漢や犯罪者――社会の中でいっそう過激で、腐敗した、卑屈な分子――を、シャビーハと呼ばれる武装民兵集団に雇い入れている。シャビーハは抗 議行動をする人々を恐ろしい戦術で威嚇しようとしてきた。反対派にとって象徴的なのはディルア出身の14歳のハムザ・アル=ハティーブが、連れ去られた1 カ月後に、殴られ性器を切り取られた遺体となって家族に返されたことだ。(政権は少年が逮捕されて殺されたことを一度も否定していないが、法医学者をテレ ビに登場させて、少年は実はジハード・ネットワークで活動していた強姦者だったと説明させた。)アサドは徐々に国家指導者の仮面を振り捨てて、相手を打ち 負かすためなら手段を選ばない陣営の最高権力者として発言するようになっている。
一方、シリア国民評議会(SNC)は、大部分が亡命者からなる反体制派の主要集団だが、2011年9月の結成以来、勇気を与えるような代替選択肢を 提示することができていない。大半が無名で経験もないメンバーは、政権のプロパガンダに対抗するすべをほとんどもっていなかった。前向きの政治公約でひと つも合意に達することができないSNCは、政権との一切の交渉を拒絶して「国際的介入」を求めているが、都合のいいことにそれが何を意味するか定義されて いない。このため、政権を嫌悪すると同時に外国の干渉も恐れ、リスクの高い政権移行を思って戦々恐々の多くのシリア市民は、不安を掻き立てられている。 SNCは、トルコの政治的狙いを恐れるクルドの諸党派ととりわけ軋轢があり、また、カタールとサウジアラビアの影響力への不信をもつシリア市民をも硬化さ せている。もっとも注目すべきは、SNCがアラウィ派と関係を築けていないことだ。アラウィ派の多くは、貧しく不満を抱いているが、暴力の大半に責任があ る治安部隊や軍部隊との結びつきのために報復を受けるのではないかと危惧して、反体制側につくのを恐れている。こうした人々をみな、先行きの不安の中に置 き去りにすることで、SNCは、政権の衰退を加速させる機会、さらにアサド失脚時に内紛を防ぐ機会を失っている。国際レベルでは、SNCは、すでに好意的 なトルコや湾岸君主国、欧米からの支持をとりつけることに全精力を注ぎ、政権の同盟国を無視・疎外することで、政治的な未熟ぶりを露呈した。
社会変化
今回、シリア社会の振る舞いはこれまでのどのステレオタイプにも合致しない。分裂傾向があるのは確かだが、その分割の境界は予測可能な線に沿ってい ない。1970年代後半と80年代初めのムスリム同胞団の率いた反乱、2000年のドゥルーズ・インティファーダ、2004年のクルド人の反乱といった過 去の蜂起は共同体色が強く、一般社会の不信を招いた。これに対して今日の抗議行動は、驚くほど基盤が広く、横断的だ。アラウィ派、特に知識人やふつうの村 の住民の間では、自分たちの共同体が政権によっていかに人質にとられているかを嘆く人が多い。ドゥルーズ派はほぼ半々に割れている。キリスト教徒は地理的 に散在しているが、武装治安組織の暴虐を現場でどれほど目にしているかによって、まったく異なる視点をもっている。ダマスカスとアレッポにいるキリスト教 徒はおおむね政権側だが、他の多くの地域では、抗議行動をする人々に少なくとも共感をもっている。サラミーヤ〔シリア中部ハマとホムスの中間〕の町に本拠 をもつイスマーイール派〔シーア派イスラームの一派〕は、最初に反体制派に加わった人々に含まれていた。そしてもちろんスンナ派アラブ人もみながみな反ア サドというわけではなく、たとえば北東部にいるシャワーヤ系諸支族はアサドを支持している。
また、紛争を共同体というプリズムだけを通して見るべきではない。抗議行動はハウラーン平原での地方色の強い底辺層の現象として始まったが、社会経 済学的境界を越えて、医師やエンジニア、教師も引き込んだ。運動は首都に拡大し、治安維持部隊の大規模な展開で開けなかった大集会の代わりに、散発的なデ モが起こった。財界は、財閥たちが初め慎重な保守的姿勢を示したが、政権が財界の利益を損ねていることに気づいた。ほとんどが――取り巻き資本主義者一派 さえも――、反体制派にずっと資金提供している。さらに思いがけないところにも断層線が現れている。一族の中で、上の世代は若い世代と比べると、自分の 知っている悪魔にしがみつきがちだ。夫婦の中でも意見が分かれる。女性は、安定と対話を望む傾向をもつ人がいる一方、夫たちが示しがちな姿勢以上に反対の 声を強く挙げる人もいる。
蜂起によって、長い間無気力でばらばらだったシリア社会の一部が、一種の復興を遂げつつある。抗議行動をする人々はすばらしく献身的で創造的だっ た。資金を集めて分配する委員会を立ち上げ、一人ひとりの死を少しもゆるがせにしない使命感をもって記録に残した。流血のさなか、洗練されたスローガンと 目を惹くポスターを次々に編み出し、国内各地の包囲された都市を支持するシュプレヒコールを上げ、新しい旗を縫い合わせ、ビデオやアニメで政権を茶化し た。ダマスカスに近いダラーヤなどの地域は、こうした人々の市民的抵抗の行動で知られるようになった。若き活動家で後に拷問されて殺害されたギヤース・マ タルは、地区の警備に派遣された兵士と治安部隊に渡すバラの花と水を注文していた。
政権が、反目の元になり得るものなら何でも利用しようとしたため、反体制派は、派内の暴力的、宗派的、原理主義的な要素を押さえ込むために力を注ぐ 必要があった。宗教的、犯罪的暴力や報復感情に駆られた暴力が増え、懸念もあったが、反体制派の努力が、社会を一つにつなぎとめた。メンバーの多数派の間 に、自分たちの国と尊厳と運命を手放すのではなく取り戻すのだという強い意志がなければ、抗議運動はずっと前に混乱状態に陥っていただろう。
この危機には紛れもなくシリア的な特徴が一つある。数時間のうちに集団で逃げ、武器を取って、外の世界に介入を求めたリビア人と違って、シリア人 は、武力に訴えたり、国際介入を求めるまで何カ月もかかった。また革命が、崇高ではあるもののある意味で束の間の栄光だったエジプトとも違って、シリアの 蜂起は、長い時間のかかる、骨の折れる仕事だ。抗議運動は徐々に形成されて、政権の一挙手一投足を研究し、また北西部のビンニーシュのような小さな町のこ とまでみなが知るほど、国のことを綿密に調べた。
実際に行われたデモだけでなく、表にはあまり見えない広範な市民社会が出現して、さまざまな形の支持を提供することで、デモが可能になっていた。ビ ジネスマンは資金と食べ物を提供した。医師は病院から薬を持ち出し、もっとも暴力の激しかった地域の野戦診療所に人を配置した。宗教指導者はおおむね、宗 派主義と暴力を抑制し続けようとした。蜂起が続く中、シリア市民は、今では深く根を張った反体制の文化を口に出し、ときには洗練された自治の形を発展さ せ、地方評議会を設立している。ホムスは、ルールも何もない武装集団の本拠地でもあるのだが、11人の執行部からなる革命評議会を発展させている。評議会 は、メディア対応から医薬品調達まで、危機のさまざまな側面に責任を持つ委員会を統括する。反旗を翻した共同体の内部には、シリア近代史のどの時期にも増 して、高い目的意識、連帯感、国民的団結がある。
数を増す武装蜂起さえも興味深い逆説を生み出している。急増する武装集団は、自らの正当性を、平和的デモを軍事的に保護する必要があるというところ から引き出しているのだ。やみくもに武器庫へ突進するのではなく、ほとんどの場所で武装は段階的に行われてきた。まず、治安部隊の急襲に備えて自衛用に家 に置いておく武器を買った。次に治安部隊がデモ隊への銃撃を始めたら応戦するために、武装した男たちの小集団が抗議デモとともに繰り出した。時が経つにつ れて、行動は純然たる防衛から攻撃的なやり方に変わっていった――標的は政府の検問所、政権の手先や情報提供者、軍の車列、治安部隊施設だ。売り言葉に買 い言葉の宗派間殺人が、シリア中部ではあまりに頻繁に起きている。だが、暴力の多くは、今までのところは野放図ではなく、抗議行動と民間人を守ることを行 動の基盤としているため、曲がりなりにも約束事の制約を受けている。
困難な時期が待ち受けている
言うまでもなく、ここまで述べてきたのはいい方の側面だ。政権側、反体制側ともに、暴漢と犯罪者が社会的上昇の手段、金儲けの手段、そして宗派間の 憎しみのはけ口として、この闘いを利用している。これは政権側の部隊に当てはまり、法と秩序を体現するのだというまやかしの主張は、その忌まわしい振る舞 いによって、あまりにたびたび反証されてきた。一方これは、地元の用心棒の雑多な寄せ集めである「自由シリア軍」の傘下で戦う複数の武装集団にも当てはま る。この「軍」への入隊者には、家族を守ろうとする父親、家族を亡くした若者、あるいは命がけで戦う離反兵がいる一方、戦闘的な原理主義者や根っからのな らず者がいる。今までのところ、後者〔原理主義者やならず者〕は主流ではないが、政権とその支持者、同盟者は彼らが前面に出てくればいいと考えている。論 理はおのずから明らかだ。支配エリートたちは、提供できる美徳がほとんどないので、自分たち以外にシリア社会から出てくるものは何であれ、自分たちよりは るかに悪いのだと証明しようと躍起になっている。このためアサドをほとんどヒステリックに崇めており、アサドの危機対応の誤りは支持者には問題にされな い。この社会をそれ自身から救うことができるのはアサドだけというわけだ。
だがシリア社会は、もっと早く権力構造が崩壊していた場合と比べて、移行に対応する用意が整ってきている。社会の崩壊を防ぐためにどのように自らを 組織すべきか学ぶことを余儀なくされてきたのだ。政権の「分断して統治せよ」戦術は、社会の広範な層が団結する鍵を握る要因となってきた。生き残るには、 地理的、社会経済的境界、共同体間の境界を超えて関係を築かなければならないということだ。とはいえ、革命勢力が成功を収めた暁には、団結の源が消滅し、 方向を見失うことになる。中東各地と同様、「政権の失脚」は、支配エリートが社会を閉じ込めていた抑圧的な行き詰まりの解決ではあっても、実りある変化へ の青写真ではない。
イランとヒズブッラーの後押しを受け、ロシアの支援に支えられた政権と、国外から軍事的ではないにせよ政治的支援を受けてますます力を増す武装反乱 とが対峙する中、政権が生き残りもせず、「失脚」もせず、徐々に弱体化して民兵集団になり果て、全面的な内戦に至る可能性も消えてはいない。だが、内戦状 態に陥る前に権力構造が崩れると仮定すれば、政治的移行をすぐに失敗させかねない脅威が少なくとも三つある
第一はアサドの権力を支えてきた基盤。大きく狭まったとはいえ、現に存在するのは動かし難い事実だ。政権は、街頭に繰り出してはいるのは多数派では ないといった(世界のどこかの国で国民の半分がデモをやったことがあるとでもいうような)、まやかしの論拠で抗議運動をはねつけているが、それとちょうど 同じように、反政権派も政権支持者のことを思い違いをした犯罪的な裏切り者の少数派市民だと叱りつける。実際は、政権が何百万もの反対派を無視してこの危 機を乗り切ることができないのと同じように、アサドに賭けてきた何百万もの人々――治安部隊将校、手先、ふつうの人々――から目を背けては、移行も成功し 得ない。報復にもっともさらされる人々、特にアラウィ派の保護、真の和解の機構、移行期の効果的な司法手続き、また治安維持組織の徹底的かつスムーズな再 編なくしては、すべてが水泡に帰す恐れがある。
第二に、シリア国民評議会(SNC)の実績から考えると、こうした移行でSNCが重要な役割を果たすべきかどうか懸念するのは故なきことではない。 SNCの指導的メンバーは、個人的なライバル関係に足を引っ張られて自滅を恐れるあまり明確な政治的立場を打ち出せずに、スポットライトを浴びることに 汲々としているように見える。唯一合意に達しうる権力分有の基準として宗派による割り当てに逆戻りしかねない。街頭に出ているシリア市民は、SNCの正統 性を、外交的圧力を取り付けられる能力に見ているのであって、それ以上のことは期待していないと明確にしている。だが、外の世界が既成の「代替選択肢」を 求め、中東の多宗派社会は結局宗派による権力分配に至るものだという思い込みが大勢を占めるなら、シリアは破滅に至る恐れがある。SNCを排除しないもの の、地元指導者の率いる組織、技術官僚、ビジネスマンを中心にして政治プロセスを築くほうが正統性があり、成功の可能性も大きいだろう。
最後に、抗議行動をする人々がますます必死になるあまり、外に支援を求めると、外の世界が救世主ごっこをして事態を悪化させる危険がある。支援の要 請は、悪魔との契約よりも悪い。さまざまな点で互いに意見の合わない多くの悪魔たちとの契約ということになるからだ。湾岸君主諸国、イラク、トルコ、ロシ ア、米国、イランなどはみな、アサド政権の運命に戦略地政学的利害関係をみている。関与が大きくなればなるほど、シリア市民が自らの運命を制御できなくな る。政権による極端な形の暴力にさらされているふつうの市民が、何としてもこの緊急事態を終わらせようとして、何らかの外国の介入を求めることはまだしも 理解できる。だが、外からのどのような「支援」がもっとも害が少ないかを冷静に慎重に見極めることが必要とされている今、国家指導者を気取る亡命中の反体 制派連中が、ただただ介入を求めるなどというのであれば、弁解の余地はない。
中東でこの3つのすべてについて実例を示してくれるケースがすぐ近くにある。イラクだ。イラク社会の中で相対的に小さな少数派であっても、それを排 除した政治プロセスは、国全体の災厄につながった。社会基盤をもっていなかったのに、目に見える唯一の既存の「代替選択肢」として国際的な支持を得ていた 帰国亡命者の一団が、すばやく移行を乗っ取ると、共同体を勘案して算盤をはじき、自分たちの間での権力の分配のみに合意した。彼らがやった戦利品の分捕り は、徐々に国家全体に蔓延し、最終的には内戦につながった。この悲劇を監督していた米国は、イラクを本来の姿とは似ても似つかないものに変えることしかで きなかった。イラクは今では、占領者米国が当初、イラクとはこういうものだと考えていたまさにそのイメージどおりの、ありとあらゆる宗派的な根深いステレ オタイプに当てはまっている。
つまるところ、国内レベルでみれば、シリアはポスト植民地時代に終止符をうつ闘いに入ったのだ。問題は単に「政権」を転覆させることではなく「体 制」を根こそぎ変えることだ――ニザームというアラビア語はまさにこの概念を二つとも含んでいる。現行の体制は、シリア市民を、分裂した共同体間や中東で の権力争いの人質とすることに基盤を置いている。実際、政権にわずかでも正当性があるとすれば、国内の共同体各勢力や外国勢力を対立させ続けてきたことに もっぱら由来し、その間、真の国家建設と責任ある指導体制は犠牲にされてきた。20世紀半ばの革命の活気の中で植民地主義の遺産と決別しようとした前回の 試みは挫折し、限られた政治エリートと軍という集団におさまってしまった。今日それと違うのは、広範な一般市民の運動が目を覚ましたことだ。視野の狭い利 害や大仰なイデオロギーではなく、自分たちの富と尊厳と運命がまったく奪われているという意識がその原動力になっている。
ある意味で、この覚醒をこそ政権は弾圧してきたのだ。外国の干渉は事実だが、今シリアにあるのは、陰謀ではなく、動き始めた社会だ。その目指す道筋 に政権が向かうことは決してない。この先の道のりは険しく、シリアもそして中東をも内戦の迷路に迷い込ませる危険が現実にある。しかし、あまりに多くのシ リア市民にとって、逆戻りはあり得ない。政権には、はるかに安全に前進できる道をつける猶予が1年与えられていたのだが、旧態依然の論法にますますしがみ つき、結局、自らに歴史的な行き詰まりの役を振り当てている。
原文
Beyond the Fall of the Syrian Regime
Peter Harling and Sarah Birke
Znet掲載: http://www.zcommunications.org/beyond-the-fall-of-the-syrian-regime-by-peter-harling
初出:Middle East Research and Information Project: http://www.merip.org/mero/mero022412